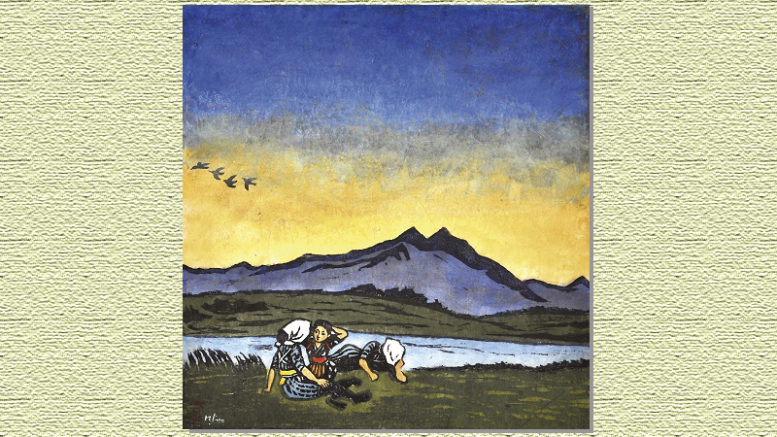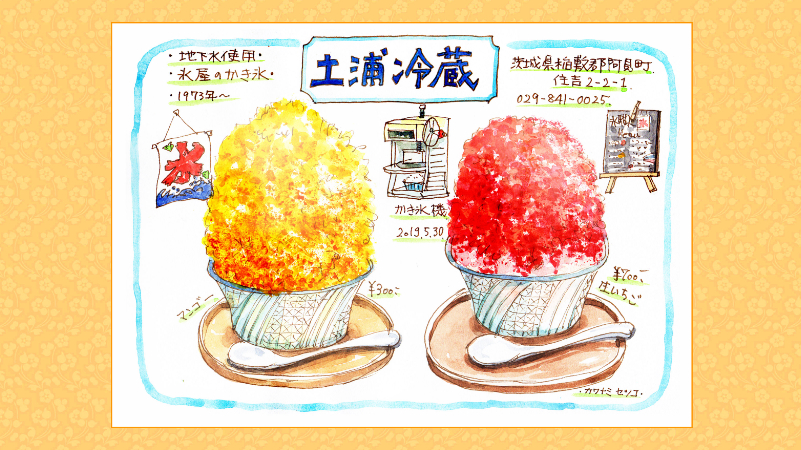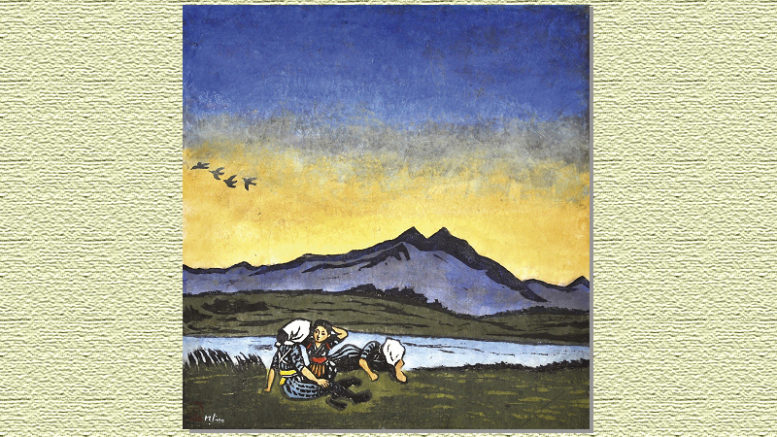【コラム・室生勝】人生会議(ACP)とは、もしものときのために、あなたが望む医療やケアについて前もって考え、家族や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取り組みのこと―と、厚労省は説明している。このチームは、主治医である病院医やかかりつけ医、病院看護師あるいは訪問看護師、ケアマネジャー、ヘルパーらからなる。
後期高齢者となると、自分ではまだ元気だと思っていても、最期はどうなるのだろうかと心のどこかで思い、苦しまないで最期を迎えたいと願っている。それを家族に伝えておかねばならないと思うが、言い出せない人が多いのではないだろうか。そのきっかけを作ってくれるのがACPだ。
初めてACPを経験する人には、桑名市の冊子をお奨めしたい。同市のホームページを見ると、「今から始めましょう! 元気な方でも、いつ、もしもの時……」と勧めているが、本人は言い出しにくい。お盆や彼岸のときに、祖父母の思い出話から始めてみるのはどうだろう。
葬儀や納骨の思い出から始め、最近話題の家族葬や樹木葬などについて話し、本人の希望を聞き出す。話が進めば、本人にもしものときにどうすればいいか、聞いてみよう。
要支援・要介護の人の場合は、本人と家族に現在の病状と将来起こりうることの説明を主治医に依頼するか、ケアマネジャーに相談する。桑名市のテキストには、まず、本人がこれから先どのように暮らしていきたいか、本人の目標・希望・想いについて整理することを勧めている。
目標や希望は病状の変化で変わることがある。年1~2回、家族が集まるたびに話し合うとよい。最期を住み慣れた家と決めていても、病状によっては病院で迎えるときもある。何回かACPを開いて、想定されることを考えておく必要がある。要支援・要介護の人は、主治医を含む医療・介護ケアチームが加わったACPを開いてほしい。
カードを使った「もしバナゲーム」
2013年、日本でACPを広く国民に知ってもらおうと、啓蒙活動を始めたのは亀田総合病院疼痛(とうつう)・緩和ケアチームである。その後、日本緩和医療学会で取り上げられ全国に広まった。2年ほど前から、地域の病院や市町村の在宅医療介護連携推進事業で医師を含む多職種の研修が始まったばかりだ。
亀田総合病院の医師たちは、米国の「Go Wish Game」の日本語版「もしバナゲーム」も作った。若い人たちの「恋バナ(恋のはなし)」を拝借したらしい。36枚からなるカルタやトランプに似たカードゲームである。
「人生の最期にどう在りたいか。だれもが大切なことだとわかっている。でも、なんとなく『縁起でもないから』という理由で、避けてはいないだろうか。このカードを使えば、そんな難しい話題を考えたり話し合うことができる」と勧めている。私たちのサロンでは、桑名市のテキストによる勉強のあと、「もしバナゲーム」を毎回、全員が交替でやっている。(高齢者サロン主宰)
➡室生勝さんの過去のコラムはこちら