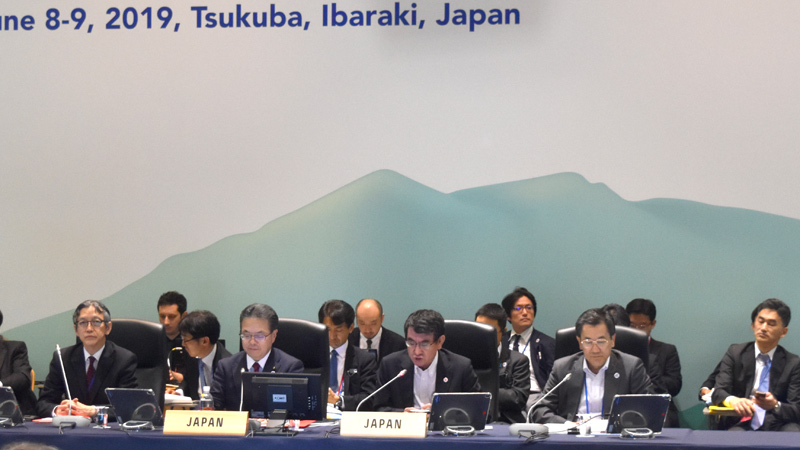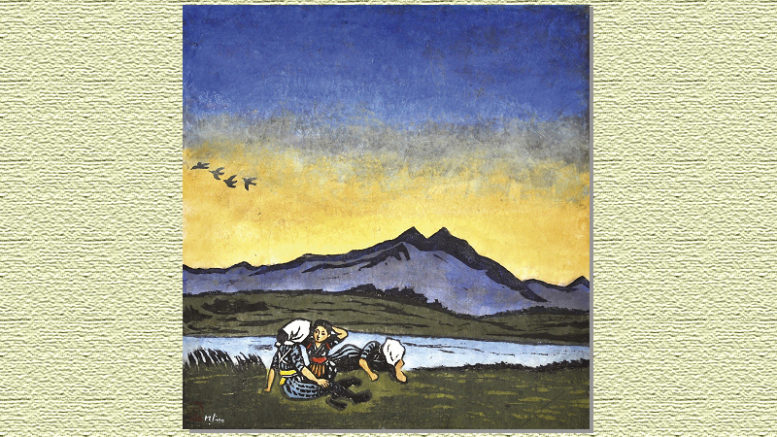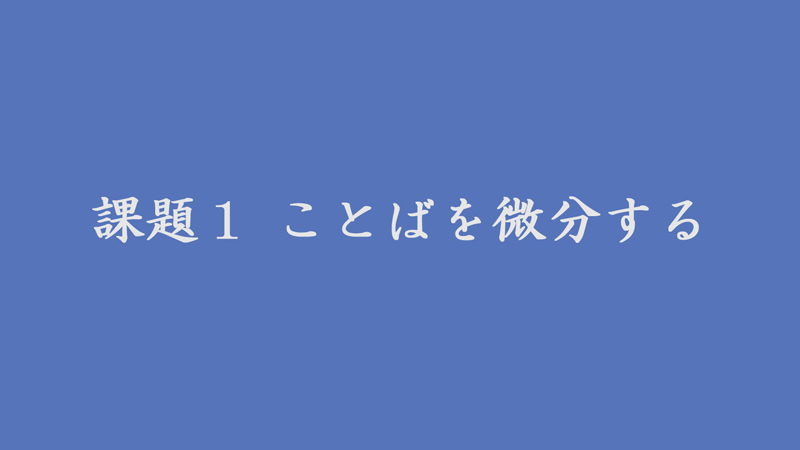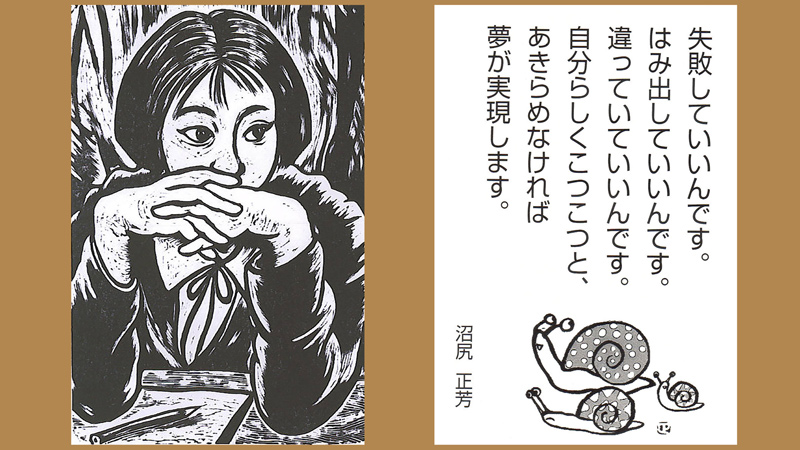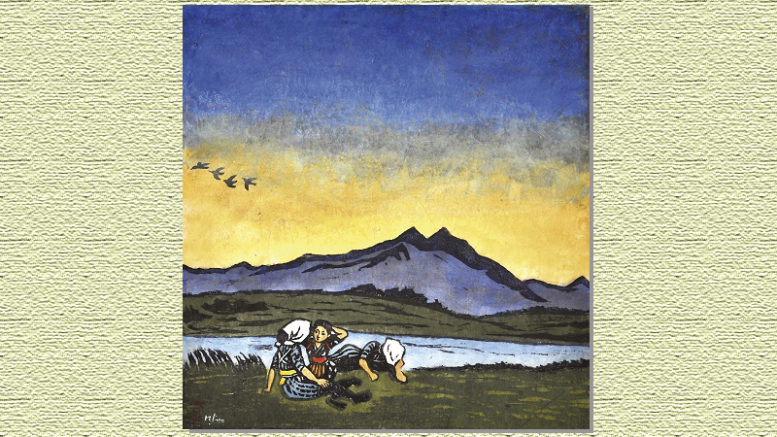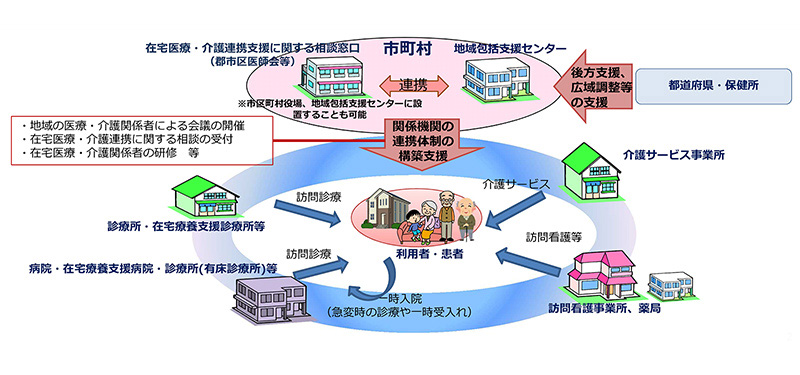【コラム・及川ひろみ】全国一の栗の産地である茨城県、梅雨の季節は栗の花が見ごろです。花は木を覆うように白く垂れ下がった花を咲かせます。しかし垂れ下がった花から、どのようにして栗が実る―栗のイガができるのでしょうか。不思議ではありませんか。
白いたくさんの花は雄花で、その根元をよく見ると小さなイガの赤ちゃんが見られます。これが栗の雌花です。栗の花には独特な臭いがあり、これに誘われ、いろいろな虫がやって来る、いわば虫媒花(ちゅうばいか)です。晴れた日なら、ベニカミキリ、アカシジミなど美しい虫たちが白い花にやって来ます。
ところで、青森県にある縄文時代の大規模集落跡、三内丸山遺跡には、シンボル的な三層の掘立柱の建物が再現されていますが、その柱は栗材でできています。直径1メートル近くもあります。当時、この辺では栗が栽培されていたことも明らかになっています。
童謡「大きな栗の樹の下で」と歌われている栗ですが、今は太い木がほとんど見られません。里山でも普通に見られる栗ですが、大木になることはなく、同じ仲間のコナラやクヌギに比べても若くして枯れます。
三内丸山遺跡の不思議 掘立柱は栗の大木
原因は、シロスジカミキリ、ミヤマカミキリだといわれています。これらの虫は栗畑でも代表的な害虫です。枯れた栗の木を伐(き)ってみると、何本もの太いトンネルが見られますが、これは日本で最も大きなカミキリムシ、シロスジカミキリや、やはり大型のカミキリムシであるミヤマカミキリの幼虫(テッポウムシ)が作ったものです。
シロスジカミキリのメスは丈夫な顎(あご)で、木の幹を一周するように樹の堅い皮に帯状にたくさんの穴をあけ、その後、体を半回転させ、腹の先端にある産卵管を穴に差し入れ一卵ずつ産卵していきます。ミヤマカミキリは樹皮のくぼみに卵を産み付けていきます。
1本の樹に何匹もの幼虫がトンネルを掘ることから、カミキリムシの幼虫が入った樹は次第に弱り、大風などで倒れます。それで栗の木が大きく育つことがほとんどないのです。
しかし、三内丸山遺跡ではどうして栗の樹が大きく育ったのでしょうか。最近の考古学の研究によると、シロスジカミキリは縄文時代以降に日本に入って来た渡来の生き物だったのではないかといわれています。
さて9月になると、里山には芝栗、山栗と呼ばれる小粒の栗がたくさん実ります。甘いですよ。しかし、甘いものにはこれを好む生き物がすばやくやって来ます。風が吹いた朝などに、落ちたばかりのピカピカ光った栗を拾い、生でかじる。里山の楽しみの一つです。(宍塚の自然と歴史の会代表)
➡及川ひろみさんの過去のコラムはこちら