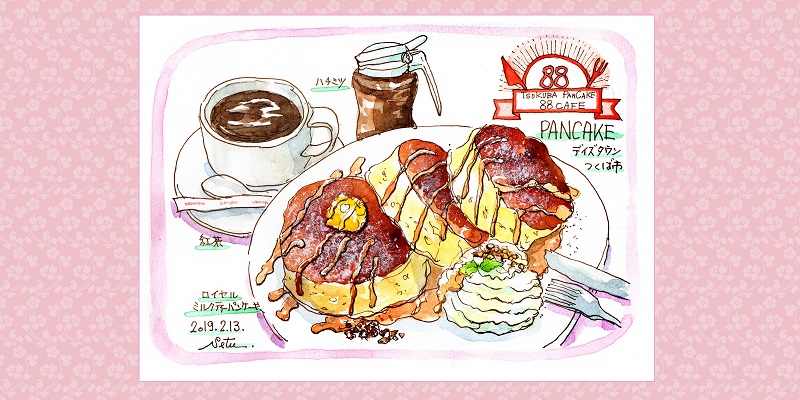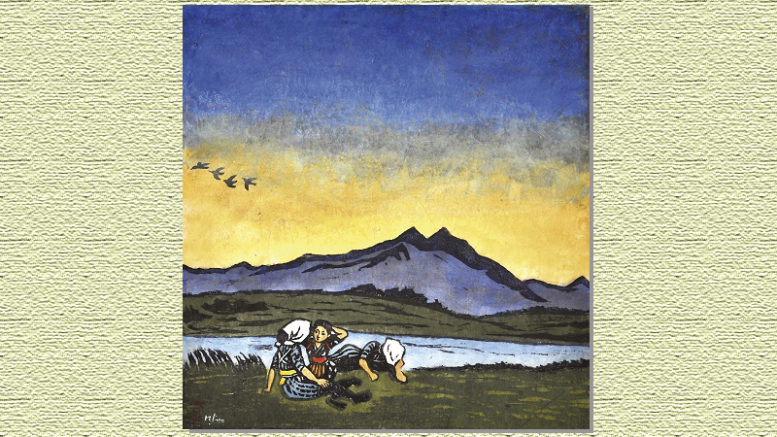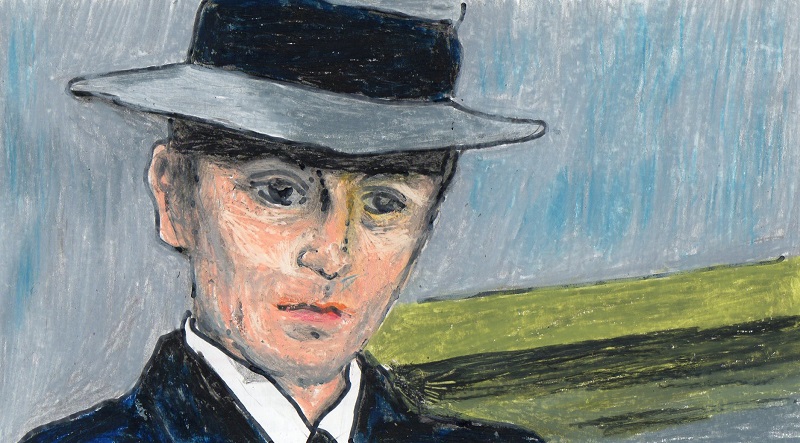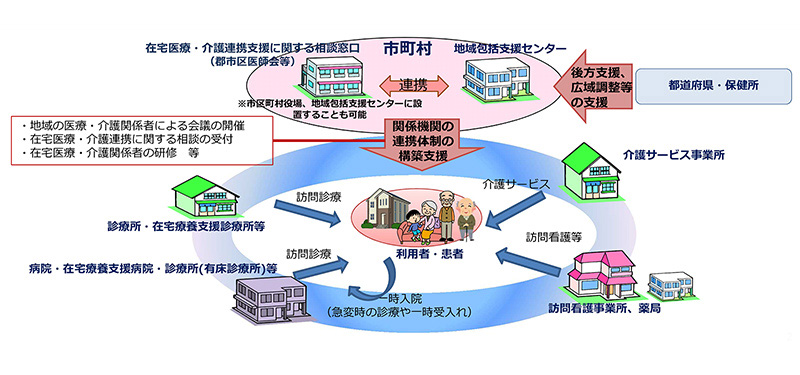【コラム・及川ひろみ】茨城町の涸沼(ひぬま)は汽水湖で、シジミ、ヤマトシジミが名産ですが、実は里山にもシジミが生息しています。淡水域に生息するシジミ、マシジミが小川にいます(いました)。以前、地元の人から、40~50年前の宍塚大池からの小川にはシジミがいて、よく食べたとの話を聞き、小川の底をザルで探ったのは1990年ごろのことでした。すると、普段見慣れた黒いシジミとは違った、緑色がかったシジミがたくさん採れ、びっくり。
一晩水にさらし砂を吐かせ、食べてみました。甘みがある美味しいシジミでした。大池から流れ出るこの小川の底は砂地です。里山からの山砂が流れ出たもので、宍塚大池の底も砂地です。貝は入・出水管を上に、貝の下部からは白色の足を延ばし、砂の中に立つような形でプランクトンを捕らえていますが、川底が砂地でなければ生息できないのです。
さてマシジミをよく見ると、表面に年輪を思わせるしわが見られますが、年に数本のしわを作りながら、寿命は3年ほどと言われています。
ところで、上高津貝塚に展示された紀元前4000年の縄文時代の貝塚の貝層を見ると、最も多く見られる貝がヤマトシジミです。当時から、重要な食材であったことがうかがわれます。江戸時代、「シジミ売り、黄色なら高く売り」という川柳がありました。顔色などが黄疸(おうだん)ぽく見える人には高く売るという意味です。シジミに多く含まれるオルニチンは肝機能低下、黄疸などの人が用いるサプリメントですが、その機能性成分は早くから知られていたのですね。
厄介なタイワンシジミに入れ替わる?
さて、宍塚のシジミ、どうやら最近では外来種であるタイワンシジミに入れ替わってしまったようです。2010年10月、貝類(カタツムリも含まれます)の観察会を行ったとき、講師の千葉県立中央博物館黒住耐二さんから、宍塚のシジミはタイワンシジミだと考えられるとの指摘を受けました。
そのころ、すでに各地のマシジミがタイワンシジミに置き換わっていると聞きました。タイワンシジミは精子側の遺伝子のみが遺伝する(雄性発生)という大変厄介な生き物で、また生命力、繁殖力も大変強く、生息域の拡大もすさまじいと聞きました。
マシジミへの遺伝子汚染も問題で、近く特定外来生物に指定されるだろうとの話もあります。またマシジミと比べると、うまみがなく、人気がないとも聞きます。ひところ、宍塚の小川では貝採り用の道具(ジョレン)持参でシジミを採る人もいましたが、最近は見かけません。(宍塚の自然と歴史の会代表)
➡及川ひろみさんの過去のコラムはこちら