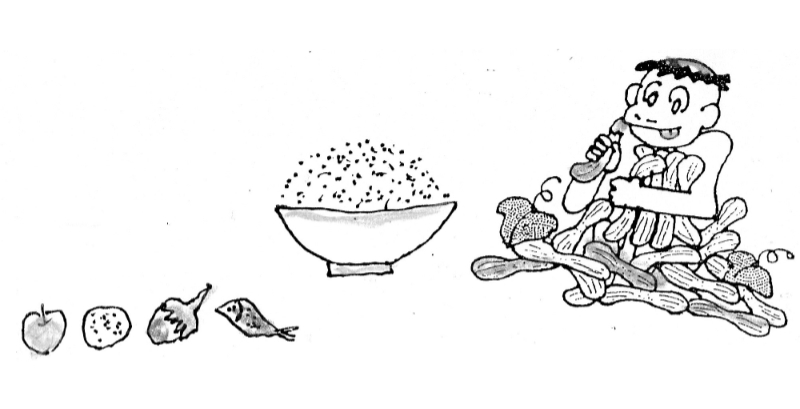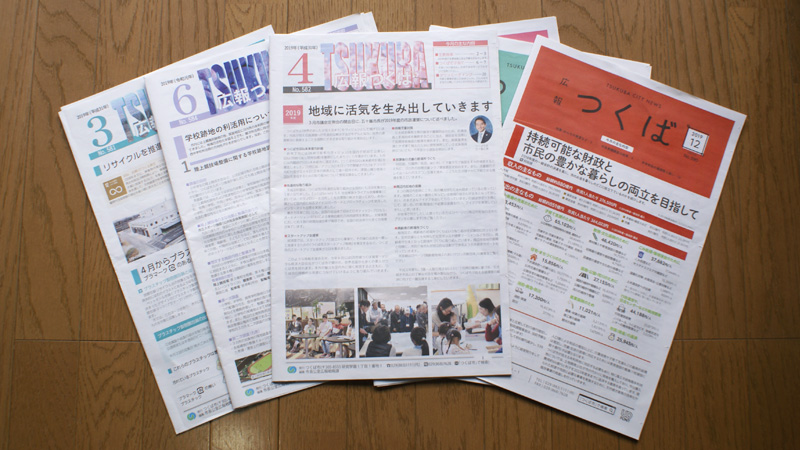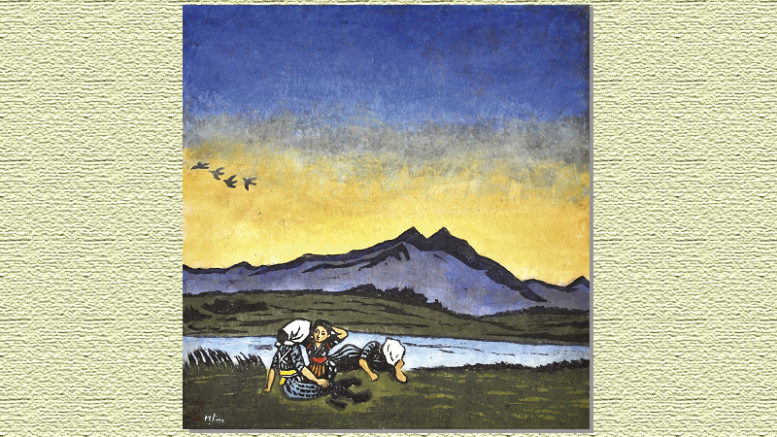【コラム・冠木新市】28年前つくば市に引っ越してきた時、桜川流域での土浦花火大会を見に行った。10月のひんやりした時期に開催されるのに、見物客の熱気は凄(すご)かった。だがそのころの私は、地方の花火大会の一つとしか思っていなかった。後に、土浦の花火大会は「大曲の花火」(秋田県)、「長岡まつり大花火大会」(新潟県)と並ぶ日本3大花火大会であり、また赤字を覚悟して花火師たちが技術を競う「土浦全国花火競技大会」であることを知った。
日本の花火は世界一だから、土浦の花火は世界一といえるわけだ。しかし長い間観察してきたが、花火客を当て込んで一夜にして稼ごうとする雰囲気が強く、花火弁当コンテストや市博物館での花火記念展示はあるものの、世界一の文化を象徴する煌(きら)めきにはほど遠いのが現状ではないだろうか。
大正14年(1925)、神龍寺の住職秋元梅峰(あきもと・ばいほう)が不況に苦しむ土浦を見て、花火大会をすれば莫大な収入が一夜にして得られ、税金滞納、金融途絶から救えると考えたのが始まりであるという。95年が過ぎた今でもその原点は息づいているといえるが、もっと運営側でも花火師の花火玉に学ぶ工夫があってもよいのではないか。
平成26年(2014)、人口8万人の秋田県大仙市で、市と商工会と大曲商工会議所が「花火創造産業計画」をぶち上げた。5カ年計画で交流人口を272万人引き上げ、316億円の経済効果を見込む。2017年には、6日間にわたり「第16回国際花火シンポジウム」を開催し、38カ国449名が参加した。
経済的な面だけではなく、「花火を伝承する資料館の設立」「花火師に対する技術講習会の実施」「新たな特産物の開発」「花火創造産業の設立」「NPO法人大曲花火倶楽部による花火鑑賞士を認定」など、いろいろな仕掛けを打ち出した。実態は知るよしもないが、現在「大仙市花火産業構想第2期」が進行中だ。
C・イーストウッドの『荒鷲の要塞』
『荒鷲の要塞』(1968)は、アリステア・マクリーンの冒険小説を映画化した2時間35分の大作である。物語は、アメリカの将軍が飛行機事故でナチスの捕虜となり、アルプス山脈のロープウェイでしか行けない断崖絶壁の「鷲の城」に閉じ込められる。連合国側は、機密漏れを防ぐため、イギリス情報部スミス少佐(リチヤード・バートン)とアメリカ軍のシェイファー中尉(クリント・イーストウッド)らを将軍救出のために派遣する。
「侵入」「将軍救出」「脱出」の構成で描かれる冒険だが、2人の主人公の行動が淡々と描かれ、ドンパチは後半に集中する。しかし、黙々と爆弾を仕掛けていく作業を見ていると、妙にワクワクしてしまう。今では地味に映る作品かもしれないが、仕掛けられた爆弾がどう爆発するのか想像を刺激する。要塞の大爆発シーンに壮快感があるのは、それまでの仕掛けが効果を上げているからだ。
筒を横に向けると大砲という戦争の道具も、上に向けると花火という平和の芸術。花火玉は化学と数学と美術が結晶したもので、頭脳と忍耐力を要するためゲーム世代の若者の教育には絶好の素材である。
令和元年、人口14万の土浦市に女性市長が誕生した。これをきっかけに、「世界一の花火都市」ビジョンを華麗に、盛大に打ち上げてもらいたい。サイコドン ハ トコヤンサノセ。(脚本家)
➡冠木新市さんの過去のコラムはこちら