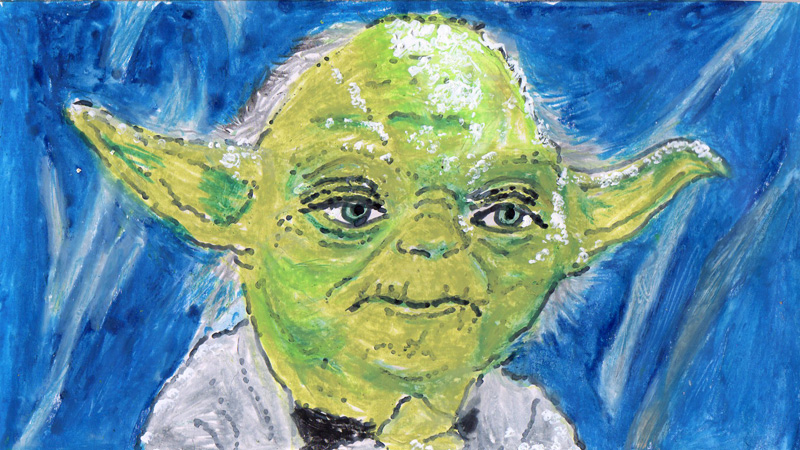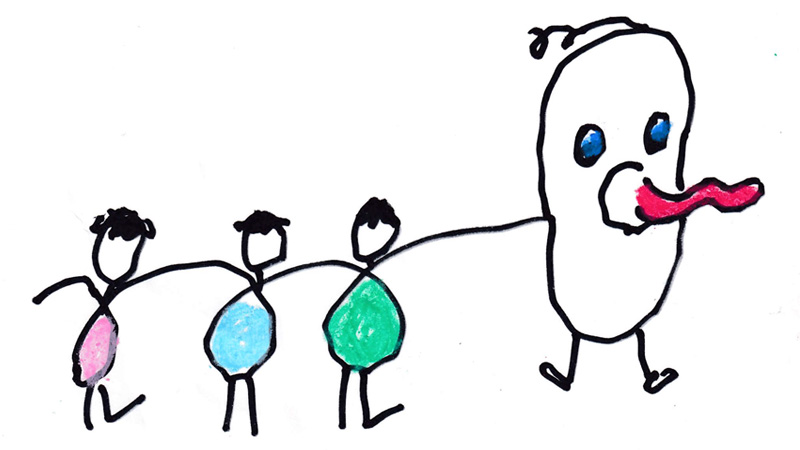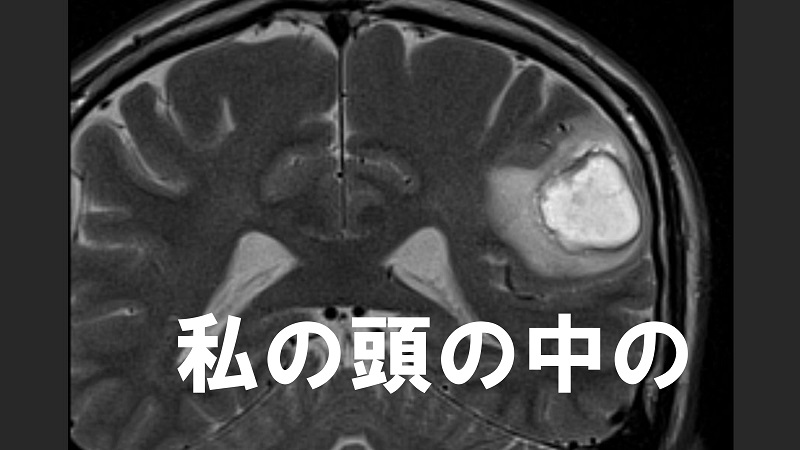【コラム・沼澤篤】12月に入り、霞ケ浦の湖内や周辺で越冬する鳥類の顔ぶれが出揃(そろ)った。湖面ではゴマ粒を撒(ま)いたように、カモ類が翼を休めている。日本野鳥の会茨城支部などの調査で、20種近いガン・カモ・アイサ類が霞ケ浦湖内と周辺で一冬を過ごすことが分かっている。
一見すると変化に乏しい広大な湖面で、なぜ多種のカモ類が生息しているのだろうか。生物は生態系の中でニッチ(生息場所)を求めて種分化しているが、変哲のない湖面で多種のカモ類が生息しているのはなぜか。
私は、その疑問を鳥類学者に問いかけたことがある。彼によると、カモ類はシベリアなどの繁殖地で、採餌(さいじ)、営巣(えいそう)、子育て、成長などの生活史においてそれぞれ、地形、水場、植生などの多様な生態系に適応して種分化しているのであり、日本列島の湖沼は越冬の場に過ぎないとの解説が返ってきた。なるほど。
そのように見ると、霞ケ浦で越冬中のカモ類は姿形や色彩だけでなく、食性や行動が異なっている。雑食性のマガモ、コガモ、ヒドリガモなど。魚貝類食のホシハジロやキンクロハジロなど。プランクトンや小魚食のハシビロガモなど。雑食性のカモ類は水面近くの餌を食べるので、潜水できない。魚貝類食のカモ類は深く潜水できる。ハシビロガモのくちばしは平たく、内部は櫛(くし)の歯のような構造をして、水中、水面の細かい餌をろ過して摂食する。
日常生活と霞ケ浦との関係性を考える
一見、平坦に見える霞ケ浦の湖内でも、浅場(あさば)、深場(ふかば)、波が静かな入り江や河口、植生の有無、好適な餌の有無などの条件によって、カモ類は越冬場所を変えている。ベテランのバードウオッチャーは岸辺から双眼鏡や望遠鏡で観察し、カモ類を識別するが、姿形だけでなく、生息場所をよく知り、出現する種類を予測しているのである。
霞ケ浦ではカモ類だけでなく、葦原(あしはら)、柳などの湖畔林、水田、蓮田などの湿地で、四季を通して、サギ類、クイナ類、シギ類、チドリ類、ヨシキリ類など、様々な野鳥が生息し、繁殖し、世代交代している。霞ケ浦の生態系の多様さと豊かさが生物種の多様性を保障している。それは、霞ケ浦という自然の恵みであり、人間が共存していくべきものである。
霞ケ浦の生物多様性を考える時、関心が、どんな生き物が生息しているのかに集まりがちだ。その生き物が希少であるほど注目され、保護運動の対象になる場合もある。しかし、霞ケ浦の生物はなぜ多様なのか、多様性を守ることの意味、生態系や生物の多様性の本質論まで認識が深まらない。
霞ケ浦の生物に興味がある人でも、植物、魚、鳥、それぞれの識別を対象にしている例がほとんどである。大多数の方々は霞ケ浦にも、そこでどんな生物が生息しているかも、そして水質をはじめとする環境問題にも無関心でいるのが現実である。霞ケ浦流域に暮らしていることの自覚さえない方が多い。上水道の水源や生活排水の行き先をはじめ、自分の日常生活と霞ケ浦との関係性を考えることから始めてほしいものだ。(霞ヶ浦市民協会研究顧問)
➡沼澤篤さんの過去のコラムはこちら