【コラム・浅井和幸】いくら負けようとしても勝つことが出来ない「最弱のオセロAI」というものがあります。先日、そのサイトの勝率を見たら、AIの「4254勝1671337敗234引分」でした。簡単なので、ぜひ、皆さんも楽しんでみてください。そして、負けるように頑張ってみてください。
これが、なかなか負けられないのです。面白い話なのですが、このオセロゲームに負けられる人は、オセロがある程度以上強い人なのです。弱い人が負けるのではなく、「負けることが出来るのは、強い人」なのです。
強い人は、勝ち方を知っている。だから、負け方も知っているのです。これはオセロに限らず、私たちの日常にも似たような場面はたくさん転がっています。
その場の口ゲンカには勝ったけれど、何一つ得るものがなくイライラするだけということはないでしょうか? 怒鳴ったり、クラクションを鳴らしたりして相手を脅かしたところで、到着時間が早くなるどころか、余計なトラブルにつながることもあるでしょう。
何かの活動をしている人が、思い通りにならないから行政窓口に怒りをぶつけ、担当者に謝らせたとしても、目的を達成することとは程遠い時間を浪費しただけになるかもしれません。
中長期的な勝ち、目的に目を向ける
家族や友人、職場などでのケンカはこのようなことが多いと感じることはないでしょうか。その場の言い争いに勝つことを優先して、結局は何の目的も達成できないどころか、その後も話しづらくなり、居場所をなくしてしまったり、次の要求が出来なくなったりしてしまいます。これらは、「勝ち方を知っている」とは、到底言えないでしょう。
お互いが同程度だからケンカになるのだと耳にすることがあります。それはまさにその通りで、相手が、自分よりもずっと弱いとケンカになりません。
例えば、自分と同じか少し目上の人がずけずけと悪口を言ってきたら、例えば「服のセンスが悪いな」と言ってきたら腹が立って、その怒りをぶつけたくなります。感情のままに動くと、たとえ言い争いに勝ったとしても損をすることのほうが多いですよね。
これが、幼いお子さんに「服のセンスが悪いね」と言われたら、大人である私たちは、余裕を持って「そう? どこを直せばいいかなぁ?」なんて言いながら、下手に出ることが出来るのではないでしょうか。短期的な勝ち負けにこだわらず、中長期的な勝ち、価値、目的に目を向けることも考えたほうがよいですよね。
そういえば、「最弱のAIオセロ」ですが、一生懸命にこちらに負けてくれるように感じられて、健気とか、可愛いとかの好意的な感想もあるみたいですよ。(精神保健福祉士)
➡浅井和幸さんの過去のコラムはこちら





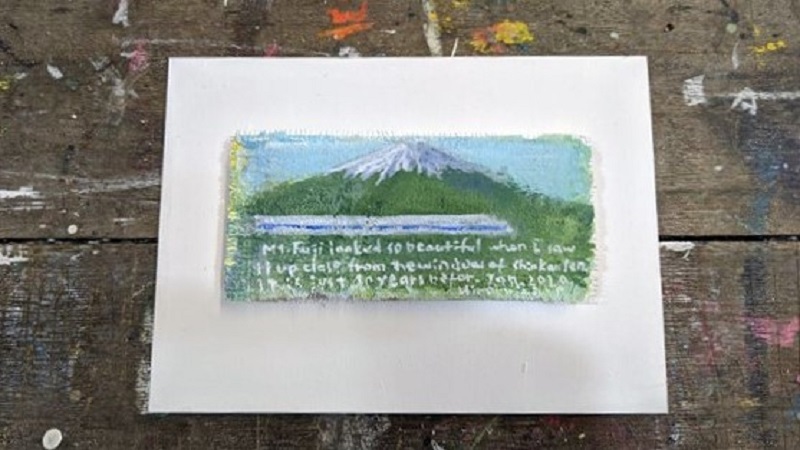
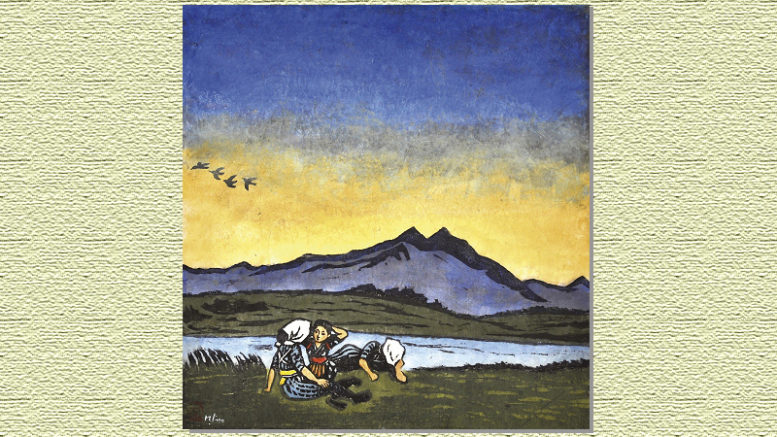

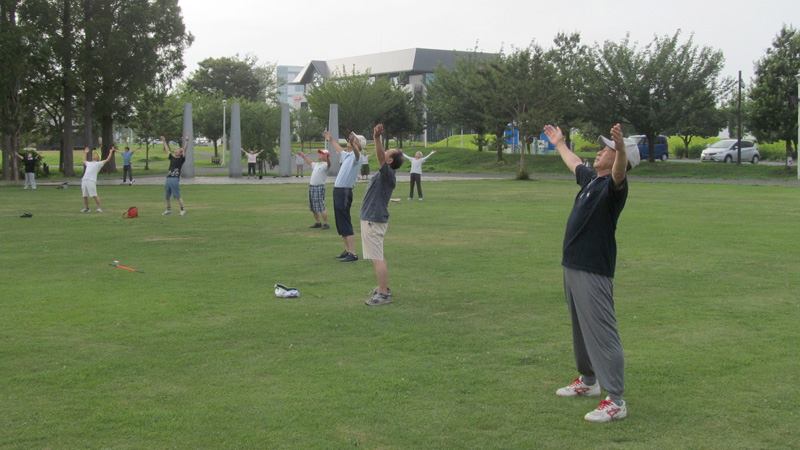


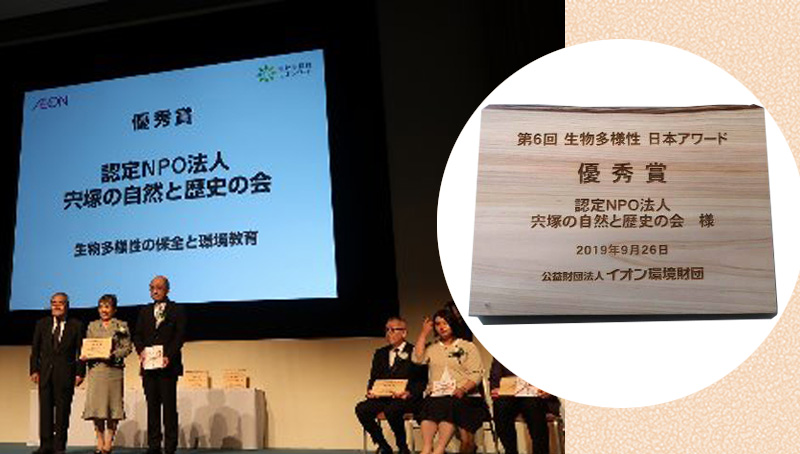






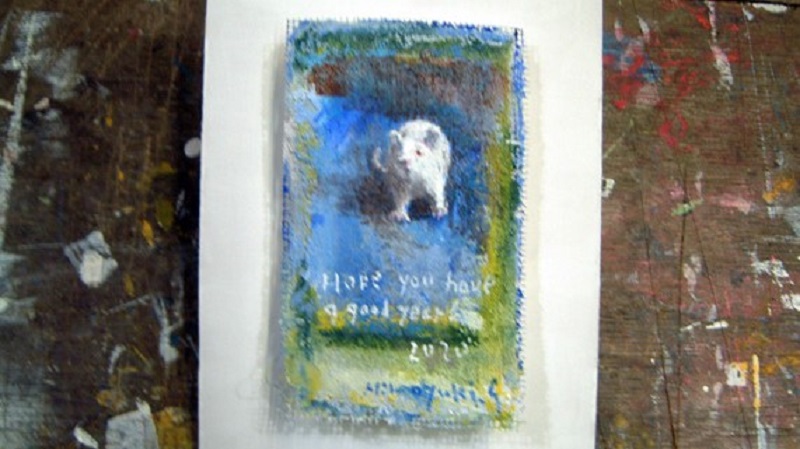
![a312f08bb111a4aba6135d19057bce62[1]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2020/01/a312f08bb111a4aba6135d19057bce621.jpg)