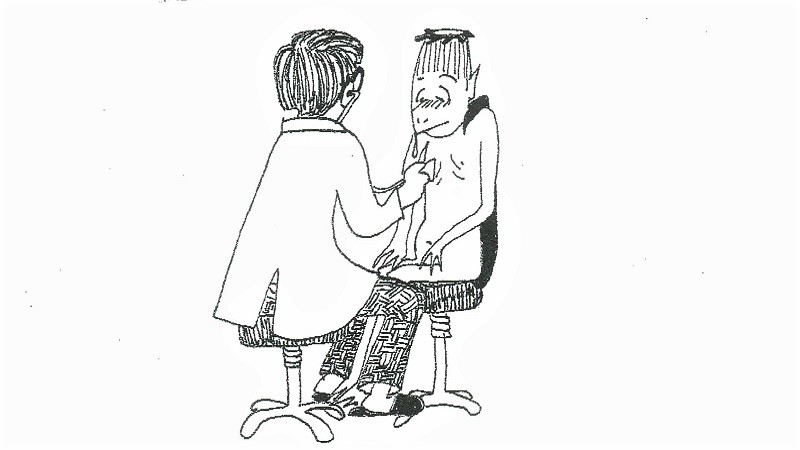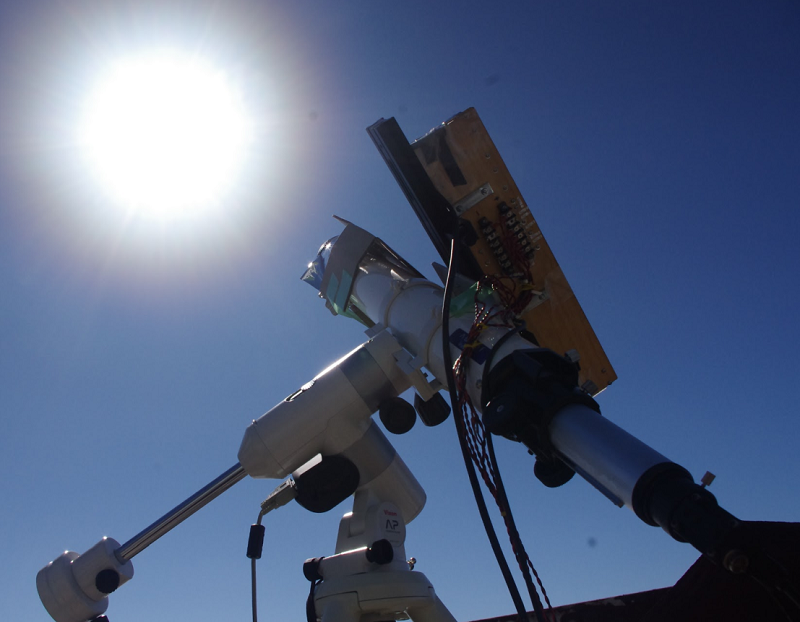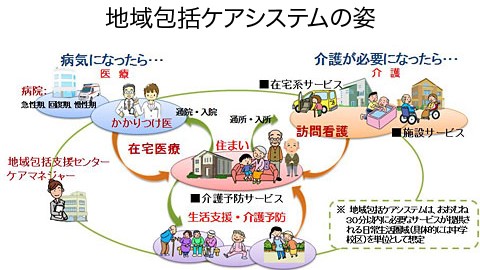【コラム・及川ひろみ】宍塚を訪れる多くの方が、土浦学園線からわずかに入った所に人工物がほとんどなく、谷津田、大池、雑木林が広がり、坂を上り、小道を曲がると、次々変わる景色、奥行きのある景観に大変びっくりされる。それもそのはず、ここは東京駅から筑波山麓までで最も広い里山なのです。
宍塚の自然と歴史の会は1989年に発足しました。それからほどなく、会員が100人を超えました。
そのころ、「確かにいい所だけれど、いい所ってどう言うこと」と質問されました。わたしたちは、宍塚の自然の特徴を知るには調べることが必要だと、仲間たちと足しげく通い、調査を行いました。(会員には昆虫、野鳥、植物、水質など、多くの分野の専門家が加わっていました。現在もそうですが)。なるべく標本に残すべきとの意見もあり、かなり克明な記録を残し続けました。
ある時、宍塚大池の水源である「泉」を案内しますよ、との申し出を地元の方から受け、これまで足を踏み入れたことのない谷津の奥、池の周りの泉を見て回りました。池の縁の大木の根元から絶え間なく水がしみ出していました。「サメゲの泉」と呼ばれる池の西に広がる谷津の泉は、地下から水がこんこんと湧き出ていました。
90年6月から、毎月、この水を採取、水温や水質を調べたところ、この泉は年間を通して13度から16度と水温がほぼ一定でした。泉のそばには、水が飲めるように、昔は茶碗があったそうです。今は荒れ果てていますが、当時は一帯には田畑が広がり、暑い時期の農作業には、冷たい水が飲める大切な場所であったことが推察できました。
調査の結果、宍塚には、植物(維管束植物)は県内で記録されている約1/3の種、チョウ・トンボは全国に生息する1/4の種が生息することが明らかになりました。
これらの記録に加え、藻類、鳥類、両生類・爬虫類、池の水質、気候、谷津の成り立ち・地質・水門などや、明治初年における宍塚大池周辺の土地利用形態(地元の方からお借りした土地明細帳を基に会員が図面を作成しました)、野生動植物を中心とする公園整備サイトとしての適性などを調べました。
95年、これらに保健保安林と都市の緑地保全といった項目も加え、「宍塚地域自然環境調査報告書」(A4版224頁)を、筑波大学の先生や農業環境技術研究所など研究所の方のご協力を得て出版しました。この報告書によって、宍塚の自然環境の豊かさが明確になりました。
現在、宍塚は環境省「生物多様性保全上重要な里地里山(重要里地里山)」に選定され、同省によるモニタリング1000調査コアサイトとして、会が調査を請け負っているほか、キノコ、サシバ、池や湿地の生物調査など、宍塚の自然を知る努力を続けています。(宍塚の自然と歴史の会代表)