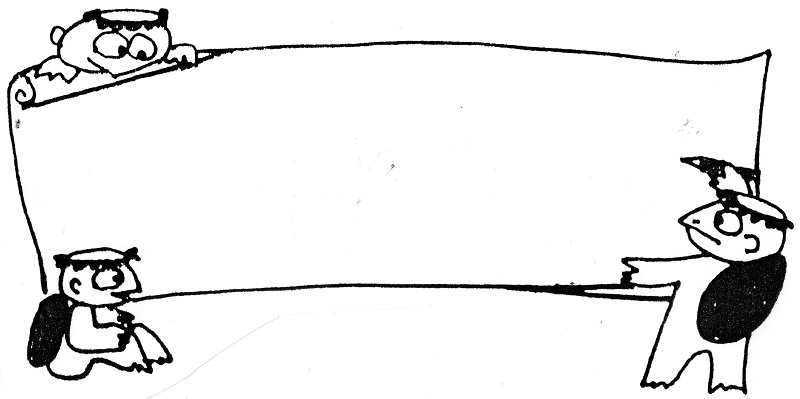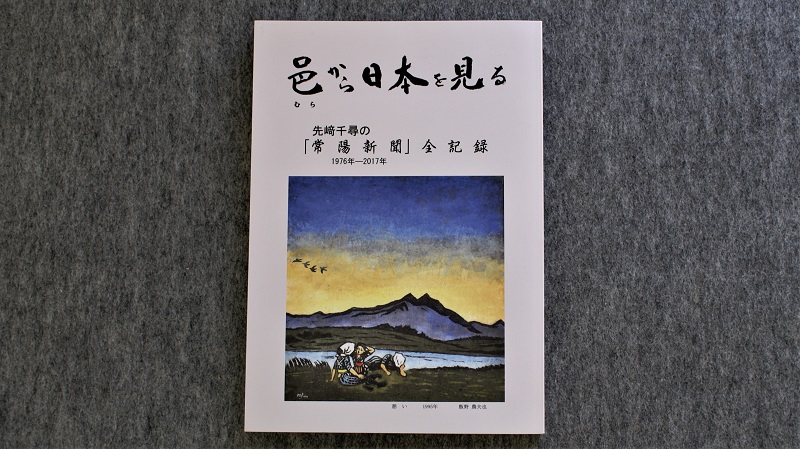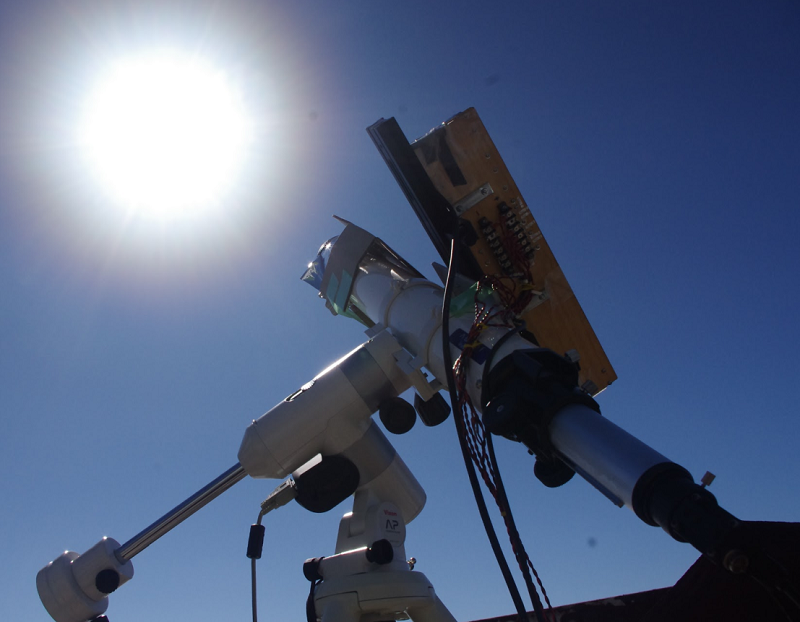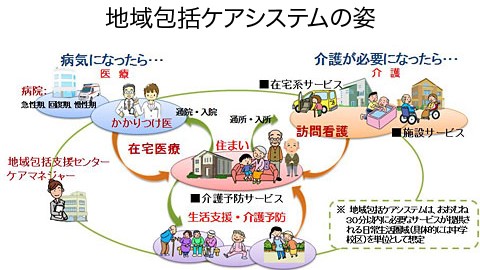【コラム・堀越智也】安倍内閣は働き方改革を提唱している。少子高齢化に起因する労働力人口減少や、長時間労働による過労死問題などを契機とする改革である。
男女問わず柔軟に労働時間を選択できれば、子育てもしやすくなる結果、出生率も上昇する。労働者が柔軟に労働時間を選択しても生産性が下がらず、むしろ向上するならば、企業も労働時間を柔軟にする労働体系を採用しやくなる。
各企業の働き方改革の成功事例がビジネス誌やビジネス番組で紹介されることが増えているが、そんな紹介事例が増えていけば、働き方改革も浸透していくだろう。
また、AI(人工知能)も急速に普及していくと思われ、仕事がなくなり労働時間が減ることを懸念する「180度逆方向の問題」があることを考えると、企業にとって労働時間が短くなることによる損失は少なくなるだろう。このように働き方改革そのものは前向きに捉えている。
ただ、自分のことをゆるく語ってみると、事務所の組織としての働き方は別として、自分自身に染み付いた働き方はなかなか変えられない。労働時間を減らせば成果が上がるという確信があればそうするが、睡眠時間さえ削らなければ、働いた分だけいろいろな成果がある。実際は睡眠時間を削ってでも仕事をしてしまう。
野球をやっていた学生時代から、1回でも多くバットを振った者が成功するという落合博満さんや、箸を持てなくなるほど手首を鍛えた野村克也さんの言葉をリスペクトして過ごした。司法試験の時も、朝から晩まで1秒でも多く勉強しようと、歩いている時も歯磨きしている時も何かを暗記しようとしていた。
僕らより上の世代の人たちも、移動のバスでもつま先立ちをして下半身を鍛えるシーンが出てくる「巨人の星」や、倒れても倒れても立ち上がる「明日のジョー」を見て育った。そんな人たちが名誉ある実績を残していると、それに憧れる。
それが子供のころからのことだと、体に染み付いてなかなか離れない。先日、同級生のお寿司屋さんも、数日前に過労でダウンしたにも関わらず、再び立ち上がったジョーのごとく寿司を握っていた。平昌オリンピックでも、極限まで努力した人が結果を出したように思える。
僕の中の働き方改革は、そんなことと、自分の年齢や健康と相談しながら進めていかなければならない難解な事業なのだ。(弁護士)





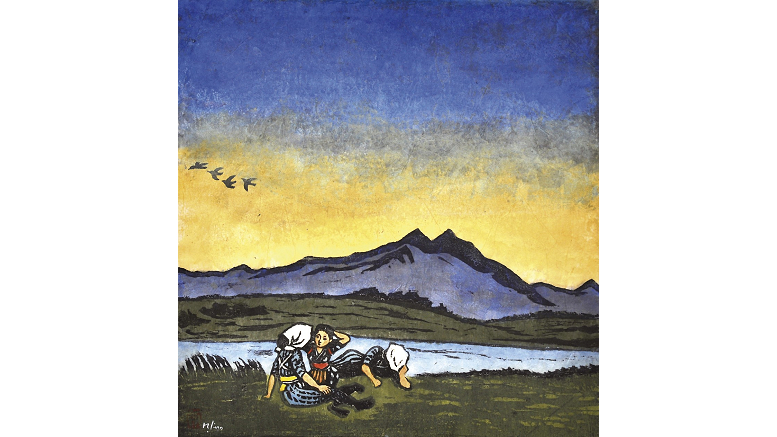

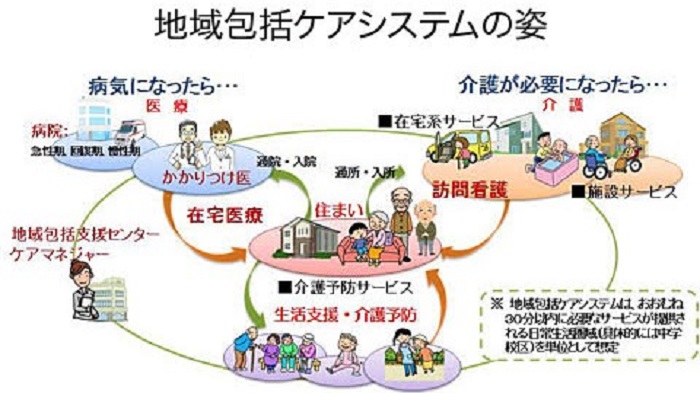

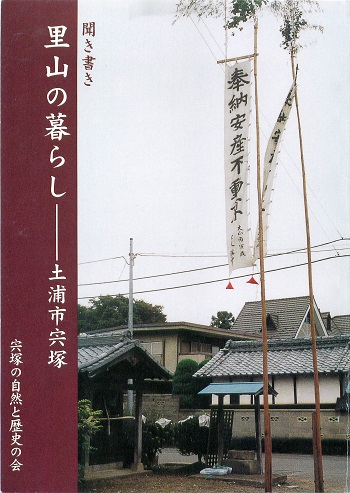
![ski-2098120__340[1]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2018/02/ski-2098120__3401.jpg)