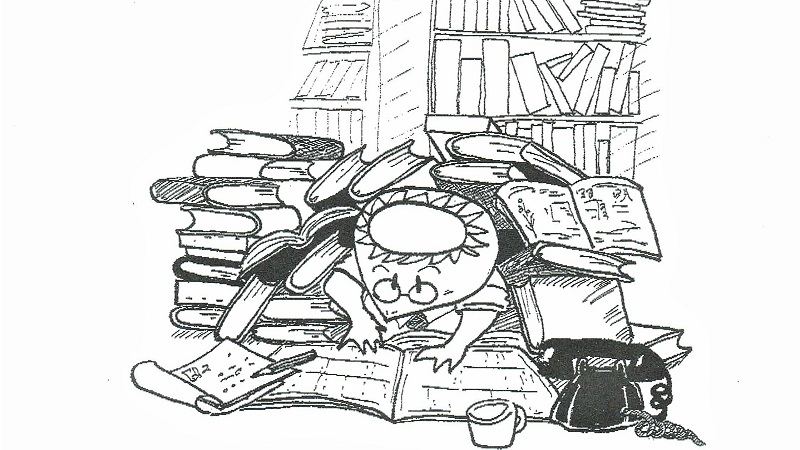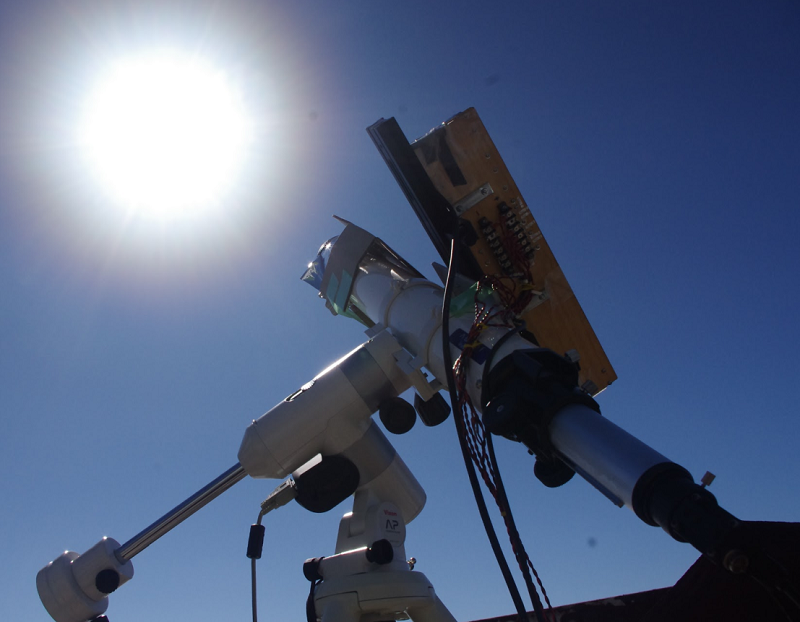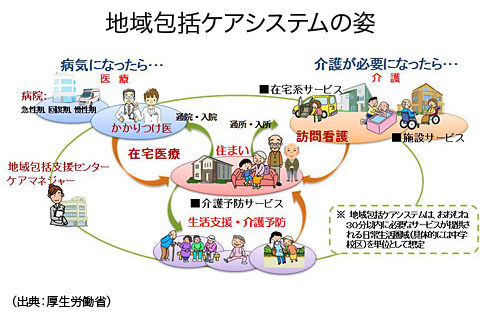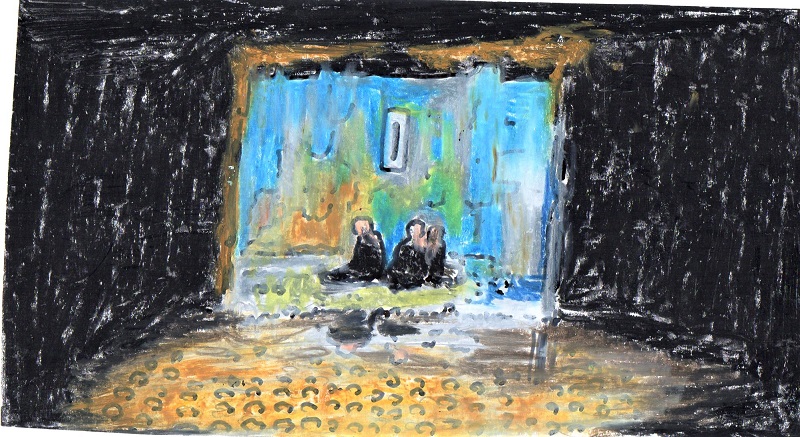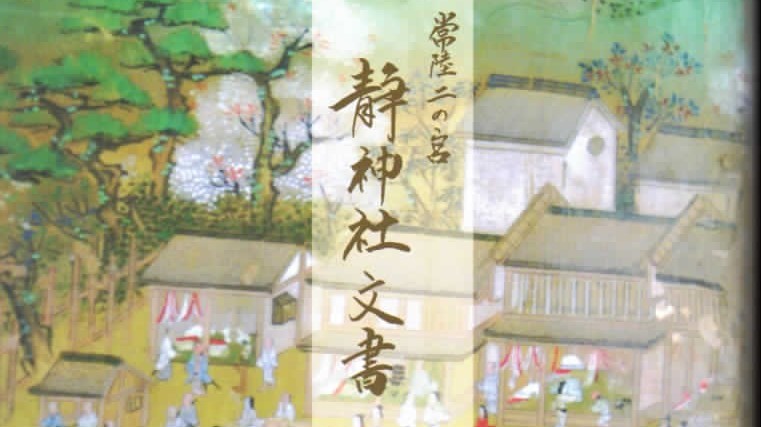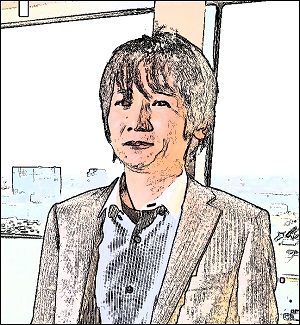【コラム・浅井和幸】遠い昔、魚の祖先が海で生まれたそうです。それらは背骨がないミミズのような生き物だったそうです。そのうち、強い魚と弱い魚が生まれます。弱い魚は、海から川へ逃げていきました。遥か遠くの川にたどり着き、まったく違う環境に適応するのにどれぐらいの困難があったでしょうか。想像を絶します。
その適応の過程で、弱い魚たちは、背骨を獲得します。ミネラルが豊富な海水と違う川の水。そこで暮らすには、ミネラルの養分を骨として体に蓄えておく必要があったのです。そして時がたつと、弱い魚たちの子孫の中でも、強い魚と弱い魚が出てきます。
弱い魚の子孫の中の弱い魚は、川から海に逃げ出すのです。そこで、もともと海にいた強い魚の子孫と鉢合わせすることになります。弱い魚の子孫の中の弱い魚たちは、強い魚の子孫たちとの生存競争をしなければなりません。
この直接対決、さて、どちらが勝ったでしょうか?それは、弱い魚の子孫の中の弱い魚でした。骨を持たない強い魚の子孫よりも、骨を持つ弱い魚の子孫の中の弱い魚の方が、素早く力強く泳げたし、強い顎を持っていたのです。いつの間にか、強いと弱いが逆転していたのでした。
逃げること、少しずつ力を蓄えることを、私たちは嫌います。日頃の積み重ねよりも、一発逆転のきっかけを求めてしまいがちです。失敗を重ねて弱気になり余裕がなくなるほど、全ての問題を解決する大きな一つの出来事を待ちます。
「白馬の王子様が現れるのを待つ」「ある日、ヒーローとして目覚める」「一つの施設や病院だけにすべてをゆだねる」「自分のパートナーの性格が変わることだけを待つ」「実力に見合わない難しい資格試験を受ける」など、枚挙に暇がありません。
きっかけは、日ごろの積み重ねが無ければ、きっかけにすることは出来ません。きっかけに出来るだけの、実力や環境を整える必要があるのです。積み重ねが出来たら、弱い自分が、積み重ねを忘れた強い対象に打ち勝つことも出来るのです。
そのためにも、ほんの些細な積み重ね、成長を喜べる気持ちが大切です。現状に喜びを感じたうえで、現状維持ではなく少しの良い変化に喜べるようになりましょう。もちろん、現状維持が良い、過去の栄光を考え続けるのが良い、過去の嫌なことを考え続けることが良いという価値観を持っているのであれば、それは各々の生き方なので他人が文句を言う筋合いのことではありませんので、自由にその道を選択すればよいのです。(精神保健福祉士)