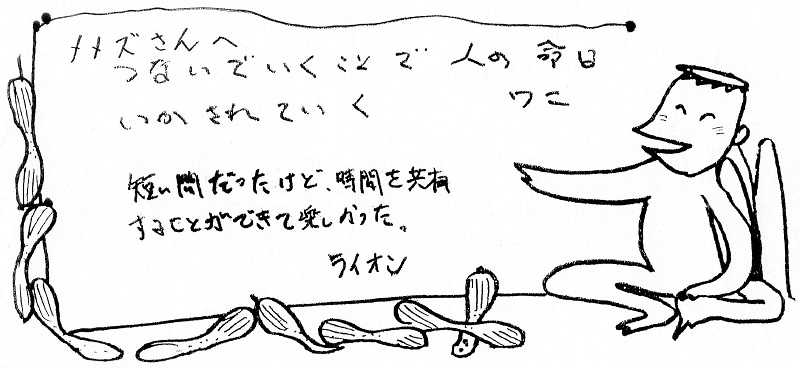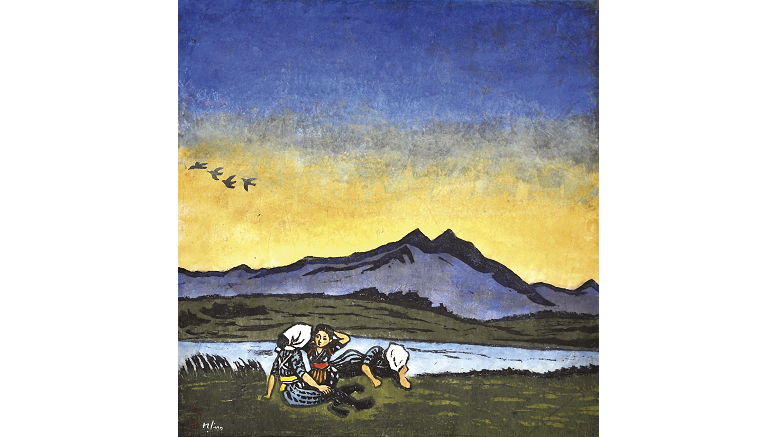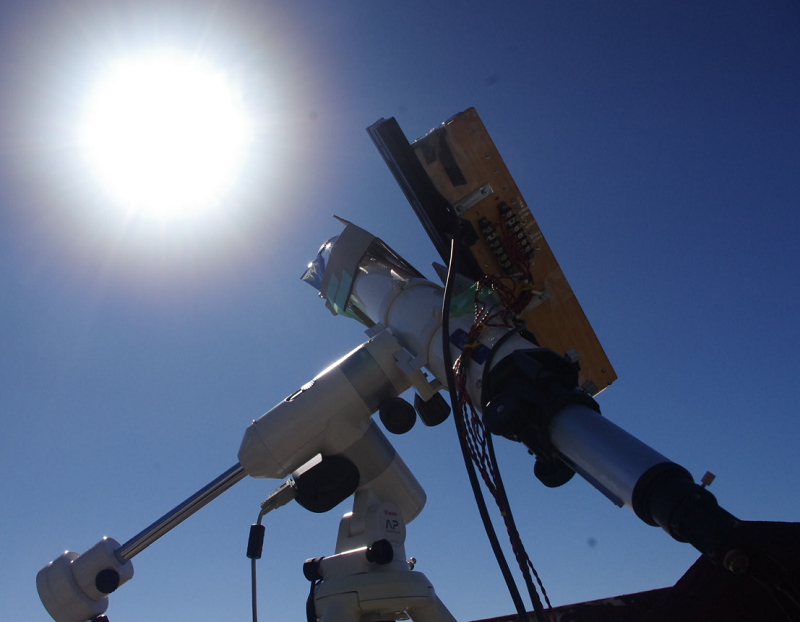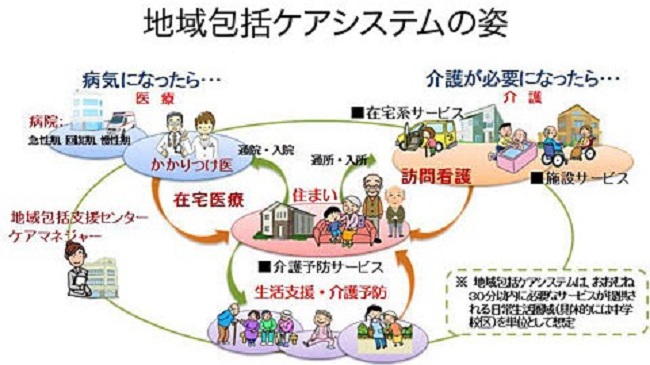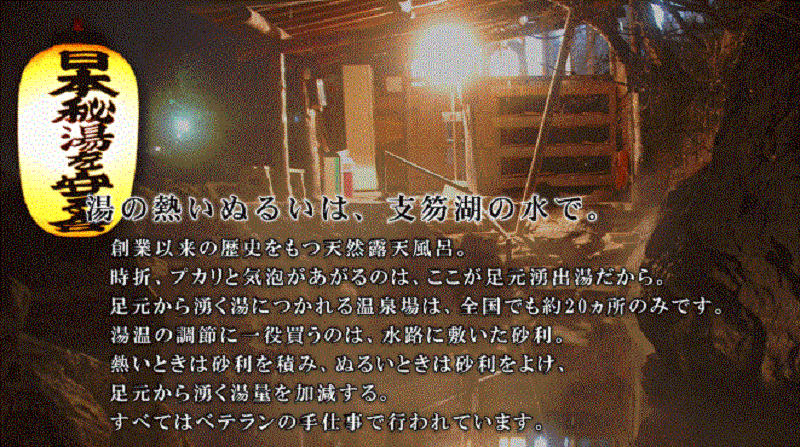【コラム・入沢弘子】梅雨入り間近の週末、6月1日に土浦市立図書館は30万人の来館者をお迎えしました。開館から半年、開館日163日目です。大勢の方のご来館を心より感謝いたしております。3月下旬、隣接するJR土浦駅に「プレイアトレ土浦」がオープンしてからは、週末の来館者が増加傾向にあります。
サイクリングウエアで立ち寄る方々も見受けられ、企画展示の「自転車関連」書籍や、情報ステーションで配布している「つくば霞ケ浦りんりんロード」「つちうらサイクリングマップ」も、すぐに無くなってしまう人気ぶり。徐々に、駅前の人や自転車の往来が盛んになってきている印象を受けます。
この半年間、来館者のご意見を運営に活かすために毎日アンケートを実施し、約600名の方から回答をいただきました。
集計したところ、①男女比は女性60%、男性40% ②年齢は10代35%、次いで50代から70代の各年代が15%前後 ③居住地は土浦市内80%、市外20% ④交通手段は自家用車50%、次いで徒歩・自転車が17%程度 ⑤職業は学生40%、次いで会社員と主婦がそれぞれ20%程度―という結果でした。
5段階評価の満足度は、①アクセスと図書館内の環境が各4.5 ②図書資料とサービスが4.2 ③スタッフの対応が4.1―でした。自由回答で記入の多い「館内に飲食場所がほしい」「周辺の飲食店を知りたい」「Wi-Fiを利用したい」「椅子の音が気になる」「平日もイベントをやってほしい」などについては、ご要望にお応えしてきました。
また、「もっと図書館に親しみをもってほしい」「これまで足を運ばなかった方にも図書館に来ていたただきたい」との願いから、5月から週1回のインターネットテレビ番組を始めました。職員が交代で出演し、図書館や本についての情報をお届けします。公共図書館の番組は世界初のチャレンジ。ぜひご視聴ください。(土浦市立図書館館長)
▽番組名:「つちうら図書館ちゃんねる」
▽放送日時:毎週木曜日 午後3時から15分間
▽公開生中継:Vチャンネルいばらき「サテライトスタジオ505」