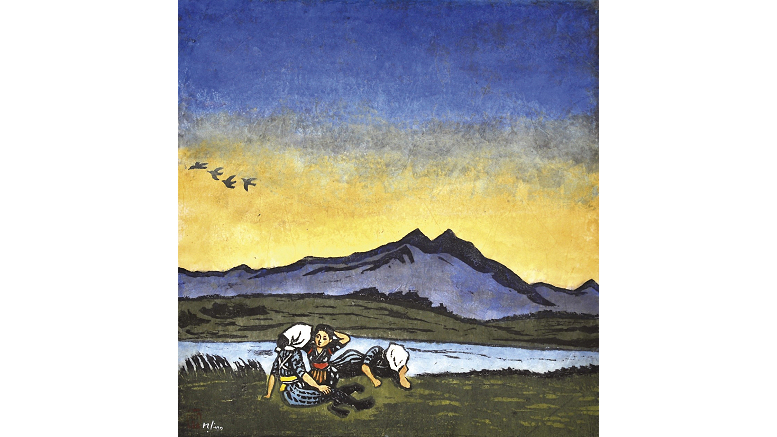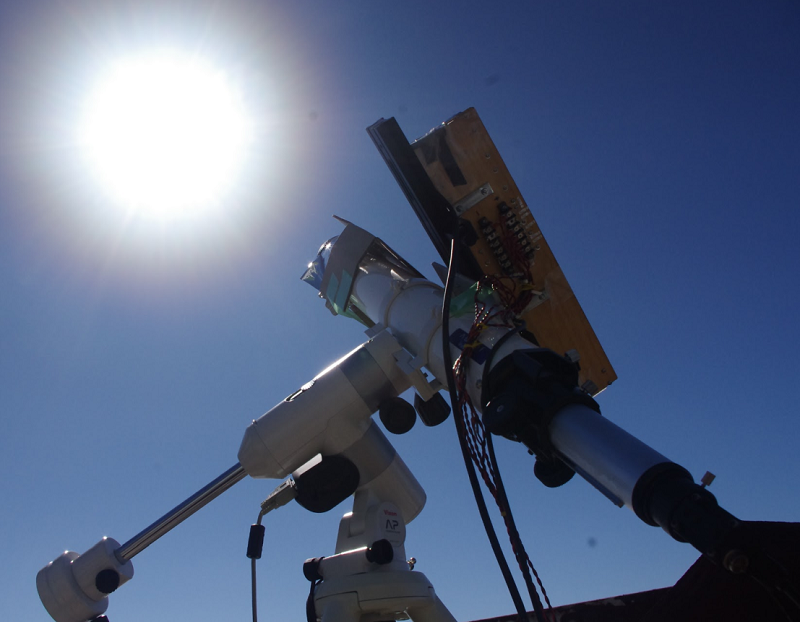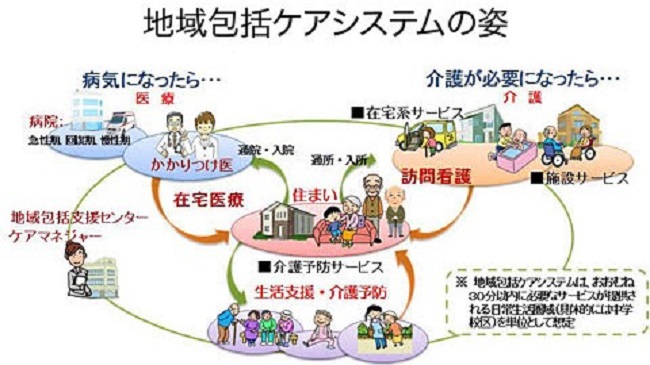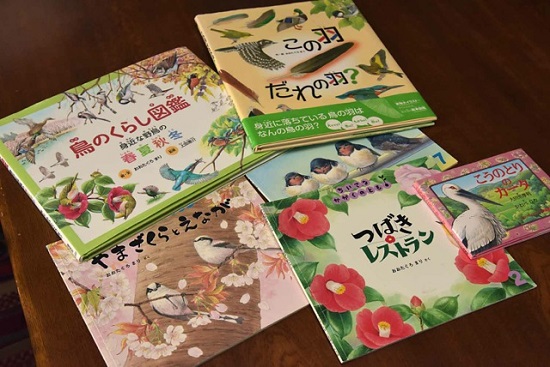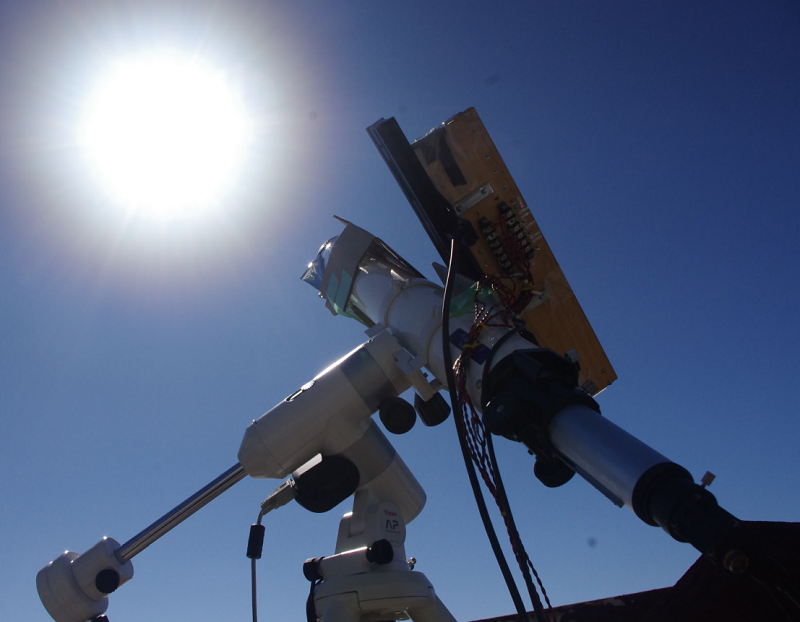【中尾隆友】今回のコラムでは、茨城県が元気になるために3つの政策を提案したい。
まず1つめの政策は、大企業の本社機能の一部を誘致するということだ。第2回と第3回のコラムで述べているように、大企業の本社機能の誘致はそれがたとえ一部であっても、若者の東京圏への流出を減らすと同時に、良質な雇用の確保や少子化対策という面で大いに効果を発揮する可能性を秘めている。
さらには、大企業の経営者に魅力的な誘致案を提案できれば、茨城県は東京圏への近さという地の利を生かして、意外に多くの大企業を招き入れることができるのではないかと考えている。大志を持った大手IT企業の経営者を中心に、東京から地方へ本社機能を移したいと思っている人は着実に増えてきているからだ。
実際に、先週、ある大手IT企業の会長と話す機会があった。その会長が「僕は利益を増やすだけでなく、社員が幸せになる会社をつくりたい」と目標を述べたのに対して、私は「本社を都心から郊外へ移転すれば、経営コストは圧倒的に安くなるし、従業員の仕事や生活における満足度も格段に上がると思う」と申し上げた。
するとその会長は「おっしゃるとおりだ。紀尾井町に6000人の従業員を抱えるのは、ものすごいコストがかかる。全部を郊外へ持っていくのは無理だとしても、郊外への分散はしていきたいと思っている」と答えてくれたのだ。本社機能の移転需要は、確実に存在するというわけだ。
茨城空港を第2成田に
2つめは、茨城空港に第2成田空港としての機能を持たせるということだ。成田空港の現状は、時間帯によっては欧州便とアジア便の離発着が過密でパンク寸前だ。そこで茨城空港に、北海道・東北・北関東方面への旅行を計画する海外観光客を成田から分散させる役割を担わせるのだ。
現在、東関東自動車道と北関東自動車道を結ぶ工事が進んでいるが、茨城空港前にもICができる予定だ。アクセス上の利便性はこれまでよりも高まり、成田空港を補完する環境が整うというわけだ。その結果、海外観光客が茨城で消費をする必然性が増し、空港の周辺に小売店やホテルなどのサービス産業が集積し、ひとつの街が誕生することも期待できるだろう。
3つめは、つくば市を上手く使うということだ。一昨年のG7では科学技術大臣会合が、来年のG20では貿易・デジタル経済大臣会合が開かれるように、つくば市は科学技術では全国1あるいはアジア1のポテンシャルを持っている。
茨城県は5年連続で魅力度ランキングが最下位だったと発表したブランド総合研究所の田中代表も、「つくば市は全国の市町村のなかで科学技術のブランドでは日本一である。その強いブランドがあるのだから、茨城県のブランドを上げるためにはそれを活用しない手はない」と指摘している。私もつくば市と他の市町村が上手く連携できるようになれば、県全体のイメージは大いに上がるだろうと考えている。
以上の3つの政策は、お互いに好循環をもたらす可能性が高いので、ぜひ実践してもらいたいところだ。(経営アドバイザー)