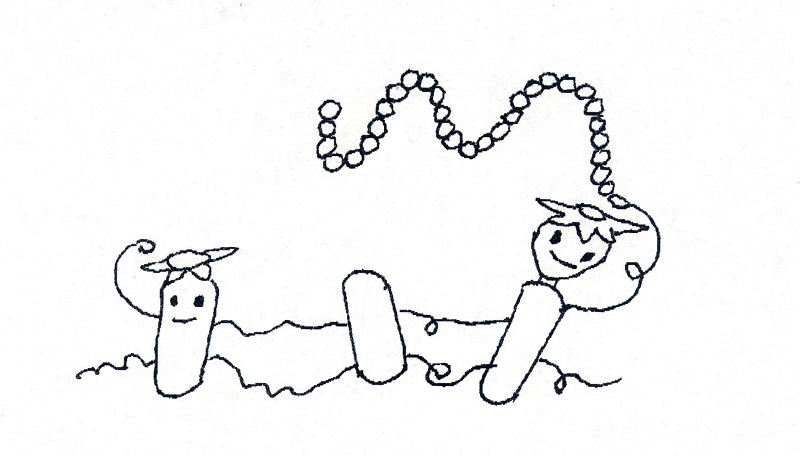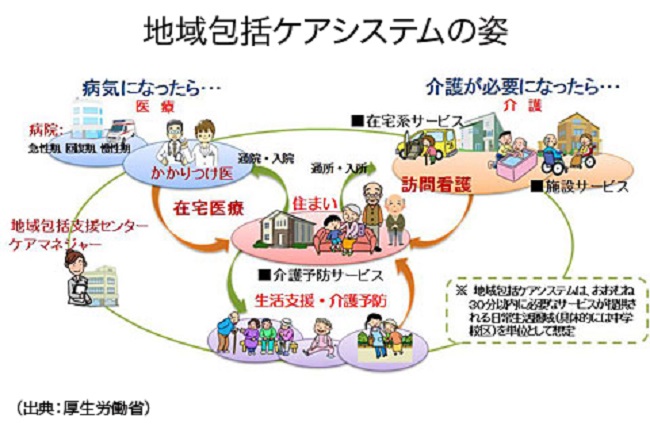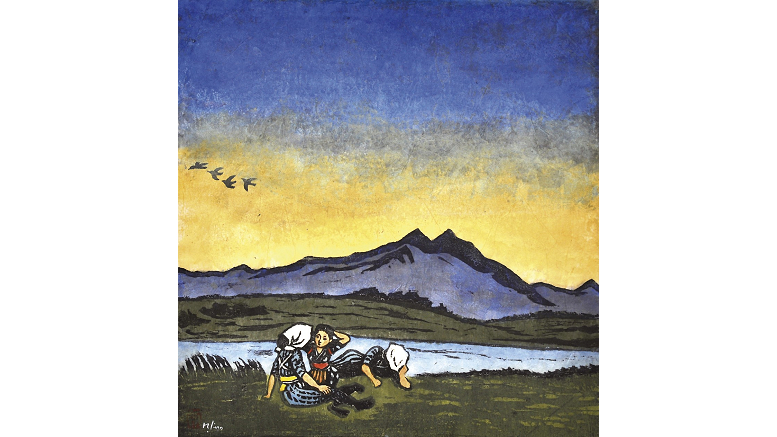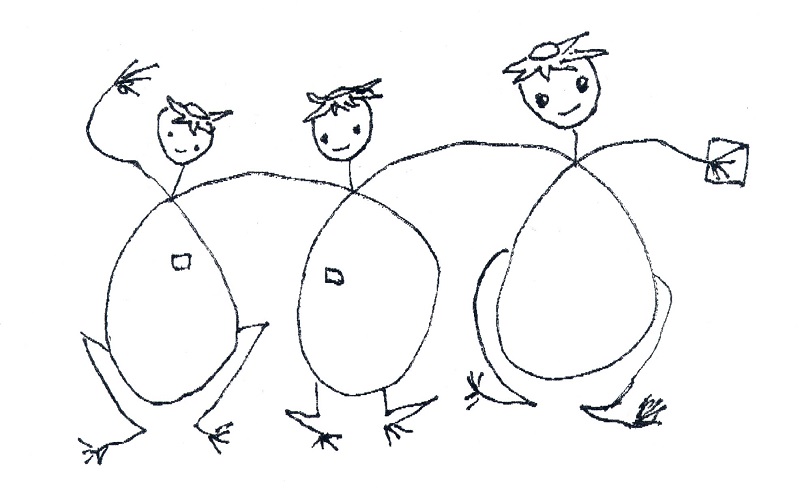【コラム・霞ヶ浦市民協会】霞ケ浦湖岸を走る「霞ケ浦自転車道」と筑波山西側の旧筑波鉄道跡を走る「つくばりんりんロード」がつながり、全長180キロの自転車道「つくば霞ケ浦りんりんロード」が開通した。私の職場がある土浦の霞ケ浦総合公園にも、自転車愛好家が全国から訪れ、土日曜日、公園駐車場は他県ナンバーの車であふれている。
この自転車道に沿って、土浦市2カ所、桜川市、石岡市、つくば市、かすみがうら市、行方市、潮来市各1カ所―合計8カ所に、どこで借りてどこで返してもOKの「広域レンタサイクル事業」もスタートした。このシステムに加え、各市の観光拠点に「自転車ステーション」を設ければ、各市のにぎわい=活性化も期待できるのではないだろうか。
近年ヨーロッパでは、「路面電車の復活」「自転車の活用」が進められているが、デンマークのコペンハーゲン市には自転車専用車線があり、レンタル自転車ステーションも市内随所にある。調べたところ、120カ所にステーションが設けられ、20クローネ硬貨(約350円)でどこへでも自転車で行ける。
以下、1999年に同市で開かれた第8回世界湖沼会議に参加した時の思い出話だが、「自転車の街」をイメージしていただけたらと思う。
自転車の街 コペンハーゲン
コペンハーゲン市は水と緑にあふれ、歴史のある都市である。チボリ公園、市庁舎、王宮殿、教会、旧証券取引所など歴史的建造物も多く、都市景観は素晴らしい。これらが運河など水辺に触れ合う工夫が随所にしてある。運河クルーズで見る水辺からの景観は特に素晴らしく、1つ1つの建造物が印象に残っている。
目を陸に向けると、やたらに自転車が多く、通勤通学などの交通手段として市民に定着している。乳母車を前に付けたような3輪自転車もあり、これはなかなか高額ということだった。自転車のチャイルドシートも、足のステップがしっかりカバーされていて、子供に合わせてオーダーできるそうだ。
チボリ公園視察のあと、レンタル自転車に試乗してみた。赤黄青が基調のカラフルな自転車は、ブレーキがハンドルに付いておらず、サドルを逆転するとブレーキがかかる仕組み。最初はとまどったが、すぐ要領が分かった。
翌朝、ホテル前のステーションから自転車散策に出てみた。早朝にもかかわらず、大通りは通勤通学の自転車であふれ、どんどん抜かれる。こちらはのんびりと、ドローニンリーゼ橋畔にあるレストラン側の木道桟橋をゆっくり走り、水鳥のさえずりを聞き、透き通った空気を吸って、朝の一時を過ごした。(大川幸一 霞ヶ浦市民協会副理事長)