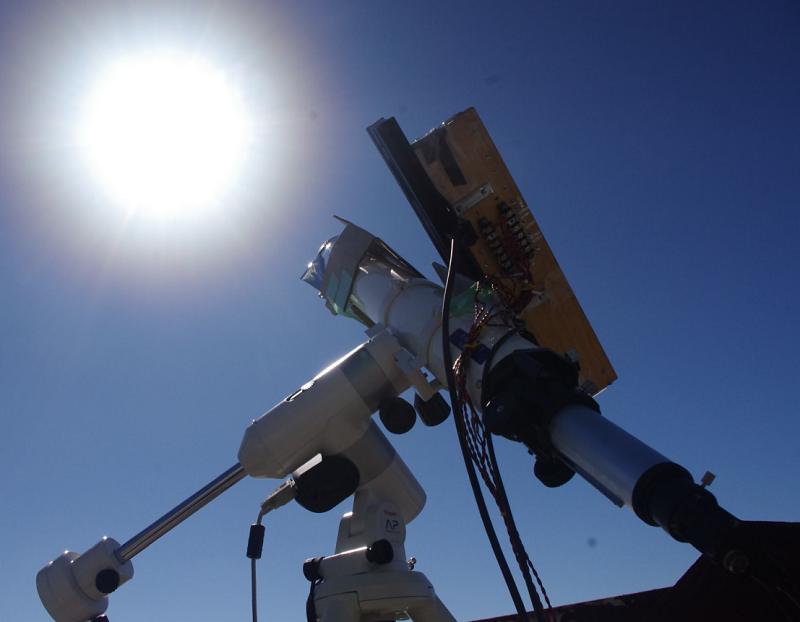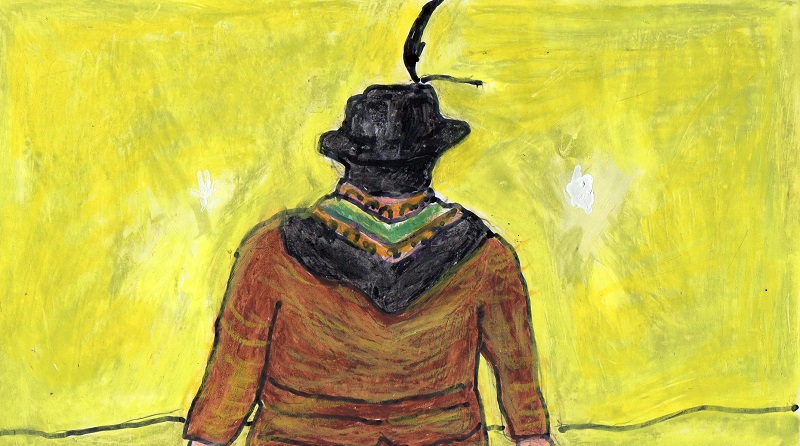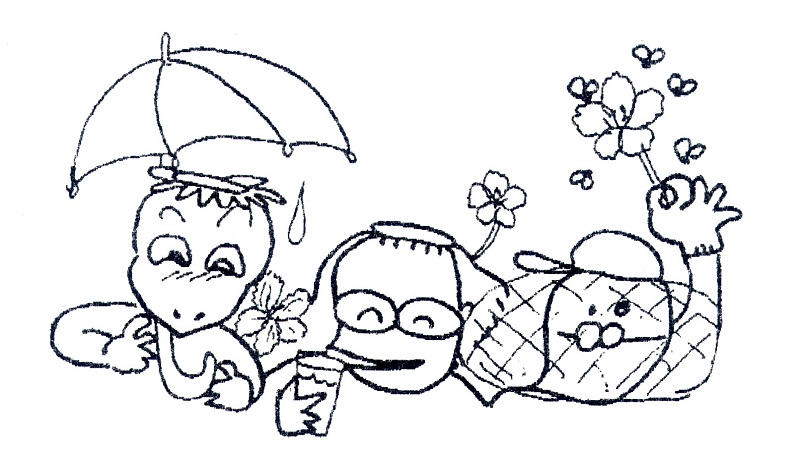【コラム・先﨑千尋】「今でも福島の放射線量は高いから、福島に行くな、福島のモノを食べるな」。私は先月21日、土浦市本郷の「ともいきの郷」で、前福島県双葉町長の井戸川克隆(かつたか)さんから、「福島に行くな、福島のモノを食べるな」という飛び上がるほど驚く話を聞いた。
井戸川さんは2005年、福島第1原発が立地する町長に就任し、7年半前に東京電力が起こした福島第1原発事故に遭遇し、住民の避難に全力で対応した。ニュースで井戸川さんのことを知っていても、話を聞くのは初めて。目からうろこが落ちた。2回に分けて彼の話を伝えたい。
前双葉町長井戸川さんの話 (1)
「私は、東電福島第1原発の事故によって、味わわなくともよい経験をした。原発事故は、1民間企業が起こした事故であり、災害ではない。東電は私たちに『事故は起きないから心配しないで』と言っていた。地震、津波が起きることを知っていた。知りながら対策をしていなかった。その事故に、国が災害救助法を適用するのはおかしい。事故の根源は、国の原子力政策の失敗、旧原子力安全保安院の怠慢、原子力関係法の不備、電力会社の安全管理、品質管理、保全管理の怠慢、電力会社の利益優先の考えなどだ」
井戸川さんは、福島の原発事故は災害ではなく、東京電力と国の怠慢により発生したと断罪し、「私は事故が起きても、東京電力は会社が大きいから大丈夫だと思っていたが、裏切られた。国や福島県、東京電力にだまされた」と怒りをあらわにする。
「東電は、原発が立地する4町の首長協議会には津波情報を隠していた。出していれば、原発を止めろと言えた。止めれば東電の赤字が増える。勝俣社長(当時)は私たちに何でも報告すると言っておきながら、結局、情報を隠していた。東電がプルサーマルを福島第1原発3号機に入れる提案をした時にも、導入に問題がないという報告を受け入れた。その後、トラブルが起き、白紙に戻した。東電にだまされた」「今必要なことは『復興』ではなく、事故の解明と責任を明確にすることだ」
「私が残念だと思うことは、原発事故の時に避難させられたことだ。その前の避難計画や避難訓練を『はてな?』と思わなかった。避難計画があること自体、異常である。福島第1原発の事故は、東電という1営利企業が犯した事故であり、1民間企業が起こす事故に対する避難計画を自治体が策定することがおかしい。これは違法で、国民の財産、生存権などを保障する憲法に違反する」
「原子力関係法のどこにも住民の責任のことは書いていない。住民の責任は存在しない。また、国民は原発事故から避難する義務もない。義務も責任もないのに、どうして避難しなければならないのか。避難計画は法律ではない。なので、国は責任をとらない」
井戸川さんは舌鋒鋭く、国と東電の対応を強く非難し、悔しさをにじませる。次回は避難計画について、東海村に即した話を伝える。(元瓜連町長)