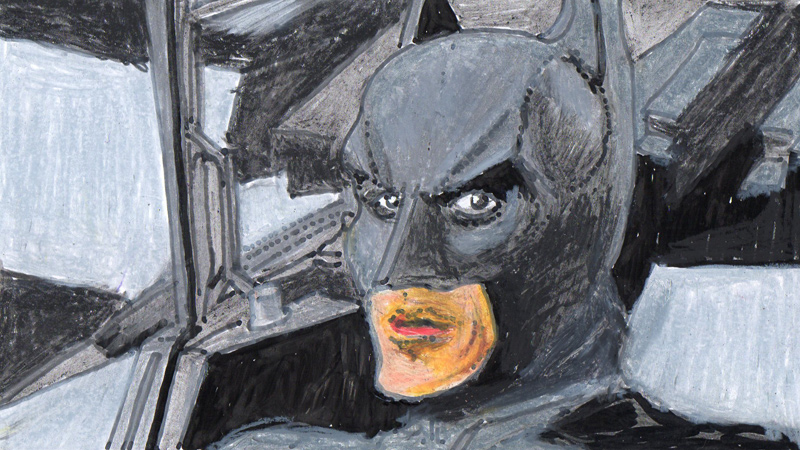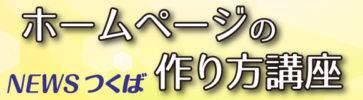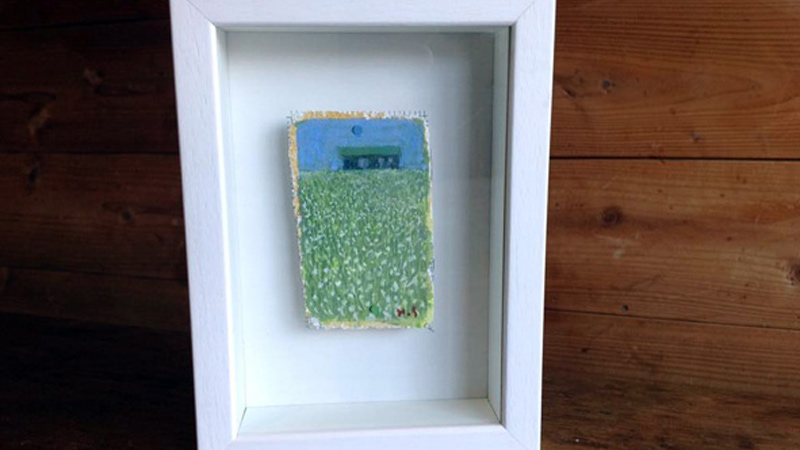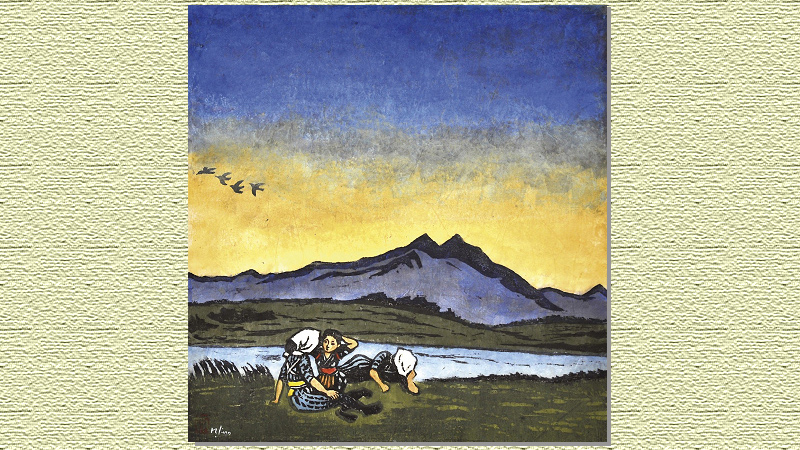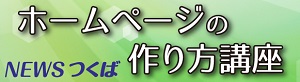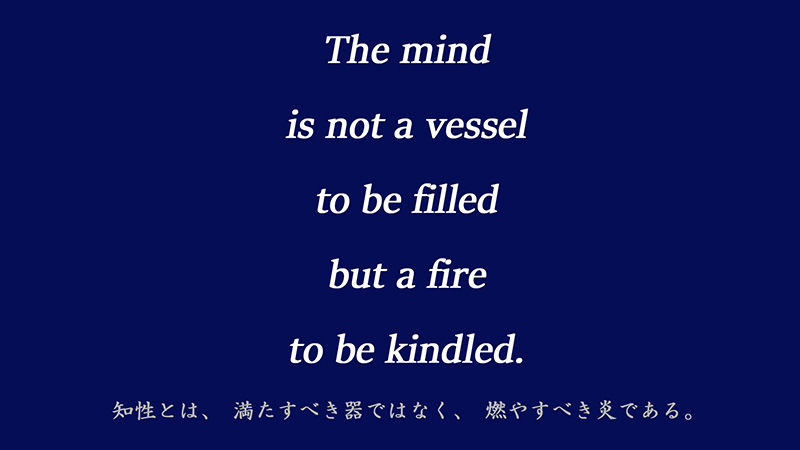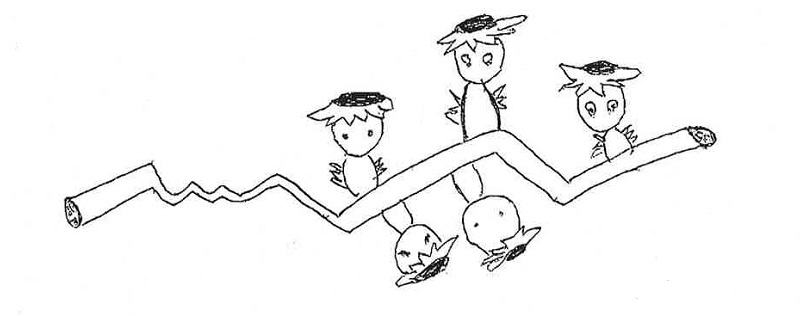【コラム・冠木新市】自転車によるまちおこしが、桜川市、つくば市、土浦市で進められている。3月30日には、サイクリング施設「りんりんポート土浦」が川口にオープン。「つくば霞ヶ浦りんりんロード」(180キロ)の拠点になる。しかし私には、旧筑波鉄道の岩瀬~土浦間の廃線跡地を活用した「つくばりんりんロード」(40キロ)の方がなじみ深い。
筑波鉄道は1918年に開業し1987年に廃業。廃業の年に誕生したつくば市と「りんりんロード」の歴史は重なる。また、ほぼ並行して流れる一級河川・桜川(63キロ)にも、まちおこしならぬ、村おこしの歴史が眠っている。
天保4年(1833)、旗本の川副氏から村おこしの依頼を受けた農政指導者の二宮尊徳は、常陸国真壁郡青木村の桜川を初めて視察する。桜川は両岸も水底も灰のような細かな砂のため、堤防が壊れ、水田は水没。どの家も耕作できず衣食に欠乏、破産して流浪の民となる者もいて荒廃していた。
二宮は村を訪れる前に名主の説明を聞き、荒廃は用水の科(とが)ではなく、苦労を嫌う村人の怠惰に起因すると見抜く。そして、大火事のもとになる茅を刈らせて買い取り、村の社寺や民家の屋根をふきかえ、村人の奮起を促した。
その後青木村に入り、堤防工事に着手、奇想天外な方法を用い、わずか10日間で青木堰(せき)を完成させた。
クリストファー・ノーラン監督の『バットマン』
私が二宮尊徳に興味を抱いたのは、父を亡くした40数年前、書店で偶然手にした本がきっかけである。それまでは、柴を背負い本を読む少年像から、小柄で善良な人物と思い込んでいた。
ところが実際は、身長182センチ、体重94キロとプロレスラー並の体格。また、一農民でありながら士分に取り立てられたため、村の再生では侍と百姓から組織的なイジメに遭っていた。無理もない。二宮は100~200年先を見据えた計画を練り、「小を積んで大を為す」の哲学で行動した。日本人離れした人物であったからだ。
二宮は各地から村おこしを頼まれ、何度も断るが、結局次々と引き受けたのは何故か。私は、二宮が少年のころ、小田原の酒匂川の洪水で田畑が流出、両親の病死、一家離散を経験しているからだと思う。
滅多に昔のことは語らなかったという二宮だが、両親のことに話が及んだときは、体を震わせ落涙したそうだ。二宮は災害や貧困に苦しむ村人の姿に、自分の少年時代を重ねていたのかもしれない。
そんな二宮尊徳とクリストファー・ノーラン監督の『バットマン』3部作(2005~2012)の主人公ブルース・ウェインの姿が重なる。ウェインは腐敗したゴッサム・シティーで好き勝手に振る舞う犯罪者や市民たち、そんなゴッサムを滅ぼそうとする影の同盟に対し、バットマンに変装して戦いを挑む。バットマンの原点は、暴漢によって両親を殺害されたブルースの少年時代のトラウマにあった。
「りんりんロード」をツーリングファッションで颯爽(さっそう)と走る人々は、バットマンを連想させる。彼らも少年少女のころ、両親の助けを借り自転車の乗り方を教わったことだろう。まちおこしとは、親が子を想い子が親に感謝する心から生まれてくるのに違いない。サイコドン ハ トコヤンサノセ。(脚本家)
➡冠木新市氏の過去のコラムはこちら