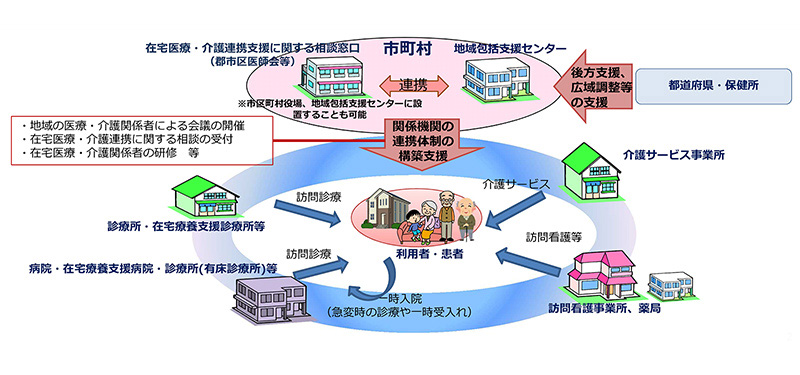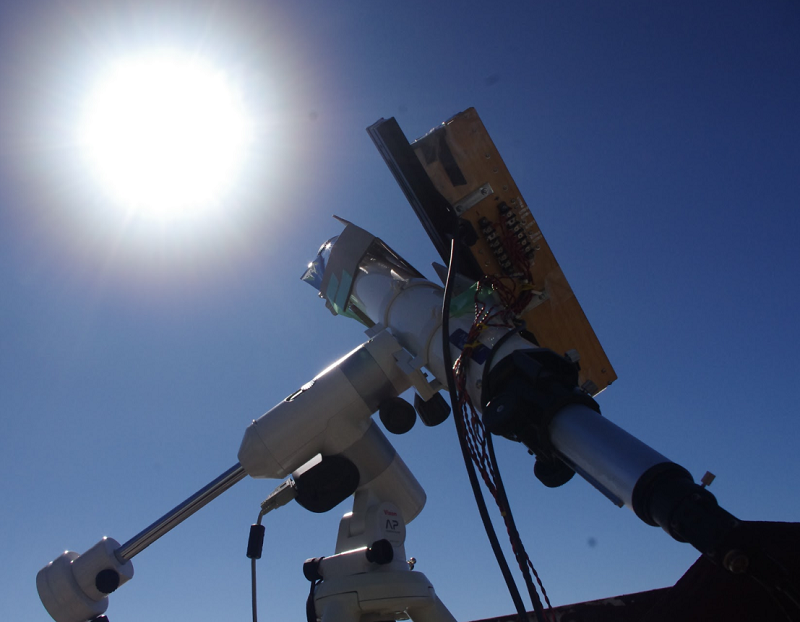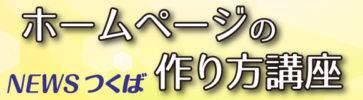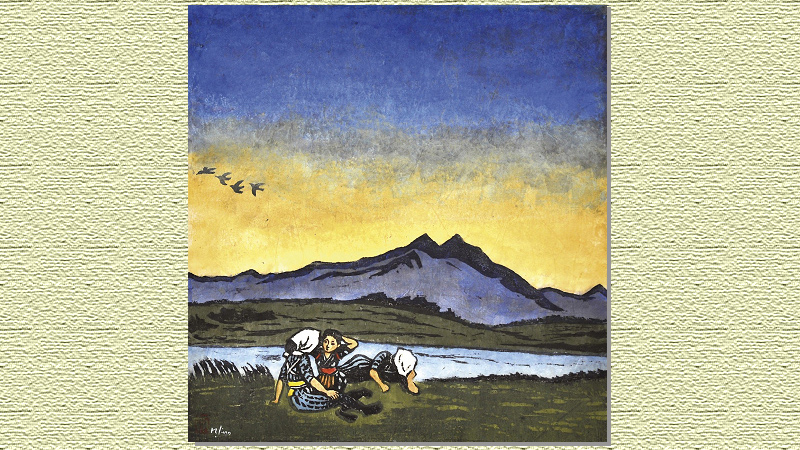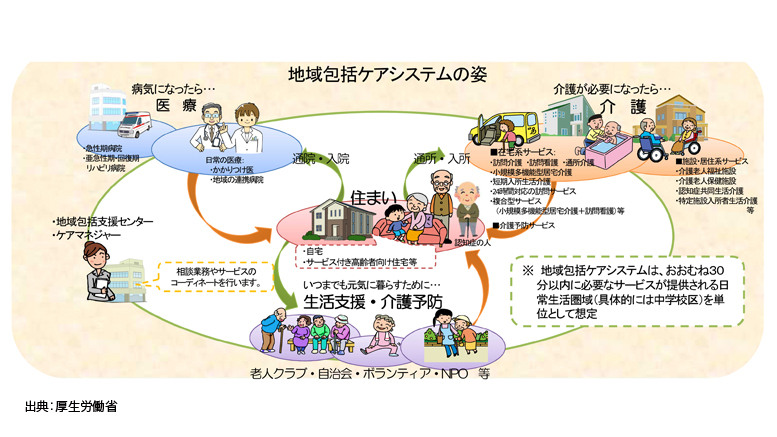【コラム・入沢弘子】「見てみて!もう100冊読んだよ」。児童コーナーを歩いていたら、本の通帳を手にした女の子に話しかけられました。「うわー、すごいね!本の通帳が出来てからまだ5ヵ月なのに100冊も読んだの?」。得意げに見せてくれた通帳には、借りた本のタイトルがビッシリ印字されています。「いつも日曜日にお父さんと来るの。学校でもらった『たからもの』に載っている本を全部読むんだ」と話してくれました。
当館では、「子どもたちの豊かな心と生きる力を育む」ことを基本理念に、2011年に『子ども読書推進計画』を立案。子どもたちが本に興味を持ち楽しむこと、読書に親しむ環境の整備、子どもの読書活動に関する社会の理解と関心を高めること―これら3つの柱で取り組みを進めてきました。現在は16年からの第2次計画に沿った全40の事業を実施しています。
17年11月にアルカス土浦に移転してからは、専用の部屋の設置とボランティアさんのご協力による「おはなし会」の開催、市内の高校図書委員が勧める本と書評の展示、読書履歴を記帳する「本の通帳」導入などの新規事業を開始。好評本の紹介冊子『たからもの』の全小中学生への配布や、独自の読書感想文コンクールのほか、約35の事業も継続しています。
高校生の利用者が「爆増」
これらの事業は、果たしてどのような効果があったのでしょうか。
昨年10月に当館がまとめた『新図書館開館1年間の利用者動向変化』では、小学1年生から高校3年生までの児童生徒への本貸出冊数は、旧図書館と比較して2.5倍の約8万3000冊に、新規登録者数は28倍の3752人になりました。中でも、高校生への貸出冊数は6倍に、新規登録者数は82倍に増えました。読書を楽しみ、図書館で過ごす子どもたちが確実に増えています。
文部科学省が17年に発表した『子どもの読書活動の推進等に関する調査研究』によると、「読書活動の度合いが高い児童・生徒の方が、論理的思考等の意識・行動に関する得点が高くなる」という結果が出ています。また、家庭の蔵書数が子どもの読書量に影響を与えるそうです。
当館では「子どもの読書週間」にちなみ、お勧めの本を包装したブックセットや、読み聞かせに最適な本の展示、子ども映画会などを企画。利用カードは全国どこにお住まいの方でも作成できます。ゴールデンウィークも無休の当館で、お子さまと一緒に「読書三昧」で過ごしてみませんか?(土浦市立図書館館長兼市民ギャラリー副館長)
➡入沢弘子さんの過去のコラムはこちら