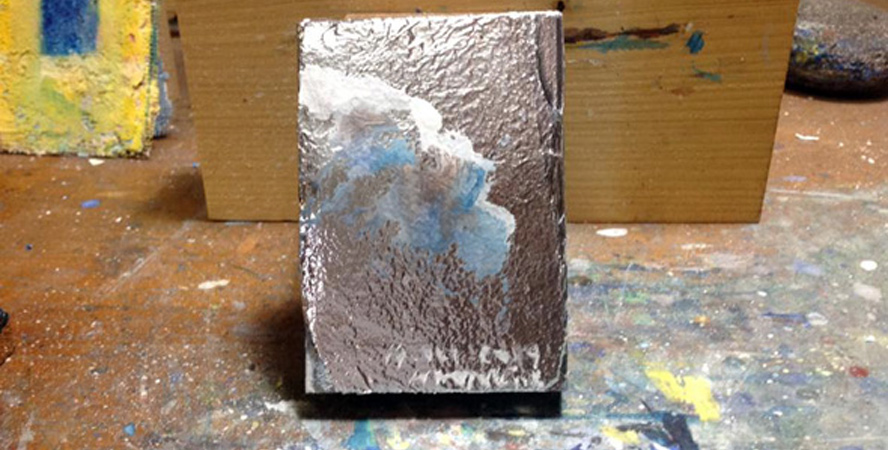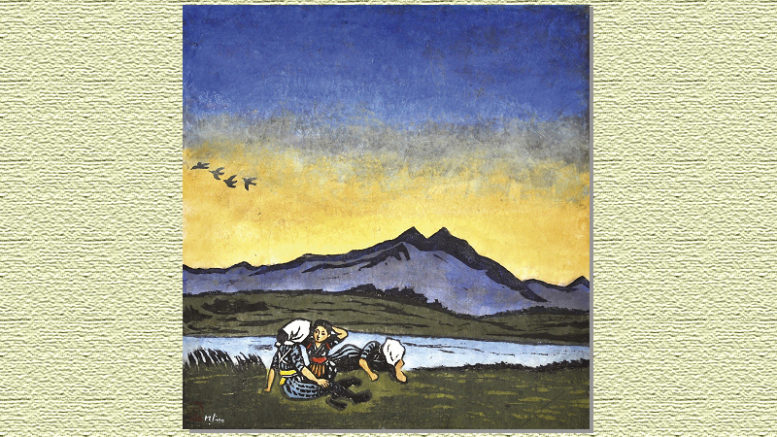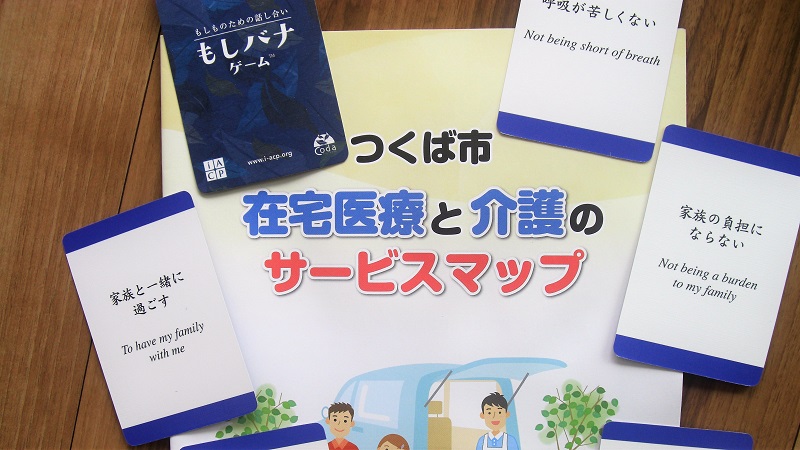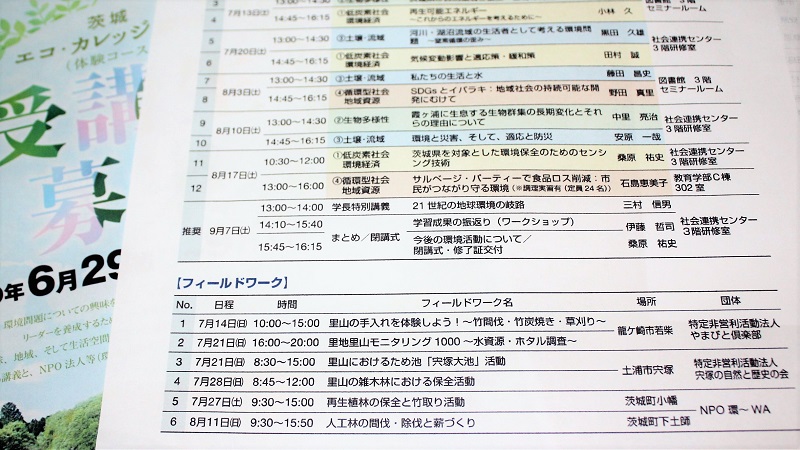【コラム・山口絹記】何かを思い出すという行為は、深い海にボンベ無しであてもなく潜るのに似ている。濁っているときは何も見えないし、海底まで見渡せるときもある。基本的には息が続くところまでしか潜れないし、あともう少しと手を伸ばしても、届かないときは届かない。
私はときどき、そんなふうに思う。
12月が近づいた、私が緊急入院することになる1週間前のある日。家族3人の夕食中、妻のことばに何か返そうとして、私は違和感を覚えた。自分が何を言おうとしたのか、わからなくなってしまったのだ。
ふと台所に置かれている長ネギを見て私は固まった。その味や調理方法もわかるのに、名前がわからないのだ。そういえば、今何の話をしていたんだっけ?
「どうしたの?」妻が怪訝(けげん)な顔でこちらを見ている。机の上に視線を戻す。食卓に並ぶものすべて、一つも名前がわからない。何か言おうとするも、「あれ、なんだっけ、どうしよう」と特に意味のないことばがこぼれ落ちる。
耳から入ることばは理解できるのに、何かを意識的に言おうとすると、途端(とたん)に頭の中にもやが広がって訳がわからなくなった。時計を見る。18時5分前。数字、時刻は理解できる。床に落ちていた広告の文字も理解できた。しかし口に出して読むことはできない。
その症状はちょうど1分ほど続いた。
すぐに回復した私は「今話せなくなって、ものの名前もわからなくなった」と妻に話しながら、脳裏に失語という単語が思い浮かんだ。歴史上の人物の名前が思い出せないとか、先週の夕飯のメニューが思い出せないというのとは明らかに違う。長ネギ、みそ汁、コップなどという単語が同時に思い出せないのは、疲れがたまっているくらいのことでは説明がつかない。
脳出血だろうか。頭痛やしびれはない。脳腫瘍(のうしゅよう)かあるいは若年性Alzheimer病? そんなことを考えていると、脳外科で長年看護師をしていた妻も同じようなことを考えたのだろう。身体、動く? 右手、動く? と尋ねてくる。
私は「大丈夫、動くよ、疲れてるのかな」と右手が動くのを見せながら、病院に連れていくかを考え始めている妻を無理やり止めた。
日記に不自然な誤字脱字
その夜、家族が寝静まったあとに、日課であるオンライン英会話はキャンセルして、過去の日記を読み返した。前日の日記に、不自然な誤字脱字が見つかった。この2カ月間で誤字脱字はそこだけだ。やはり、おかしい。
先程の症状も継続時間はわずか1分。つまり今までもただ気が付かなかっただけで起こっていた可能性は大いにある。
しかし、なにぶん過去に失語になったことなどなかったので、これが失語かと自分に問うてみても自信がない。誰かに相談したいところだが、会社の上司に「年とってくると長ネギ見ても名前が出てこないことってありますかね?」などと質問した日には、おそらく趣を異にした問題が身に降りかかるだろう。
いずれにせよ、よく食べて寝ておけば治る類(たぐい)のものではなさそうだった。私は2週間を期限に注意深く自身を観察することにした。-次回に続く-(言語研究者)
➡山口絹記さんの過去のコラムはこちら

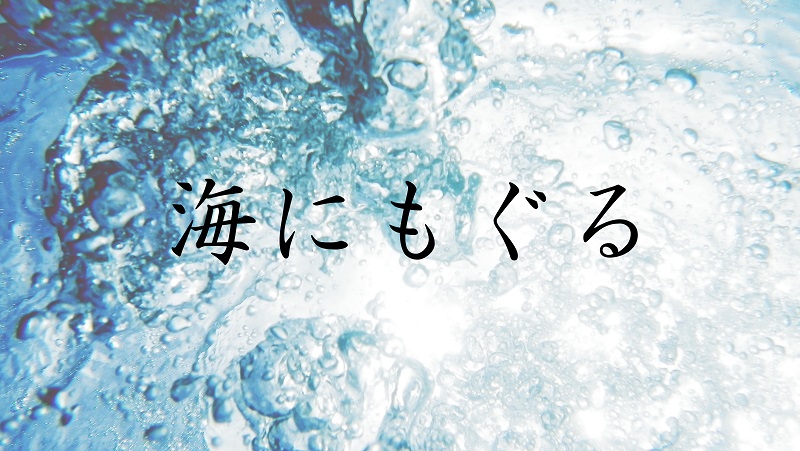







 【コラム・小野村哲】「学校に行きたくない」という子に、私はいつもこう答える。
【コラム・小野村哲】「学校に行きたくない」という子に、私はいつもこう答える。