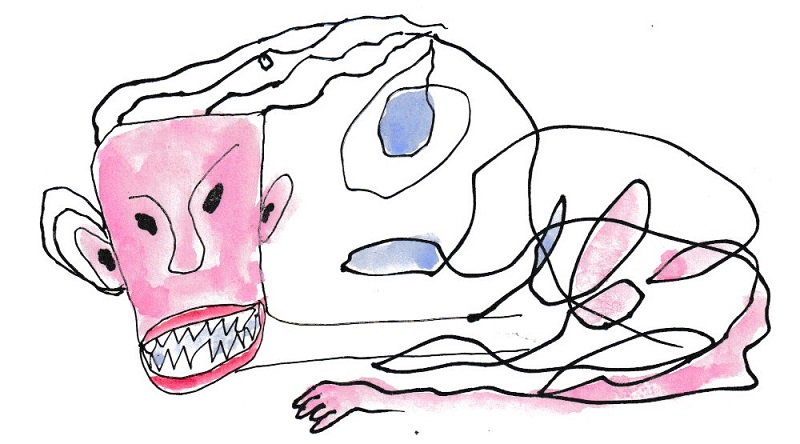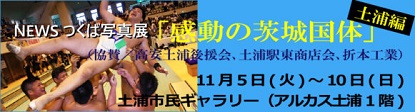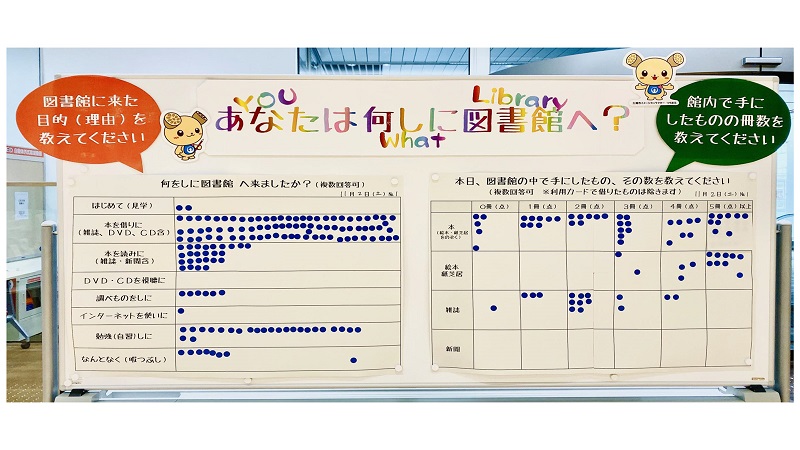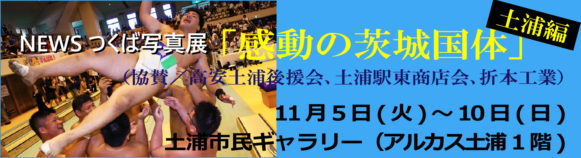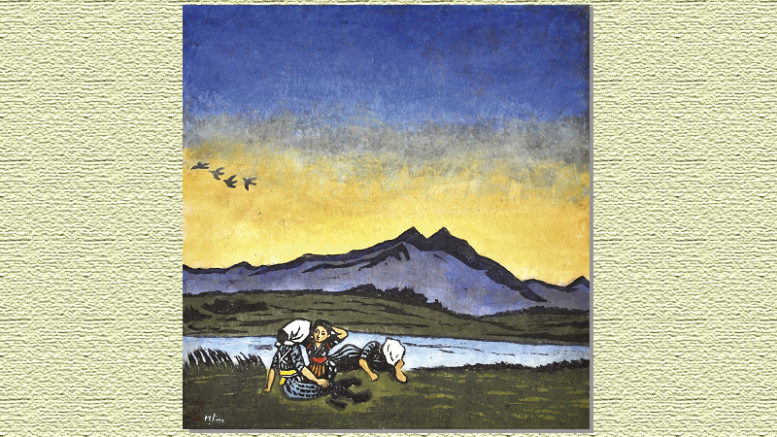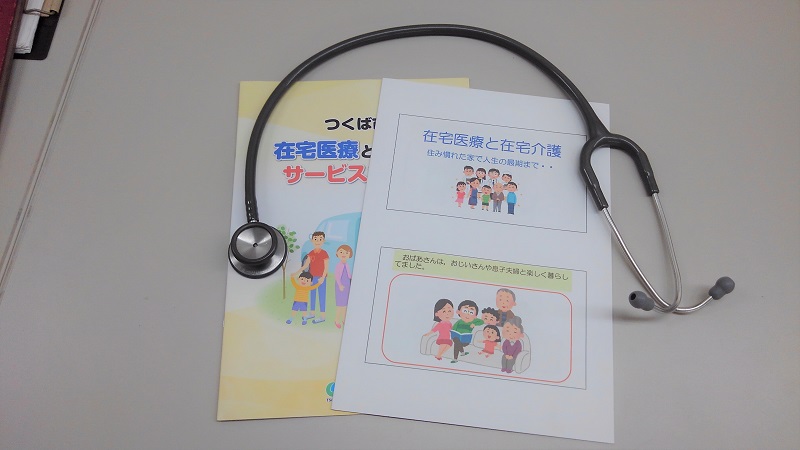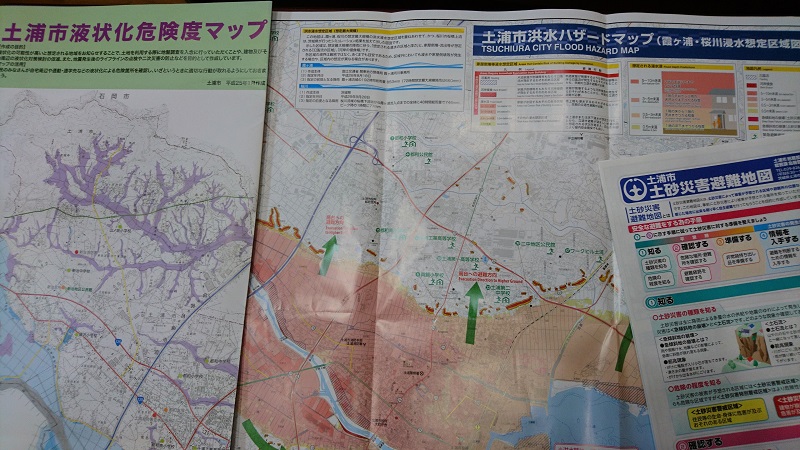【コラム・奥井登美子】「私がオジイサンの始末を、キチンとして送り出すから大丈夫よ。でも、親戚やご近所さんにはオジイサンがボケたこと言わないでネ」
姑(しゅうとめ)の奧井静は、外国人と英語で話せる薬剤師。個性的で面白い人だった。庭の中に隠居(いんきょ)所を建てて老夫婦で暮らしていたが、舅(しゅうと)の認知症に苦労していたらしい。その姑が心筋梗塞(しんきんこうそく)を起こし、一足先にあの世にバイバイしてしまった。
舅には、姑が死んだとわかっている日と、生きていると思い込んでいる日がある。高校生、中学生、小学生、3人の娘たちに協力してもらって、「生きている日」には皆で「オバアチャン生きているゴッコ」をしてごまかす。お手伝いさんのほかに、奥さんを亡くしたお隣の久助さんに、話し相手をしてもらったり、小学生の子は帰りがけに友だちを呼んできて、オジイチャンの枕元でゲームをしたりした。
長男の奧井誠一(東北大学薬学部教授)を45歳で亡くしてから、チト、うつ病気味だった舅は、今度は次男の勝二を呼べと言って騒ぎ出す。彼は千葉大学の外科医。徹夜で手術をするような忙しさだった。3男の私の亭主は中外製薬の研究所勤務。実験が始まると帰宅できない日もある。毎朝3時に起き、舅の布オムツを竿(さお)に5本分を洗濯し、6時の電車で東京に通勤した。
楽しい老後をどう実現するか
皆が皆それぞれ、自分のやれることを一生懸命やって介護していたが、人々が寝静まってくると、淋(さび)しくなるらしい。「死にたい」と言い出して、何でも紐(ひも)を首に巻いてしまう。ネクタイ、寝間着の紐など、紐状のものはすべて隠してしまったが、今度はカーテンを割(さ)いて首に巻き付ける始末。事故すれすれの毎日だった。
義兄は外科医なので精神科のことはわからない。友だちの病院に入院させ、「老人性うつ病」に詳しい医者に診断してもらった。「立派な老人性うつ病です。入院中の安全のために、両手を縛らせていただきました」。
苦闘の日々から40年。今度は自分たちが老人性うつ病を心配する年齢になってしまった。楽しい老後はどうやって実現すればいいのだろうか。(随筆家、薬剤師)
➡奥井登美子さんの過去のコラムはこちら