【コラム・川端舞】2019年夏、子どもたちに障害について考えてもらおうと、「つくば自立生活センターほにゃら」が「インクルーシブ読書感想文コンクール」を開催しました。
このコンクールが開催されたきっかけは、昨年6月に「わたしが障害者じゃなくなる日」という本が出版されたことです。この本は、東京で障害者の地域生活を支援している「自立生活センター東大和」の海老原宏美さんが、自身の重度身体障害者としての経験をもとに書かれたものです。
海老原さんは、この本を通して、子どもたちに、「障害という問題の原因は障害者自身にあるのではなく、障害者が暮らしづらい社会の仕組みにある」という社会モデルの考え方を伝えるとともに、障害があってもなくても、困ったときは周りに助けを求めることの大切さを伝えたかったと言っています。
この思いに共感したつくば自立生活センターほにゃらの斎藤新吾さんを中心に、「インクルーシブ読書感想文コンクール」が企画され、市内の小学生をはじめとして、全国各地の小学生から20以上の作文が寄せられました。
「障害のある人が困っていたら助けたい」
コンクールの表彰式が2月15日、つくば市役所コミュニティ棟内で開催され、受賞した12人の子どもたが賞状を受け取り、その後、子どもたち一人一人が本を読んだ感想を発表しました。
社会モデルの考え方を理解するのは小学生には難しい面もあると思いますが、子どもたちはそれぞれ障害という問題を自分自身の生活に引き付けて考えて、「障害のある人が困っていたら助けたい」「みんなにとって生活しやすい社会になればいいと思う」など、自分なりの考えを発表していました。
表彰式には、読書感想文の課題図書の作者である海老原さんも参加し、お祝いの言葉を子どもたちに送りました。その中で、海老原さんは「みんなが生活しやすい社会にするためには、障害のある人とない人が友達になって、一緒に生活することが大切だと思います」と語っていました。
本を読み、障害という問題を自分の生活に引き付けて考える力を持っている子どもたち。しかし、読書を通して考えたことが本当に子どもたちの体にしみこんでいくためには、障害のある子とない子が友達として一緒に成長していくことが大切です。本の中だけでなく、実際の生活の中で、障害のある人とない人が当たり前に関わりあえる環境が広がっていくことを願っています。(つくば自立生活センターほにゃらメンバー)
➡川端舞さんの過去のコラムはこちら

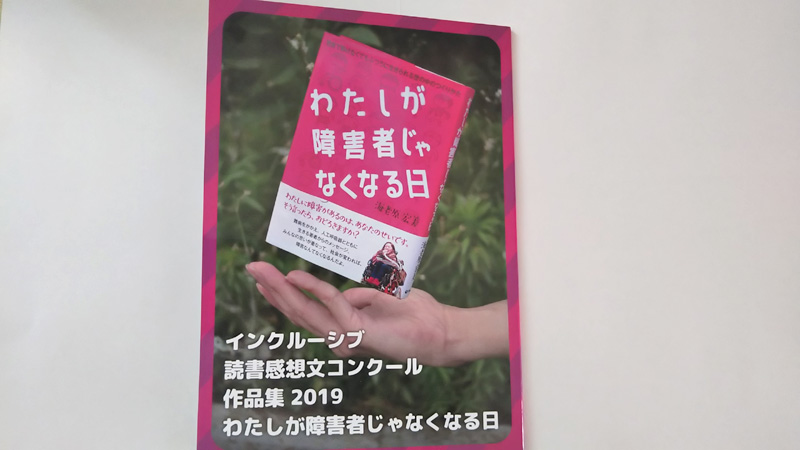












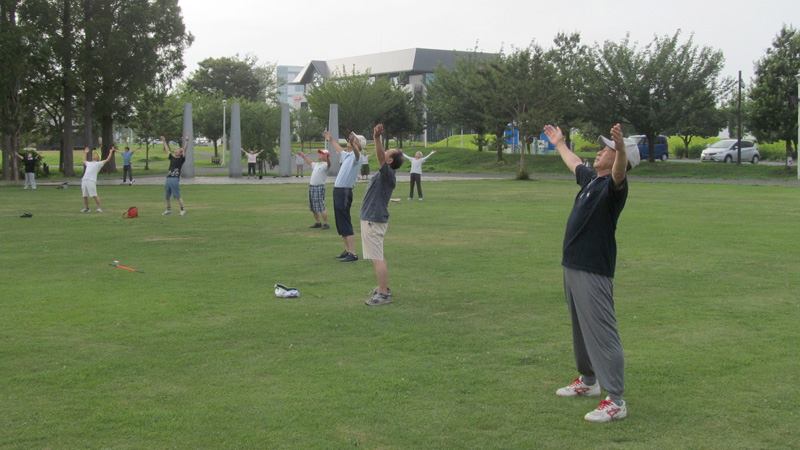
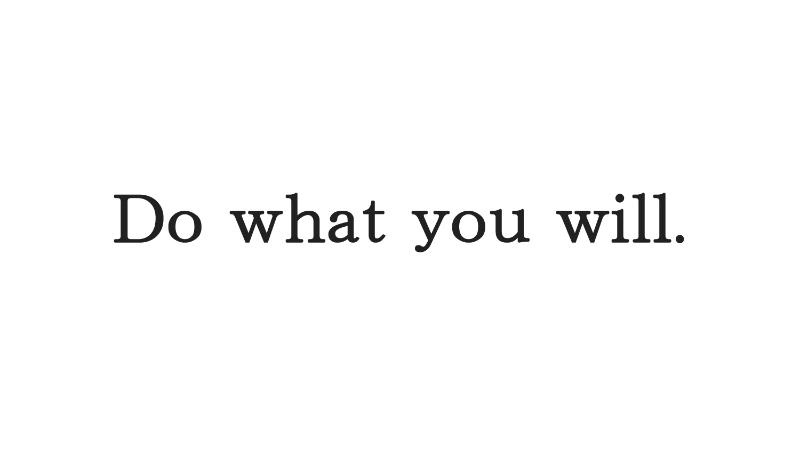
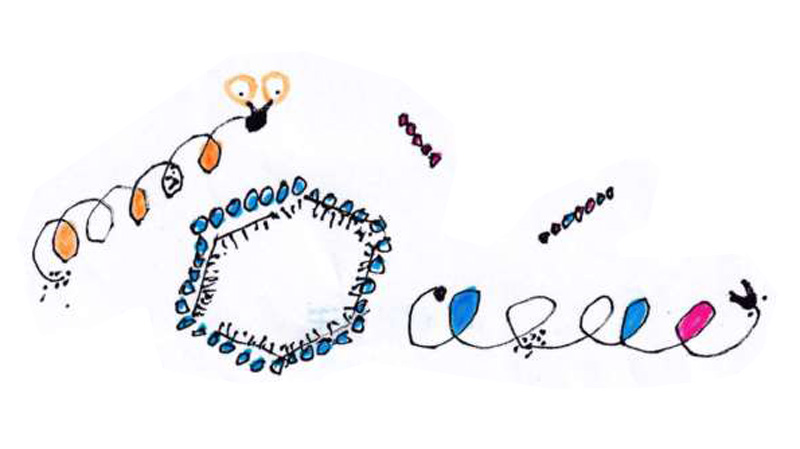


![9183882905242ef7bac5f723dc66cc23[1]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2020/02/9183882905242ef7bac5f723dc66cc231.jpg)
