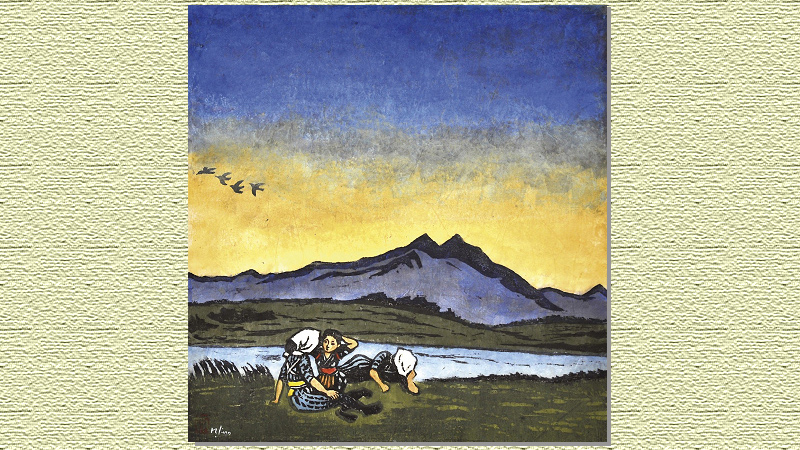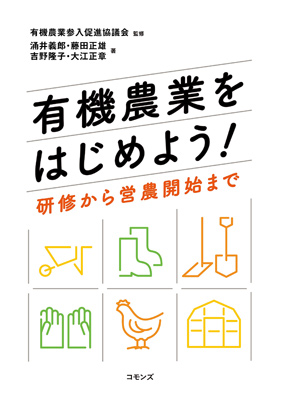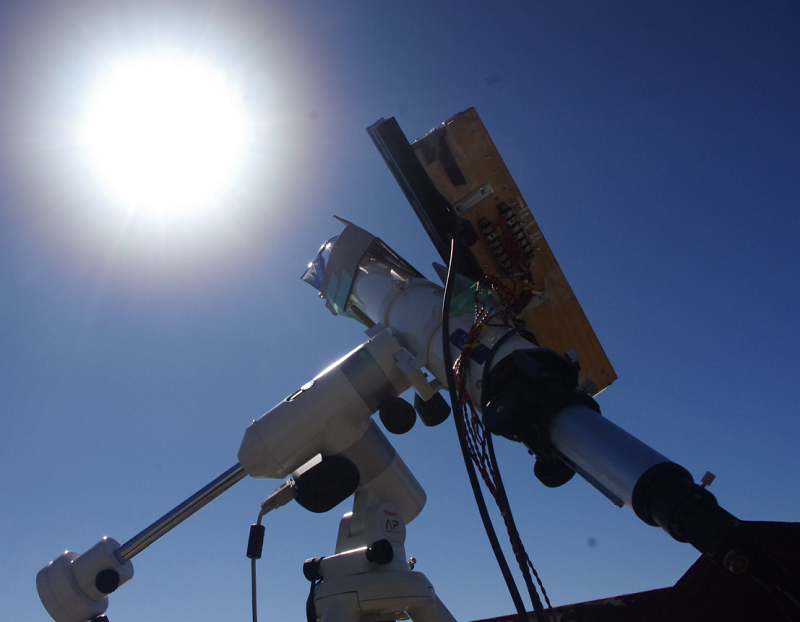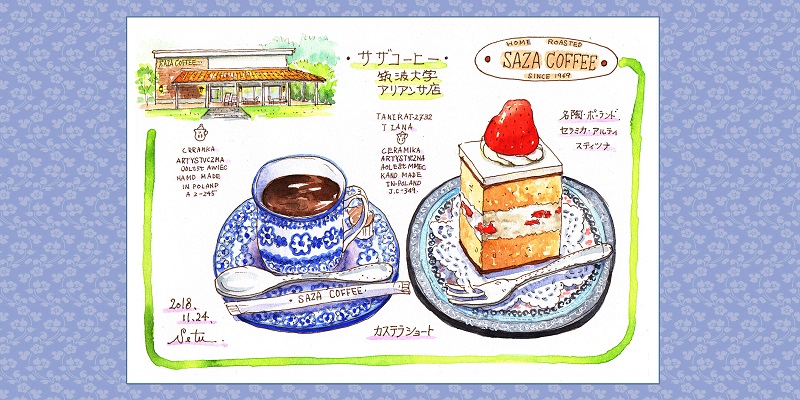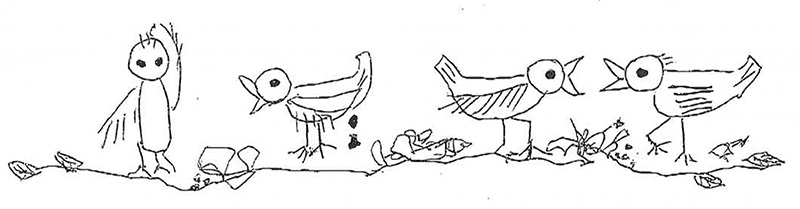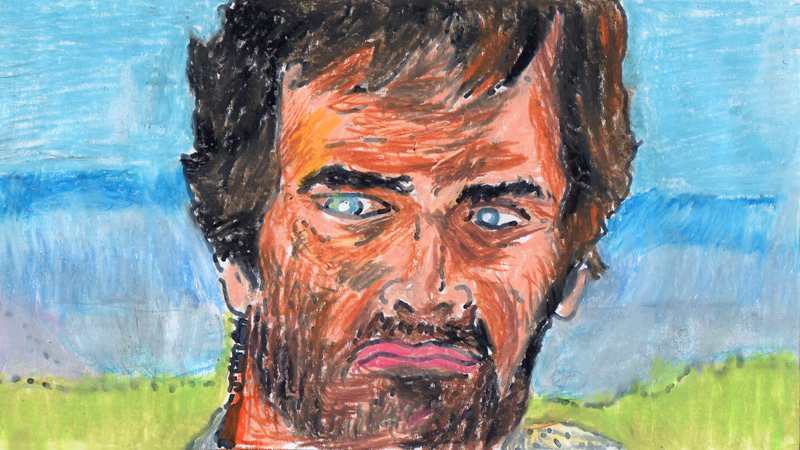【コラム・斉藤裕之】「冬の朝、洗濯機から出した冷たいシャツの袖に手を突っ込んで引っ張り出すことほど嫌なことはない」。これくらいのことは英語でガツンと言ってやりたい。洗濯物の袖を「ボーシット!」とひっくり返しながら、私は思うのです。
以前にも書いたことがありますが、日本の英語教育に私は疑問を感じています。第1に、この国では日常的に使うことがない英語を必死こいて学ぶ意味があるのかと。それでも英語は必要というならば、今のやり方では手ぬるい。
本気ならば、小学校入学時から週数時間は必修化するべきでしょう。また、例えばフィリピンなどの英語教育先進国からノウハウを学ぶべきです。大学入試に、民間の試験どうこう言っている暇があったら、本気でやれよって。
私自身も英語教育の犠牲者として悔しい思いもしましたし、私の子供たちの時代には間に合わず、果たしていつになったら日本人は普通に英語が使えるようになるのでしょう。今のままでは、英語の話せるエリートとそうでない者の差が生じるだけです。
英語漬け宿泊学習施設
そんなことを感じながら、未練がましく車中で英語のCDなんか聞いているところに、「教室をイギリス風にして欲しい」という突然の相談を受けまして。英語教育に力を入れているという市内のある中学校。東北地方のある施設に毎年英語の研修に訪れていて、空き教室を、その記録などを展示する部屋にしたいとのこと。
パンフレットを見ると、この施設、緑深き森の中、イギリスの大邸宅を移築してきたかのような豪華な造りで、某語学学校が経営するネイティブのスタッフによる英語漬け宿泊学習施設だとか。
こんな私でお役に立てばということで、とりあえず現場に向かってはみたものの、そこはただの日本の典型的な学校の教室。かみさんの趣味で、アガサ・クリスティーやホームズなどのドラマをテレビでイギリスの風景はよく見ているものの、限られた条件でどうしたものかと思案。
結局、ブリティッシュグリーンなどの色彩を効果的に使うことともに、読まなくなった英語で書かれた本を寄付してもらい、ディスプレイなどしてなんとかイギリス感を出すことにしました。
ちなみに、かの宿泊施設は「ブリティッシュ・ヒルズ」といい、キャッチコピーは「パスポートのいらない英国」。皮肉にも、イギリス本国はEU離脱でてんやわんやで、出入国も面倒くさくなりそうですが。
あ、洗濯物の袖や裾はちゃんと出しましょうね。はい、これを英語で!(画家)
➡斉藤裕之氏の過去のコラムはこちら