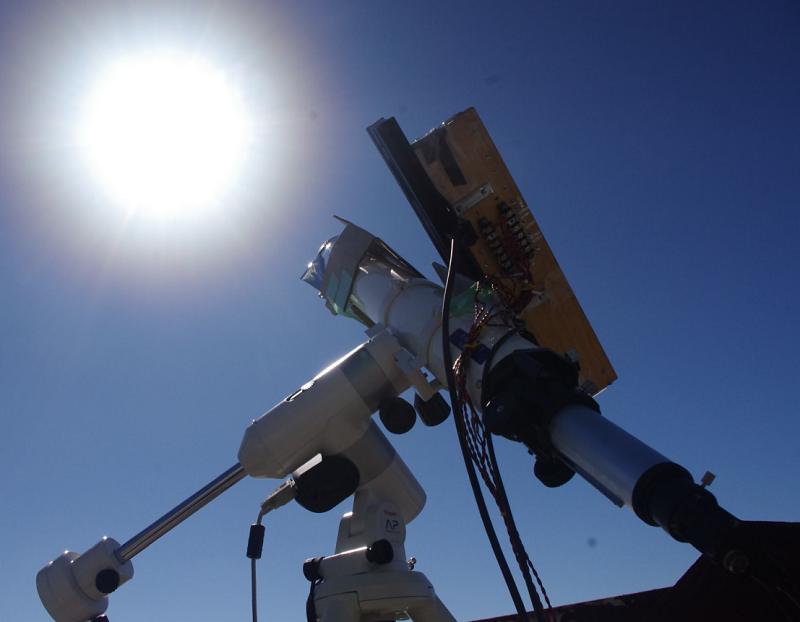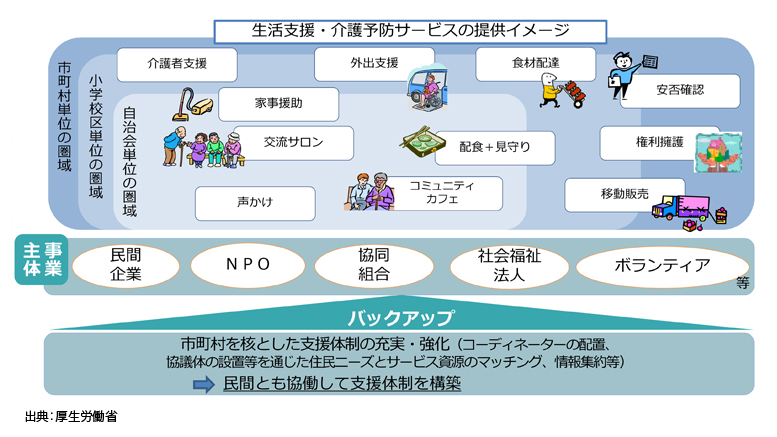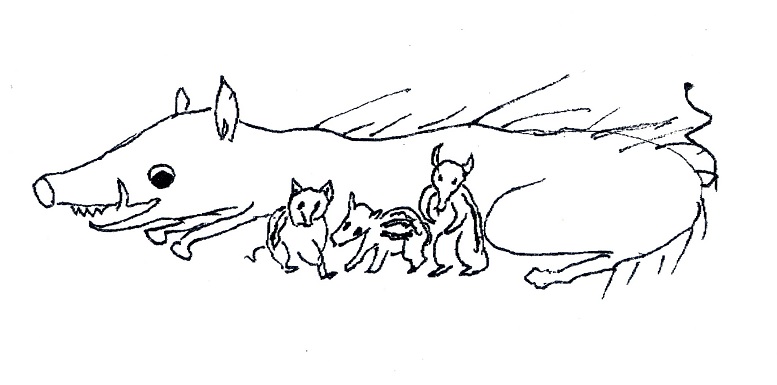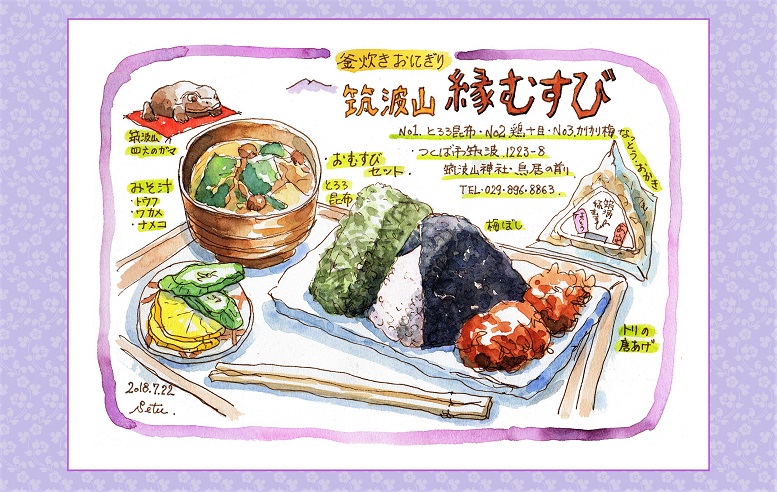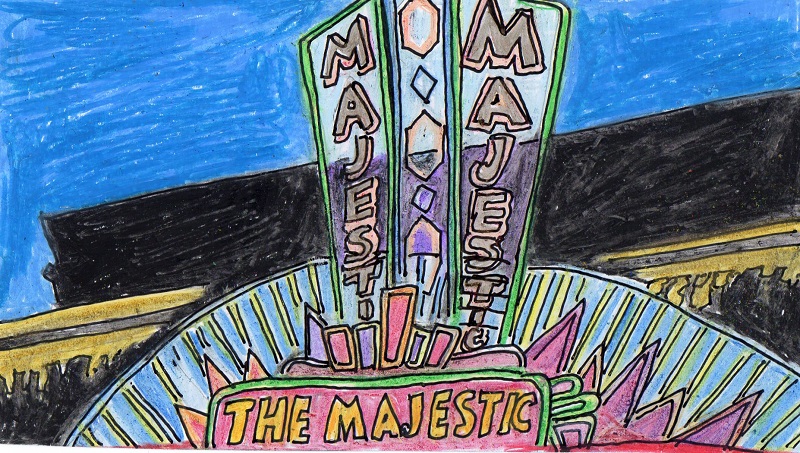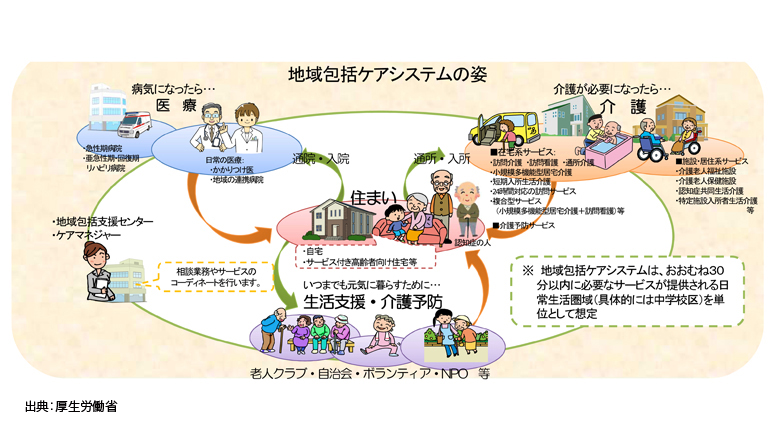【コラム・浅井和幸】「多くの交通事故が自宅の近くで起こっている」という話を耳にしました。インターネットで調べてみると、内閣府や国土交通省、警察庁などの統計が出てきます。不慣れな道ではなく、ある程度知っている道での事故が多いことは、気を抜いてしまう注意不足からくるのでしょうか。この道路は、車や歩行者は通らないというような、決め付けもあるのだと思います。
自動車の運転で、初心者のころはビクビクしているからあまり大きな事故は起こさないけれど、慣れてきたころが危ないから気をつけろと言われたことがあります。そういえば、福祉でも悩み相談でも、大きな事故を起こすのは、自分は大丈夫だと思い込んだときなのかもしれません。
私は保護犬の散歩ボランティアをしていますが、犬を逃がしそうになるときや、かまれそうになるときは、自分ならば大丈夫だと過信したときや、慣れてきたときに事故が起こるのを体験しています。こう考えると、慣れというのは良いことばかりでなく、悪い慣れというのもあるのだと分かります。
パニック障害
悪い慣れといえば、パニック障害になってしまう過程も、悪い慣れということがいえます。パニック障害とは、例えば、ステージで歌うことが出来ていたのに、だんだん出来なくなっていく。手が震えたり、心臓がドキドキしたり、過呼吸になったりと、緊張の度合いが度を越えて高くなり、結果、ステージに立てなくなるものです。ステージどころか、学校に行けない、車に乗れない、知り合いとも目も合わせられないといった症状の人もいる心の病です。
人前に出ると緊張して話ができない。結婚式のスピーチや余興の歌を披露する際、緊張を少しでも和らげるために、酒を一杯ひっかけてからという話もよくあることですね。人前で緊張してしまう人に対して、慣れればよいのだからどんどん人前に出ろというアドバイスをしてしまいがちですね。
確かに、それで上手くいくケースもあるでしょう。それは、その人のペースに、たまたま上手く刺激が調整出来ていたからなのです。これを「良い慣れ」ということが出来ます。もし、良いタイミングでなければ、どんどん緊張の度合いが強くなるような練習になってしまいます。緊張と失敗の繰り返し。それがひどいときには、パニック障害などを発症してしまうということなのです。
耐えられる程度の失敗ならば問題ありませんが、受け入れきれない失敗はしないほうがよいでしょう。なので、一か八かのような挑戦は、あまりお勧めできません。できるところから徐々に世界を広げていくことは、とても大切なことです。
自分にとって良い挑戦とは何か、良い慣れは何かという観点を持ちながら、出来ることを少しずつ重ねていくことが、とても大切なのです。(精神保健福祉士)