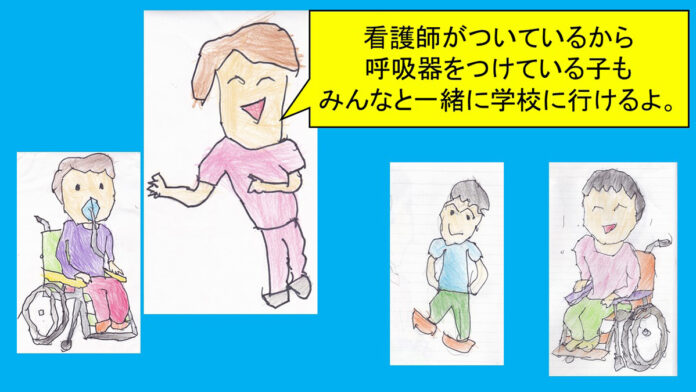【コラム・瀧田薫】古代オリンピックは、紀元前776年から紀元393年まで、1200年近くにわたって、ギリシアのオリンピアの地で行われた。この古代オリンピックと近代オリンピックとの違いは、古代オリンピックがゼウス神にささげる宗教的祭典だったことである。大会開催中、参加国は聖なる休戦(エケケイリア)を守り、オリンピアへの往還と神域における武力行使を堅く戒めた。
その結果、1200年間、戦争が原因で大会が中止されたことは一度もないという。一方、近代オリンピック120年の歴史には、2度の大戦による大会中止をはじめ、テロによる選手殺害事件(1972年)や、大国によるボイコットの応酬(1980年、1984年)があった。
西洋史学者の橋場弦(はしば・ゆずる)氏は「商業主義とグローバル資本の論理に翻弄される現代のオリンピックは、どこに向かうのか。金銭を超えた聖なる価値を、オリンピックが見失うことのないよう祈りたい」(UTokyo FOCUS 2020年4月)と述べている。
争点は財政政策(増税か減税)か?
さて、衆議院議員選挙の日程だが、コロナの感染爆発中にオリンピック開催を強行した菅首相だけに、オリ・パラ会期中の選挙はないだろう。永田町では、パラリンピック後の9月6日に臨時国会を召集し、補正予算を通して、28日公示、10月10日投開票というスケジュールが有力視されている。ただし、これも「ワクチン接種」の進み具合で延期される可能性がある。
菅政権としては、選挙前に国民の60%程度の接種を終えておきたいところだ。その場合、選挙日程はギリギリ11月28日になる可能性がある。臨時国会を開き、10月21日の衆院議員の任期満了日に解散する方法だが、さすがにこの日程の現実味は薄い。選挙の争点は、コロナ対策、特に財政政策で、具体的には「増税か減税」か、与党、野党それぞれの思惑が交錯する選挙となるだろう。
政府は、コロナ禍への対応で、20年度に3次にわたる補正予算を編成した。医療現場への補助金、企業向け支援、全国民への一律10万円支給などがその中身だが、財源の大半は国債の追加発行(20年度の新規国債発行額は100兆円の大台を超えた)であり、これは過去に類例のない規模である。リーマン・ショック後には消費税の10%への引き上げがあり、東日本大震災後には所得税、住民税、法人税の上乗せがあった。現在、財政当局の本音は「景気回復を条件とする増税案(消費税15%?)」だろう。
これに対し、自民党は選挙前の「だんまり」を決め込み、菅首相は「10年間は消費税を上げない」と公言している。逆に野党は、この時とばかりに「減税」(れいわ新選組の消費税5%案など)を主張するだろう。選挙民にとっては、どう考え、誰に投票するのか、悩ましい選挙となるだろう。
専門家による投票結果予想としては、自民党の議席減で現政権の退陣もあり得るが、自民・公明両党での過半数は維持できるとの見方もある。選挙の結果がどう出ようとも、その後に、財務当局の増税案が急浮上してくることは確かである。(茨城キリスト教大学名誉教授)

![瀧田薫 26[5045]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/08/8415bc894c4e4b4b551f5b4daaf32530-696x392.jpg)









![ひょうたんの眼 39[2305843009236009889]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/07/2054b0849bad2550984c912164078ffe-696x392.jpg)
![くずかごの唄 90[2305843009236009654]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/07/aca05f7b5678c865592917d6fd1c047b-696x392.jpg)
![斉藤裕之 90[2305843009235941421]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/07/26f90825b8f411f03977ae34863806a8-696x447.jpg)