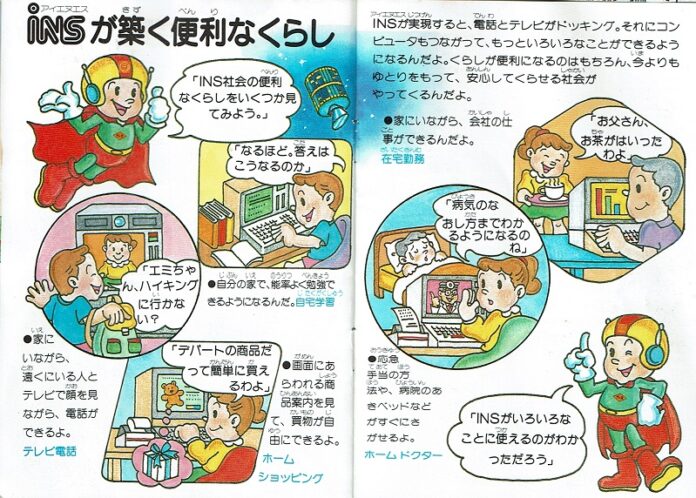【コラム・斉藤裕之】「先生、どうやって学校に来てるんですか」「車」。すると隣の男子がすかさず、「軽トラ!」というツッコミ。春先に買った中古の軽トラはその後期待通りの活躍をしているのだが、実はもうひとつの役割があったのだ。「実はねえ、長女が子供を産むためにうちに帰ってきているものだから、いつも乗っている乗用車を娘夫婦に貸しているんだよ。それにしても、なんで私が軽トラで来ているのを知ってるの?」「だって見たもん!」
別に隠すこともないが、冷やかされるのも面倒くさいと思って、生徒たちが大方登校し終わったころを見計らって、軽トラで校門を通過するようにしていたのだが…。しかし、たまたま遅刻気味のこの生徒に目撃されていて、「軽トラ先生!」と冷やかされるはめになった。
高校生だったころ、古典のK先生はセピア色の軽自動車に乗って学校に来ていた。先生のご自宅の近所に住む合田君は、「K先生の家は米屋で、あの軽自動車でよく米を配達するんよ」と教えてくれた。カラカラというやや非力なエンジン音が聞こえると「お、K先生の米屋カーじゃ!」と冷やかしていた。先生はそんなことを気にもなさらず、さっそうとしておられた。余談だが、K先生のご子息が1学年下にいて、確か現役で赤門をくぐられた。
それから、もう1人思い出すのが筑波大学の芸術系のある先生。とてもきさくでユーモアのセンスに富んだ方で、教え子の方々からも厚い信頼を得ておられたようだ。ある日、その先生がやや薄汚れた軽自動車から降りて来られるのを目撃した。地位も名誉もあるのに、メンツや外聞を気にしない。そんな先達のたくましい姿を思い出しつつも、「でもやっぱ、さすがに軽トラはねえな」。なにしろ、私の見てくれは明らかに工事関係者。
チャイルドシートが届いた
さて、大きな荷物が届いた。チャイルドシートだ。若い夫婦は早速それを私の車に取り付けた。もうすぐこのシートに乗って赤ん坊が帰ってくる。とにかく元気な子であってほしいと願うばかりだが。
登校時間の校門には生徒を乗せてくる車が次々とやって来る。国産車に交じって、高級な欧州車も少なくない。その間隙をついて、その日も軽トラで校門を通過。梅雨の晴れ間で、朝から気象予報士が「洗濯日和」を連呼していた。午後1時過ぎ。帝王切開にて3700グラムの男児を無事に出産という知らせ。すぐに動画が届いた。元気な産声を上げる立派な赤子と安心したような顔の長女。「でかした!」
待てよ、軽トラにはチャイルドシート付けられないなのかなあ。軽トラのモノラルラヂオから、ややこもり気味にレディ・ガガの曲が流れた。「ボーン ディス ウェイ」。(画家)






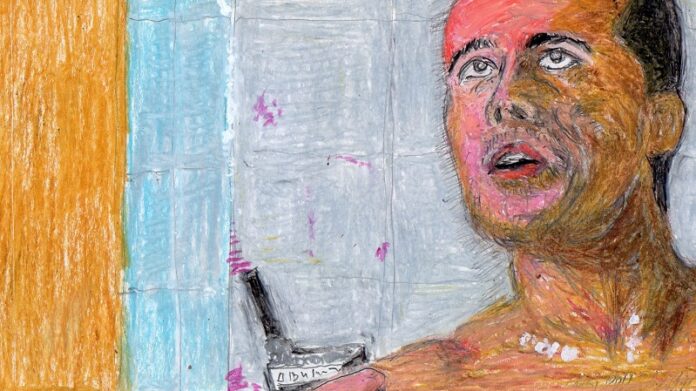
![田口哲郎 20[4511]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/07/cbc28d79db4c68e92f784ee5eb9ad4dd-696x391.jpg)
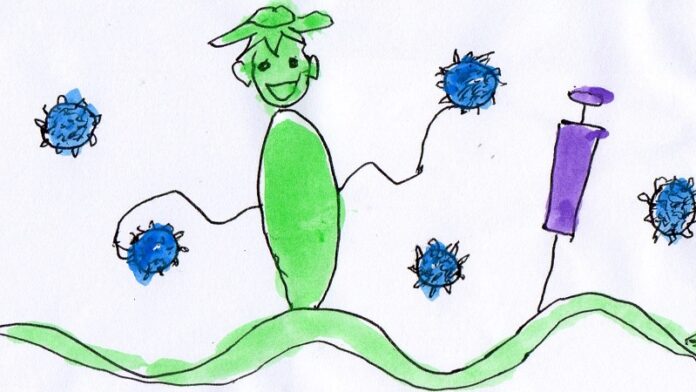
![瀧田薫 25[2305843009234764633]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/07/dad3fb3a3bce58d764d90c51b3f8a455-696x392.jpg)



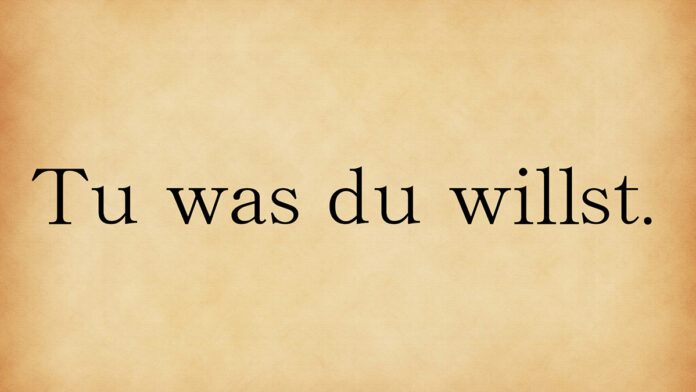
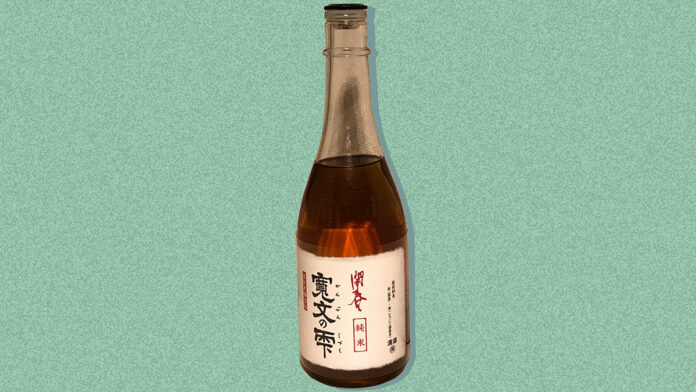
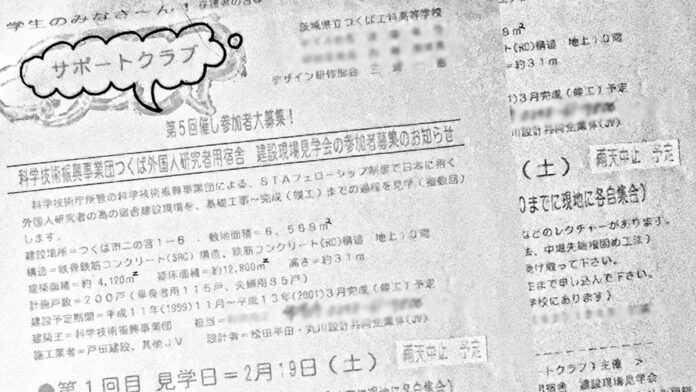

![邑から日本を見る 90[4263]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/06/2a12fbc27eeffa348ffecce1922d219e-696x392.jpg)

![宍塚-2 [復元]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/06/9da1754895972ca256b67c07c0d7bf11-696x392.jpg)