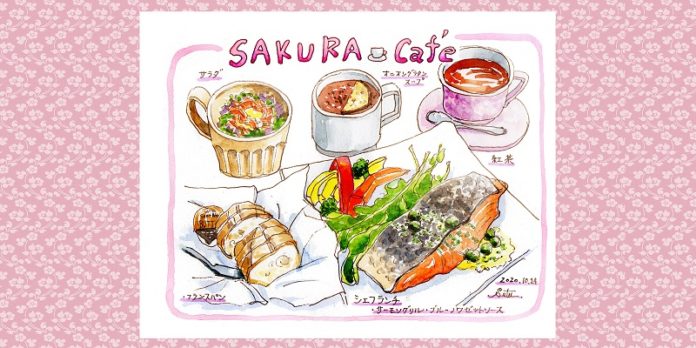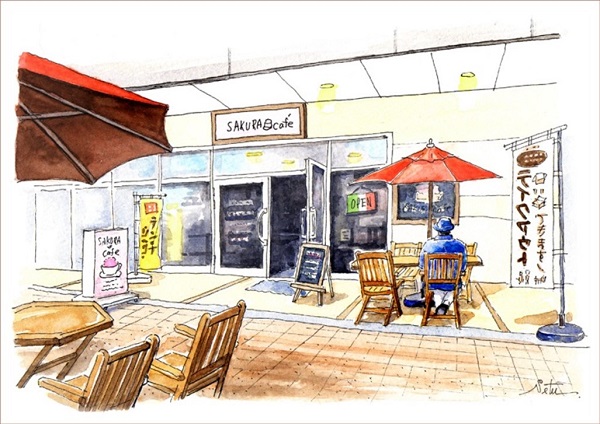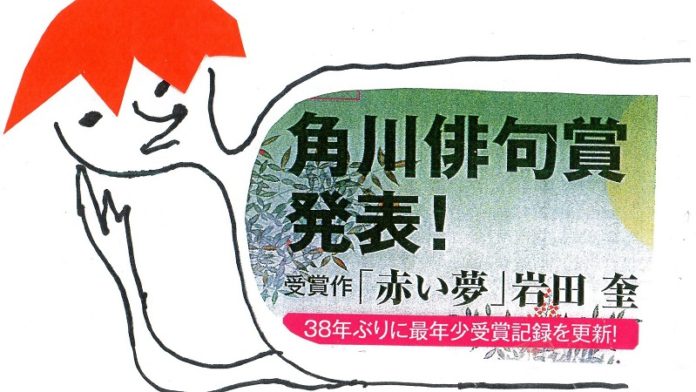【コラム・坂本栄】民間会社の場合、株主や顧客に業績や商品について理解してもらう仕事を広報と呼び、企業活動にとっては大事な分野です。公の市政の場合、その対象は市民になりますが、10月に再選された市長の五十嵐さんは、選挙活動の中で市政への理解不足を痛感したらしく、2期目では広報に力を入れるそうです。
その意気込みについては、11月の会見記事「発信の在り方 根本から検討」(11月5日掲載)をご覧ください。理解不足の例として、①市のかなりの取り組みを知らない市民が多かった②対抗候補も市の基本的な取り組みすら知らなかった③市政について相当いい加減なことを書く人もいた―などを挙げ、「市民が必要としている情報をどうやって届けられるか、あらゆる手段を考えたい」と述べました。
広報の充実はメディアも大歓迎です。でも、市民の理解不足を嘆き(平均的な市民が市政の詳細を知るのは無理)、対抗候補を見下す(彼らは無投票を避けようと急な準備で出馬を決断)ような、「上から目線」はいただけません。また、観察者(開示情報を基に市当局とは違った視点でチェック)を煙たがるようでは、度量が狭すぎます。
施策を立案・実施する市長がその内容に精通しているのは当たり前ですから、自分との比較で、①②③の方々の理解度にブツブツ言うのはいかがなものでしょうか。
広報は「自然体で」「虚偽はダメ」
経済記者が長かった私は、上場会社の広報責任者から広報の在り方についてよく相談されました。旧財閥系企業の広報コンサルタントが主催するセミナーでも、よく講演させられました。そういった際には、「自然体で対応する」「ウソをつかない」ことが大事とアドバイスしたものです。別の言い方をすれば、装飾や虚偽はいずればれる、そのとき会社は信用を失い、経営が危機に至るケースも―ということです。
行政広報と企業広報は同じではありませんが、「自然体で対応する」「ウソをつかない」は受け手が誰であろうと同じです。そして大事なのは、「広報の方法」ではなく、「広報の中身」であることは言うまでもありません。テクニックにこだわると宣伝臭くなり、信用されなくなります。
「NEWSつくば」は5月、市長と日本財団理事長の面談録(新型コロナ軽症者施設を市内の同財団敷地に設置する件)を開示するよう市に請求しました。6月9日付の回答は「存在しない」でしたが、25日にその旨を記事にしたところ、30日になって「発見された」と修正してきました。虚偽がばれると思ったのでしょうか? その詳細は本サイトの記事(7月29日掲載)をご覧ください。
五十嵐さんは市長選の討議資料で、1期目を「9割以上の公約が達成もしくは順調」と自己採点しています。これに対し、本コラム(10月19日掲載)では「総合点は60点以下」と判定しました。選挙向けとはいえ装飾はいけません。市報でも、市HPでも、SNS発信でも、報道対応でも、広報は虚偽と装飾を排し、自然体でお願いします。(経済ジャーナリスト)






![horikoshi[1]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2020/02/horikoshi1.jpg)
![雑記録 18[161]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2020/11/6ff94e5532bfbd92fb1bd93324c4c44e-696x391.jpg)

![令和楽学ラボ 10-1[145]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2020/11/f8a146bee712292342a34894ffa08be3-696x392.jpg)