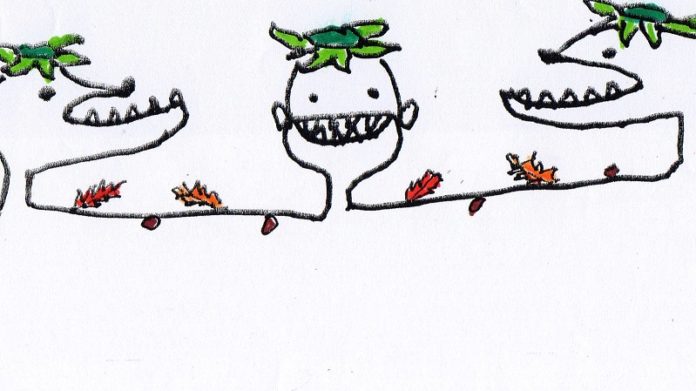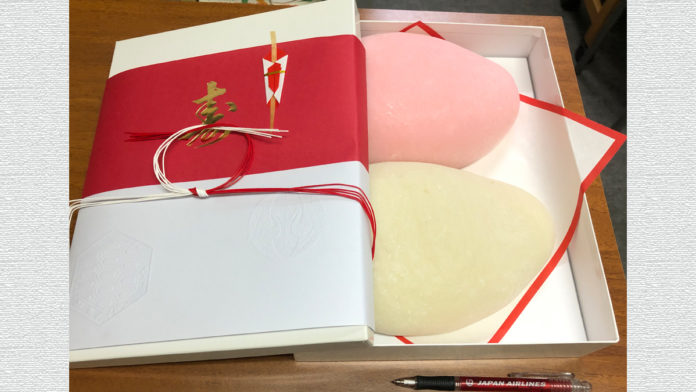【コラム・浦本弘海】おかげさまで法律かけこみ寺の連載もついに24回。今回と次回では、過去11回分の連載を振り返りつつ、まとめと解題をしたいと思います。(<>内の青字部をクリックするとそのコラムに飛べます)
<13 素顔の告白>
冒頭からですが、この回も連載第1回から第6回までを振り返った総集編。詐欺的商法から著作権まで、いろいろなトピックをまとめた、いわば幕の内弁当です。
見出しは三島由紀夫『仮面の告白』より。
ちなみにコラムのなかで特段の告白も告発も告訴もしておりません…。ところで告発は「被害者など以外の者が、犯罪事実を捜査機関に対して申告し、犯人の処罰を求めること」、告訴は「被害者などが、犯罪事実を捜査機関に対して申告し、犯人の処罰を求めること」で、両者は微妙に異なります。
この回も連載7回から12回までの総集編です。放置自転車から隣家から枝が伸びてきた場合の話まで、近隣トラブル関係が多くなっております。
見出しは福永令三『クレヨン王国の十二か月』より。
よくいただくご質問に「裁判に勝ったら、国が相手方から強制的にお金などを取り立ててくれるの?」というのがあります。その辺について詳しく(ちなみに、裁判に勝っただけでは国はなにもしてくれません)。
見出しはフィリップ・K・ディック『最後から二番目の真実』より。『最後から二番目の恋』ではありませんよ~。
消費者保護のため、一定の期間であれば契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる場合があります。それがクーリング・オフ。そのご紹介です。
見出しはアガサ・クリスティ『なぜ、エヴァンズに頼まなかったのか?』より。
<17 善悪の此岸>
第16回に続き、消費者保護に関連して、送りつけ商法対策に特定商取引に関する法律を取り上げました。ちなみに、この時期はマスクを送りつけてくるトラブルが多発していました。国民生活センターについても紹介しています。
見出しはフリードリヒ・ニーチェ『善悪の彼岸』より。 以上、第13回から第17回までを簡単に振り返りました。(弁護士)


![9183882905242ef7bac5f723dc66cc23[1]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2020/02/9183882905242ef7bac5f723dc66cc231.jpg)