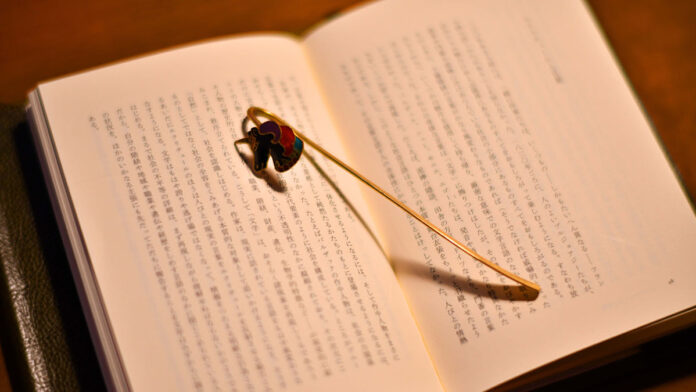【コラム・坂本栄】今回も土浦市立博物館と地元郷土史家の歴史論争問題です。1回目は158「…博物館が…論争を拒絶」(5月29日掲載)、2回目は159「…論争拒否、土浦市法務が助言」(6月5日掲載)。コメント欄への投稿に加え、コラム《ひょうたんの眼》(6月14日掲載)や市議会も論争に参入。議論が沸騰してきました。
苦情と歴史論争は次元が違う
「博物館の仕事は、城郭(研究の砦)に籠(こも)って研究するだけではなく、その成果を市民に知ってもらうことにある。この論争を見ていると、博物館は市民とのコンタクトが薄いような気がする。本堂さんとの対話を面倒くさいと断つようでは、市立博物館とは言えない。博物館は学術と市民の間に立って、学問の成果を市民につなぐのが本来の仕事」(土浦の歴史好き)
「郷土史家との対話拒否は行政の下手なリスク管理の見本。歴史論争の回答書にあんな文言(コラム158で引用)を入れたらメディアに叩かれるのは当然。博物館が論争を打ち切るのはその存在を否定するようなもの。それを市の法務担当が指導したというのは論外。一般行政への市民のクレームと市民の博物館との論争は区別しなければいけない。次元が違うものだから」(リスク管理人)
議会も博物館の対応に疑問符
コメントの中には、本堂氏が博物館に11回も通ったことに注目し、博物館の論争拒否通告を支持するコメントもありました。
しかし、博物館の面談記録(各回60~90分、糸賀館長か担当学芸員が対応)によると、2020年12月1回、2021年2月2回、同3月1回、同9月1回、2022年6月1回、同7月1回、同9月1回、同10月1回、同11月1回、同12月1回だったそうですから、論争の間隔としてはむしろ控えめなぐらいです。
この問題は市議会教育厚生委員会(矢口勝雄委員長)の会合でも話し合われました。関係市議によると、博物館が面談拒否の理由を「11回も来られ困った」と説明したとの報告について、委員からは▼本堂氏はクレーマー扱いされて戸惑っている▼市の弁護士が間に入り拒否を通告させたのは問題ではないか▼微妙な問題であり博物館は冷静に対応すべきだ―などの発言があり、博物館の対応に疑問符が付いたそうです。
自分の立ち位置から語る歴史
コメントにはクールな意見もありました。「歴史とは自分の立ち位置から過去を描写する作業。郷土史家も館長も自分の史観に都合いいように解釈している」(歴史論争嫌い)。話が脱線しますが、私の旧友、門跡寺院(もんぜきじいん=皇族や公家の寺)の門主(もんす=住職)さんの史観はその極致でした。自分事なのです。
寺は天台宗ですから総本山比叡山を焼き払った織田信長は極悪人。寺に手水(ちょうず)石を寄贈してくれた豊臣秀吉は偉い。寺領の一部を奪い他寺に与えた徳川家康は小悪人。雄藩に担がれて権力に復帰した明治天皇は期待の星。天皇制と華族制(彼もその家柄)を廃止したマッカーサー元帥は「けしからん」と。(経済ジャーナリスト)


![イラストは筆者 15.hgf[18853]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2023/06/9cf5dcc2b2afa6df00f668a48f840b68-e1686994329657-696x391.jpg)

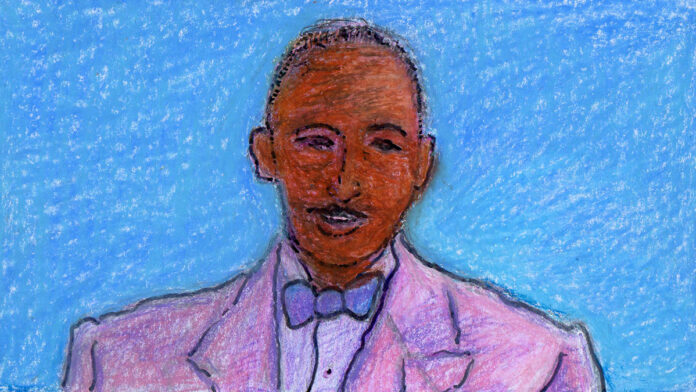


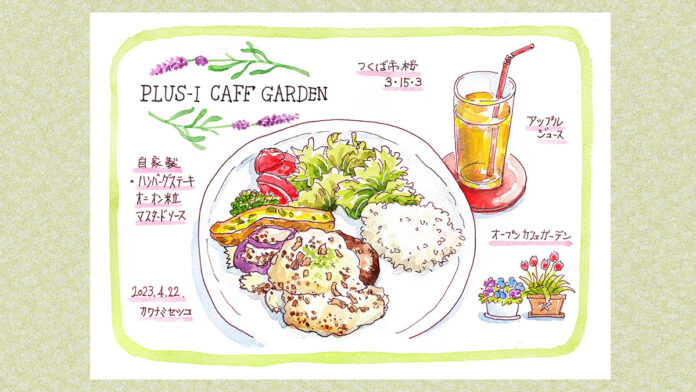

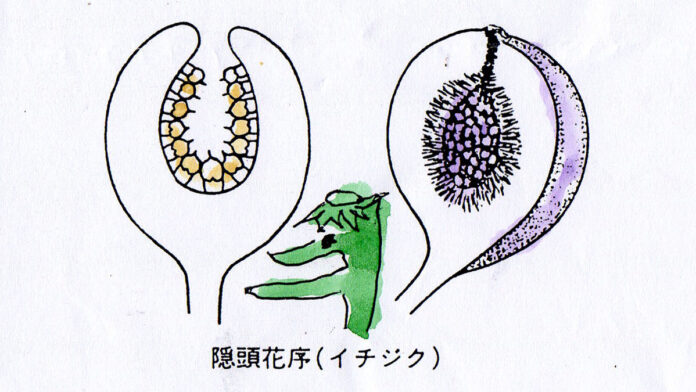




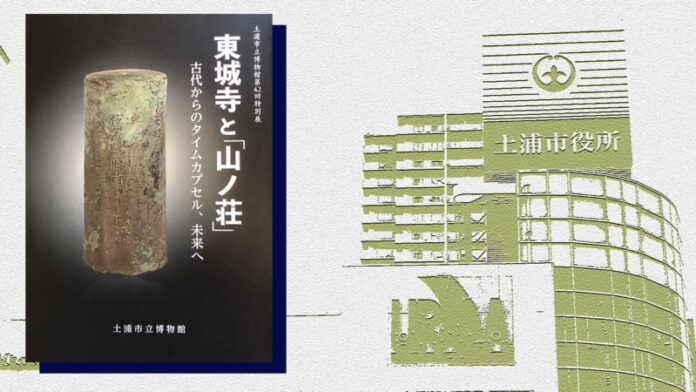
![イラストは筆者 12[18490]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2023/06/e0f7303a52c42db37cbdeb70a87bae3d-e1685797217365-696x392.jpg)