【コラム・入沢弘子】今年は3年ぶりに日本有数の市民マラソン大会「かすみがうらマラソン」が開催決定。参加予定者の方々は胸躍る思いでしょう。
そんな気持ちを少しだけ味わいたいと思い、私も10マイルコースを折り畳み自転車で走ってみました。今回はナショナルサイクルルートに指定された「つくば霞ケ浦りんりんロード」の霞ケ浦コースのごく一部。短い区間でしたが、他地域の自転車用道路と比べ、地面の凹凸や樹木の根などの障害物がなく、景色を楽しむことができ、最高のポタリングになりました。
快晴の土曜日午前9時。「りんりんポート土浦」の駐車場はまだ余裕がありました。トランクから愛車「BROMPTOM(ブロンプトン)」を取り出し、スタート地点に向かいます。
一昨年開催予定だった、第30回記念大会時にリニューアルしたスタートゲートに到着。未使用のゲートから、ランナーより少しお先に自転車で出発しました。新川を渡り、境川と並行する県道へ。この道の広い歩道は自転車通行可なので、私のような初心者ポタリストは安心です。
左手は一面のハス田の平坦な直線道。シラサギがゆるやかに飛び交っています。土浦バイパスにぶつかったら右折。両側にハス田が広がっています。今の時期は水面だけですが、初夏から秋にかけては、波のように風に揺れるハスの葉や花が見られます。
手野町南の信号を越すと、道は緩やかな上り坂になりました。民家と雑木林の単調な景色と重いペダル。ギアチェンジし、ラデッキー行進曲を歌いながらリズミカルにこいでいきます。坂を上り切った手野町信号から折り返し。途中に勾配(こうばい)4.5パーセントの標識がありました。下りは霞ケ浦越しに富士山が望める絶景です。
霞ケ浦の前に広がるハス田
坂の下に戻ったら信号を左折。石岡田伏土浦線に入ります。JA水郷つくばれんこんセンター、レンコン直売所、レンコン農園とレンコン尽くし。通称・レンコン街道です。道路から霞ケ浦まで広がる一面のハス田。今は植え付け前の準備・代かきの最中です。あぜ道には作業の軽トラックがたくさん止められていました。
沖宿郵便局を越したところで、霞ケ浦名産の看板が目に入ります。おなかが空いたので行ってみることに。「常盤商店」は、以前に土浦ブランドの仕事でお世話になったお店。住宅地の一角で、紺色の暖簾(のれん)が迎えてくれました。霞ヶ浦で獲れた魚からシラウオとエビの加工品を購入。

折り返し点から湖岸道に出ました。聞こえてくるのは、小さな波音とヒバリの声。この田村地区は土浦藩4代藩主・土屋篤直(つちや・あつなお)が編んだ「垂松亭(すいしょうてい)八景」に詠まれた場所。道沿いの古い水天宮・水神社は、霞ケ浦と肥沃(ひよく)な土地に恵まれたこの場所の農業・漁業を見守ってきたのでしょう。
霞ケ浦越しに見える、土浦駅周辺のビル群を眺めながら走っていると、あっという間にりんりんポートに到着。出発から1時間、16キロの小さな旅でした。
「かすみがうらマラソン」まであと2週間。当日の好天候と、参加者の皆さんが安全に楽しめることをお祈りしています。(広報コンサルタント)




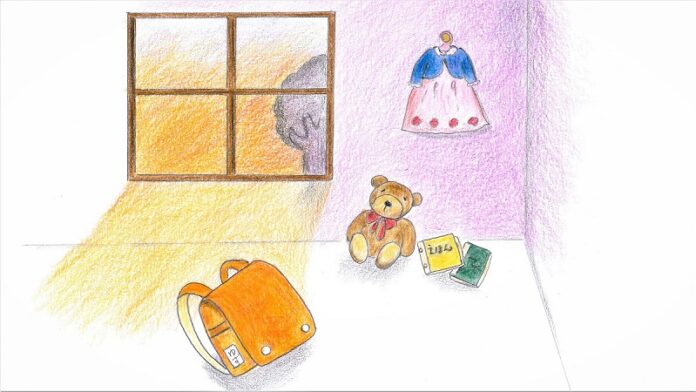


![川上美智子 17[2305843009284191779]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/03/a0d51b1ebb42a167a0fb272fc504bb3e-696x391.png)
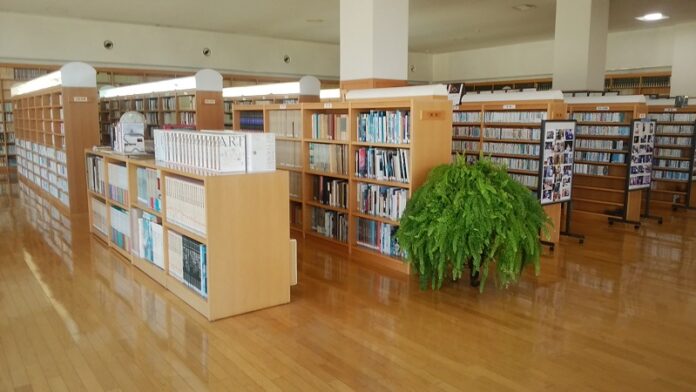








![川端舞 28[10155]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/03/3f633051ef23b984373a45baa11e61bb-696x392.jpg)
![奥井登美子 104[10153]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/03/14e9f1c8999b55d745d523fc38095ac8-696x392.jpg)
![川浪せつ子 45[2305843009281695504]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/03/19c54caf937c17ffdcd0a284c40f8e3b-696x348.jpg)
