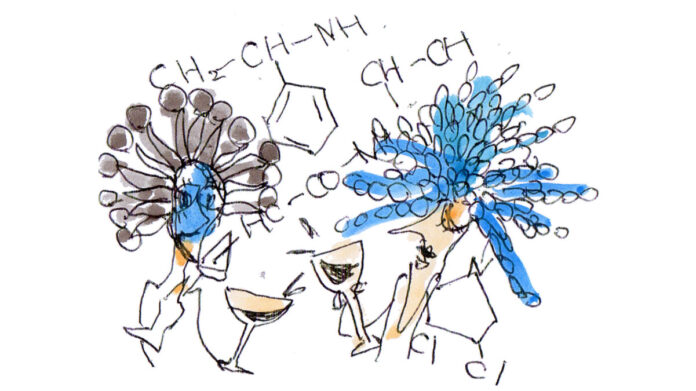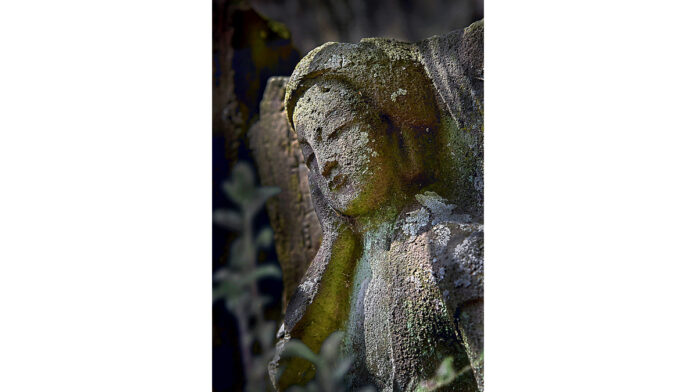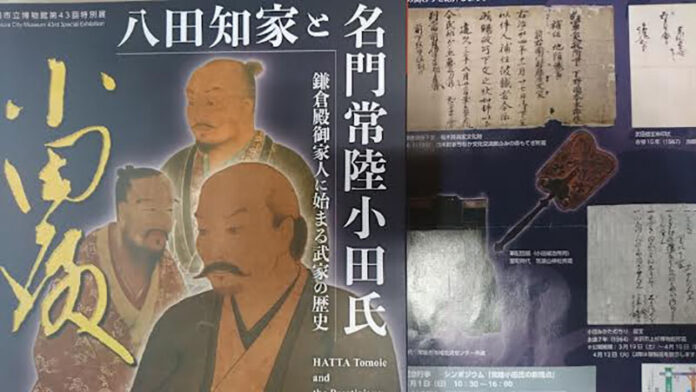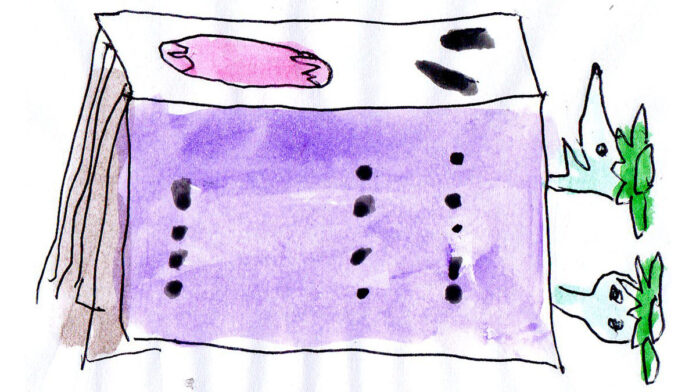【コラム・浅井和幸】かなり昔の学園ドラマで、「腐ったミカンがあるとその箱の中の他のミカンも腐るから早めに取り除かなければいけない」というニュアンスのセリフがありました。主人公の先生は「〇〇(生徒の名前)は腐ったミカンじゃない」と突っぱねていたような気がします。
ネットで検索したら、もう40年以上前のドラマのようですね。いやはや、よく覚えていないわけだ。
さて、実際問題ではいかがでしょうか。やはり、職場などで問題を起こす人物にやきもきさせられ、どうやって辞めさせようかと考えている人も少なくないでしょう。
確かに問題を起こす1人を辞めさせると、一気にチームのパフォーマンスが上がりより良い職場になっていくということもあり得ることです。しかし、1人を変えても、また別の人材が足手まといに感じて、悪口の対象になる人間関係というのは少なからずあるものです。
その腐ったミカン・ポジションの人を排除しても、また別の腐ったミカンが現れる。そう感じたときは、実はその場自体に腐ったミカンを作りだすメカニズムができている可能性があります。
どんなに優秀な人が集まった大学でも職場でも、必ず落ちこぼれは出るものです。「経済学者のヴィルフレド・パレート」とか、「パレートの法則」とか、「80:20の法則」とか、「2:6:2の法則」などで検索してみると、面白い情報が出てきますよ。
くず材料でおいしいラーメンを作る
優秀か優秀じゃないかという一つだけの定規、もしくは自分の好き嫌いの判断で、嫌いなものを取り除くことが、結果、自分の望まない方向にその場を動かしてしまうこともあります。そもそも、その「悪いもの」を排除することが難しい場面もあるでしょう。
そんなときは、その「悪いもの」の評価の善悪を抜きに、どのような性質があるかを洗い出し、それを生かすリフレーミングをすることをお勧めします。頑固者は意志が固いとか、お節介は面倒見が良いとか、声が小さいは控えめ―など。
それら短所だと思えるものを特徴としてとらえ、長所にしていける方法や組み合わせを考えて試してみるのです。
例えば、くず材料でおいしいラーメンを作るイメージでしょうか。他の料理では使えそうもないくず野菜や鳥や豚などの骨。これらを味見して、まずいから取り出しちゃえとなったら、おいしいスープが取れなくなるかもしれません。
毒は薄めると薬になることもあるものです。もともと渋柿は甘柿よりも糖度が高いといいます。物事は全てつながっていて影響を与え合っています。個々を良いもの悪いものに分けるのではなく、うまく組み合わせることでより、大きな効果を狙えるかもしれないと意識すると、違う景色が見えてきます。(精神保健福祉士)