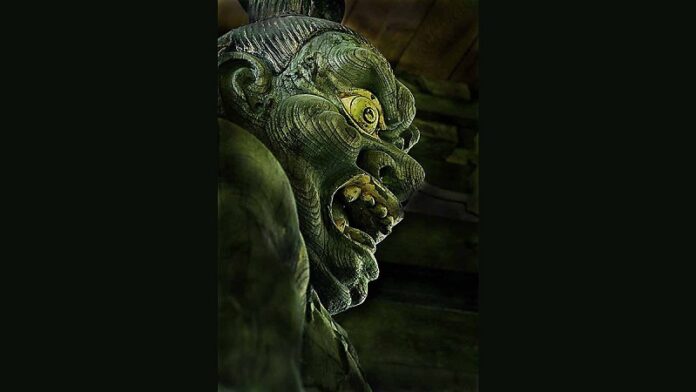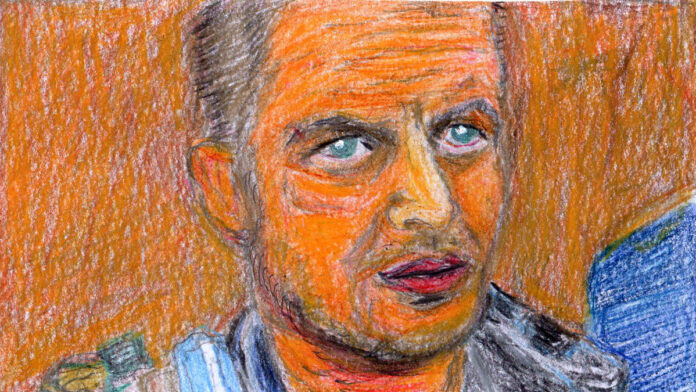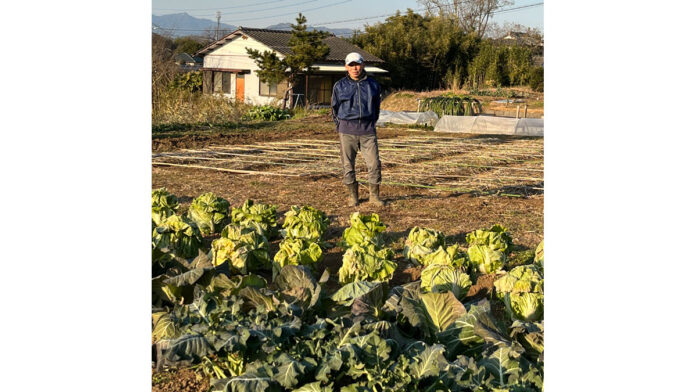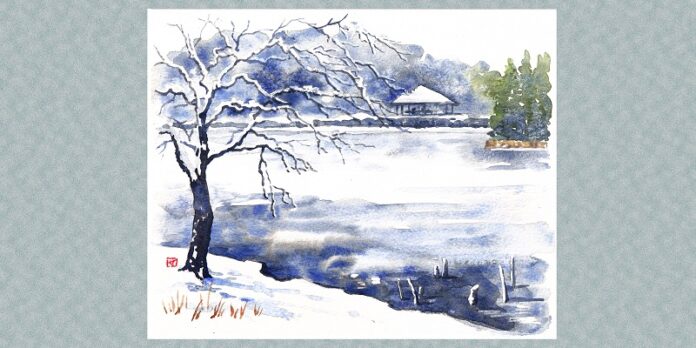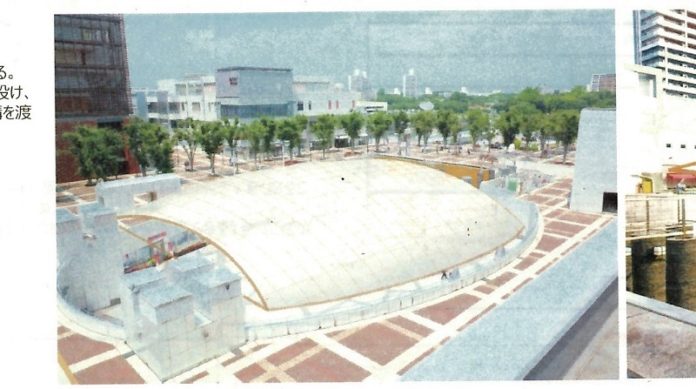【コラム・浅井和幸】気分が落ち込んでくると感謝することなどなくなってきます。感謝するどころか、すべてが悪循環で、良いことが起こらないし、今までも良いことなんてなかったと感じるようになります。こんなに頑張っているのに、どうして自分ばっかり運が悪いのだろうかと考えるようになるものです。
過去に嫌なことばかり起こっているのだから、これからも悪いことばかり起こるだろうと予測をしてしまうのは仕方のないことでしょう。0か100かの考えを持つと、過去に嫌なことが一つでもあれば、今まですべての経験・人間関係は嫌なことばかりだったと自分に言い聞かせるように愚痴をこぼし、良いことなど一つもなかったと思い込むことでしょう。
物事は卵が先か、鳥が先かの判断が難しいことがあります。楽しいから笑うのか、笑うから楽しいのか。実際に笑顔をつくると気持ちが軽くなったり、けげんな表情をつくると集中力が上がったりということもあるようです。
さて、運が良いから感謝するのか、感謝するから運が良いのかも難しい問題ですね。運というものはよく分からないものなので、人力で変化させることは出来るものではないのでしょう。ですが、感謝するのは自分自身の考え方とか捉え方なので、繰り返し練習をすれば自然と感謝できるようになっていきます。
感謝とはありがたいと思うことやそう思ったことを相手に伝えたりすることです。うれしい、美しい、楽しい、おいしい、良い香り、良い手触り、好きな音楽―などを感じて喜ぶことです。そのものに感謝してもよいし、それをもたらしてくれたものや人に感謝を伝えてもよいでしょう。
歯が痛いと歯医者の看板が見つかりやすいように、運が良いと思っていると、ポジティブな物事を見つけやすくなるものです。運が悪いと思っていると悪いことに敏感になり、運が良いと思っていると良いことに敏感になります。
そして、感謝の気持ちを表してくれる人に、人はもっと協力をして喜んでもらえるようなことをしたくなるものです。ネガティブな気持ちをぶつけてくる人には、ネガティブな気持ちを返したくなります。
感謝の気持ちを伝えよう
人を傷つけたり攻撃したりすると、攻撃が返ってきやすい状況をつくり出します。感謝や優しさを伝えることで、自分にも感謝や優しさが返されやすくなります。攻撃も感謝も、巡り巡って忘れたときに、返ってくることもあるでしょう。それが良い運、悪い運の正体なのかもしれません。
自分が好きな人に、尊敬できる人に、出来るだけ感謝の気持ちを伝えるようにしてください。自分を楽しませてくれるものに、感謝の気持ちを向けるようにしてみてください。きっと良い運が巡ってくるようになります。そして、その運に気づきやすくなり、その運を生かせる人間になれるでしょう。(精神保健福祉士)