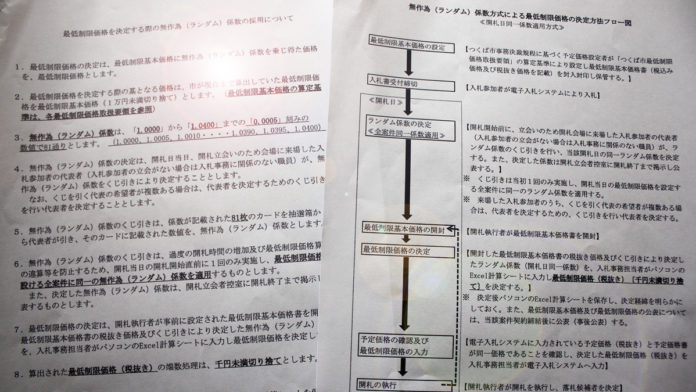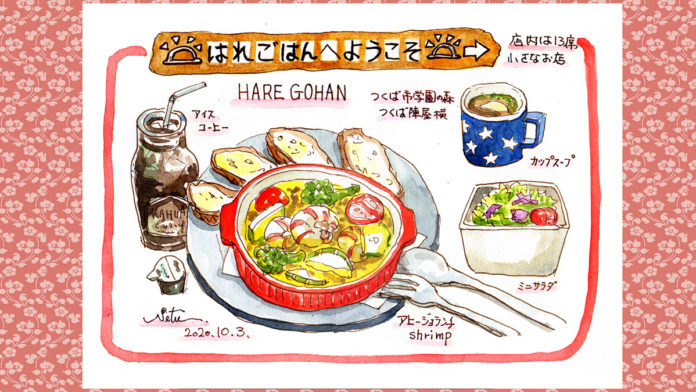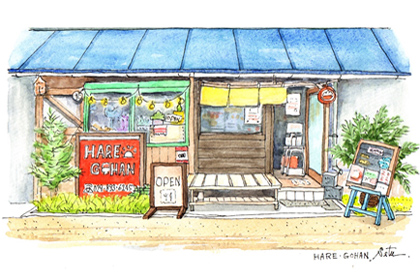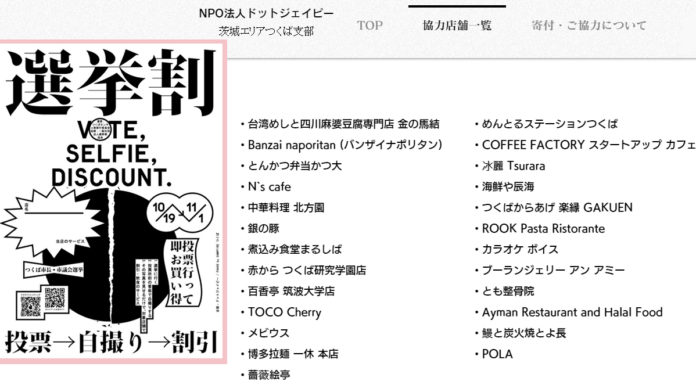【鈴木宏子】任期満了に伴ってつくば市長選と同日の18日告示された同市議選(定数28人)には、定数より13人多い41人が立候補を届け出た。有権者数は18万7565人(17日現在)
内訳は現職が23人、新人が17人、元職が1人。政党別は自民11人、公明3人、共産3人、市民ネット4人、新社会1人、諸派1人、無所属18人。男女別は男性26人、女性15人。現職5人が引退する。
▷つくば市議選立候補者一覧 届け出順(氏名・敬称略、年齢、職業、政党・政治団体、現職・新人・元職の別・過去の当選回数)

五頭 泰誠(ごとう・やすまさ)52 つくば市産業育成協議会代表理事 自現②
【略歴】栃木県立小山高校卒。TOKYO自民党政経塾13期生。つくば秀英高校PTA会長。境町出身。吉瀬在住。

高野 文男(たかの・ふみお)57 損保代理店 無現①
【略歴】藤代高校卒。元牛久茎崎ライオンズクラブ会長。元県倫理法人会副事務長。つくば中央倫理法人会相談役。つくば市出身。上岩崎在住。

浜中 勝美(はまなか・かつみ)67 政党役員 公現③
【略歴】中央大学卒。党茨城第6支部副総支部長。つくば市出身。上郷在住。

鶴田真子美(つるた・まこみ)55 動物愛護団体理事長 無新
【略歴】東京外語大学大学院修了。武蔵野音楽大学講師。NHKイタリア語会話講師。動物愛護団体「認定NPO法人CAPIN」理事長。神戸市出身。二の宮在住。

仲村 健(なかむら・けん)38 大学院生 無新
【略歴】筑波大学大学院システム情報工学研究科修了。元NTT東日本社員。元筑波大学職員。筑波大学大学院博士後期課程。埼玉県所沢市出身。研究学園在住。

飯岡 宏之(いいおか・ひろゆき)68 会社員 無元⑤
【略歴】日本大学理工学部卒。元アイ・エヌ・エー筑波研究所勤務。飯岡建設営業。市こども会育成連合会会長。つくば市出身、上野在住。

加藤 純子(かとう・じゅんこ)72 無職 無新
【略歴】元婚活支援事業「ハッピーサークル」代表。元中高年男女の親睦支援事業「ゆうゆうクラブ」代表。小田自治会会長。つくば市出身。小田在住。

鈴木富士雄(すずき・ふじお)72 農業 自現⑥
【略歴】下妻一高卒。元市議会議長。全国芝生協会会長。土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会筆頭副会長。つくば芝生事業協同組合顧問。つくば市出身。寺具在住。

皆川 幸枝(みながわ・ゆきえ)49 市議 市民ネット現②
【略歴】山形大学人文学部卒。元ソフトウエア開発会社勤務。元生活クラブ生協茨城理事。山形県南陽市出身。高崎在住。

山中 真弓(やまなか・まゆみ)42 党市委員 共現①
【略歴】茨城大学農学部卒、東京農工大学大学院連合農学研究科修了。元ツムラ勤務。現共産党つくば市委員会委員。栃木県市貝町出身。並木在住。

川久保皆実(かわくぼ・みなみ)34 弁護士 無新
【略歴】東京大学大学院法学政治学研究科修了。鳥飼総合法律事務所勤務。IT会社「リージット」代表取締役。IT会社「シンプルウェイ」取締役。つくば市出身。竹園在住

長塚 俊宏(ながつか・たかひろ)58 会社社長 自現①
【略歴】茨城高校卒。元土浦関東商事社長。県環境保全協会副理事長。学園関東サービス社長。つくば市出身。谷田部在住。

小村 政文(こむら・まさふみ)26 勝手につくば大使 無新
【略歴】筑波大学生物資源学類卒。情報サービス業「勝手につくば大使」。北海道網走市出身。花島新田在住。

川村 直子(かわむら・なおこ)48 市民ネット運営委員 市民ネット新
【略歴】日本福祉大学社会福祉学部卒。元日本聖公会名古屋学生青年センター主事。新潟市出身。花園在住。

藤岡 輝子(ふじおかてるこ)49 中国語通訳 自新
【略歴】水海道一高、中国・南京大学卒。元常総市議2期。ヤギ出張レンタル会社「山羊印本舗」経営。農産物直売所「七福交換の郷」経営。常総市出身。手代木在住

山本 美和(やまもと・みわ)50 政党役員 公現③
【略歴】創価大学卒。元松代小父母と教師の会会長。元手代木中PTA会長。元土浦一高PTA会長。市議会副議長。つくば中央ライオンズクラブむすび支部会長。東京都出身。松代在住。

神谷 大蔵(かみや・だいぞう)47 会社役員 自現②
【略歴】霞ケ浦高校卒。元つくば青年会議所理事長。市議会議長。つくば観光コンベンション協会副会長。つくばフェスティバル実行委員長。つくば市出身。沼田在住。

中村 重雄(なかむら・しげお)50 自営業 無新
【略歴】東洋大牛久高校卒。中村米穀店社長。元市消防団谷田部第一分団長。元谷田部中おやじの会会長。市商工会理事。内町評議委員会委員長。つくば市出身。谷田部在住。

木村 修寿(きむら・しゅうじ)66 元つくば市職員 無現②
【略歴】土浦日大高校卒。元谷田部町職員。元つくば市職員。市島名地区体育協会会長。市島名地区まちづくり協議会副会長。保護司。つくば市出身。島名在住。

小野 泰宏(おの・やすひろ)60 政党役員 公現⑤
【略歴】中央大学経済学部卒。元大曽根小PTA会長。元大穂中PTA会長。党つくば支部長。党茨城第6総支部長。くすのき会会長。常総市出身。花畑在住。

木村 清隆(きむら・きよたか)56 市議 無現②
【略歴】日本大学卒。元連合茨城副会長。元産別労組JAM茨城副委員長。国際IC日本協会理事。市立豊里中学校評議員。つくば市出身。上郷在住。

久保谷孝夫(くぼや・たかお)69 会社役員 自現⑨
【略歴】東洋大牛久高校卒。元久保谷商事役員。ミユキコーポレーション役員。つくば市出身。前野在住。

木村 芳美(きむら・よしみ)57 行政書士 無新
【略歴】吉沼中卒。石下高校中退。つくば市出身。西高野在住。

須藤 光明(すどう・みつあき)78 市議 自現⑤
【略歴】上郷高校卒。元市経済部長・企画部長。県つくば芝振興協議会会長。インプルーブファーム代表取締役。つくば市出身。吉沼在住。

黒田 健祐(くろだ・けんすけ)39 市議 自現②
【略歴】学習院大学文学部哲学科卒。元会社員。つくば青年会議所理事。つくば市出身。東平塚在住。

野友 翔太(のとも・しょうた)26 自営業 無新
【略歴】早稲田大学社会科学部卒。元会社員。システム企画・運用支援の自営業。稲敷市出身。研究学園在住。

塚本 洋二(つかもと・ようじ)48 会社顧問 自現③
【略歴】県立土浦産業技術専門学院卒。元大曽根タクシー整備管理者。信輝インターナショナル顧問。社会福祉法人博愛会理事。つくば市出身。花畑在住。

滝口 隆一(たきぐち・りゅういち)72 党市副委員長 共現⑨
【略歴】法政大学社会学部卒。元土浦信用金庫職員。元民青同盟茨城南部地区委員長。土浦市出身。栄在住。

宮本 達也(みやもと・たつや)48 宮本ファーム代表 無新
【略歴】谷田部高校卒。元市農業委員。つくば市谷田部農協理事。県猟友会谷田部支部事務局。つくば市出身、飯田在住。

小森谷佐弥香(こもりや・さやか)46 薬剤師 市民ネット現①
【略歴】富山医科薬科大学薬学部卒。元製薬会社MR勤務。薬剤師。前橋市出身。研究学園在住。

小久保貴史(こくぼ・たかし)47 農業生産法人代表 自現②
【略歴】八ケ岳中央農業実践大学校卒。元・小久保造園土木社長。元つくば青年会議所理事長。元筑波東中学校PTA会長。農業生産法人筑波農場代表。つくば市出身。小田在住。

ヘイズ ジョン 57 会社経営 無現③
【略歴】カナダ・リジャイナ大学卒、音楽教育学学士取得。元英会話教師。イマジネリク代表取締役。カナダ出身。二の宮在住。

浅野英公子(あさの・えくこ)59 市民ネット運営委員 市民ネット新
【略歴】東京外国語大学卒。元学習塾経営。元高校講師。元オーガニック検査員。富山市出身。吾妻在住。

下神納木加枝(しもこうのき・かえ)38 理学療法士 自新
【略歴】四條畷(しじょうなわて)学園短大卒。一般の病院で7年、動物病院で7年勤務。県理学療法士会理事。NPO法人HA-HA-HA理事。大阪府堺市出身。みどりの東在住

中山 道世(なかやま・みちよ)34 飲食店経営 無新
【略歴】藤代紫水高校卒。JTBトラベルカレッジ中退。中国上海で飲食店勤務。カクテル世界大会優勝。飲食店経営。つくば市出身。二の宮在住。

福田 恵(ふくだ・めぐみ)35 会社社長 政治団体「スーパークレイジー君」新
【略歴】東放学園高等専修学校卒。エステサロン「美肌コンシェルジュ」代表取締役。経営コンサルタント。阿見町出身。赤塚在住。

伊藤 栄(いとう・さかえ)56 行政書士 無新
【略歴】湘南高校卒。元陸上自衛隊勤務。行政書士伊藤栄事務所代表。山形県東根市出身。研究学園在住。

橋本 佳子(はしもと・けいこ)66 党県委員 共現⑤
【略歴】聖徳学園短大保育科卒。共産党茨城県委員。土浦市出身。自由ケ丘在住。

金子 和雄(かねこ・かずお)76 党県委員長 新社会 現⑨
【略歴】NHK学園卒。元竹内猛社会党衆院議員秘書。元県立土浦養護学校後援会会長。群馬県高崎市出身。下広岡在住。

塩田 尚(しおた・ひさし)70 行政書士 無現⑧
【略歴】神奈川大学法学部卒。行政書士。愛媛県四国中央市出身。真瀬在住。

田中 美華(たなか・みか)38 販売員 無新
【略歴】立正大学法学部卒。元飲食店店員。販売員。常総市出身。島名在住。
(18日午前11時現在)