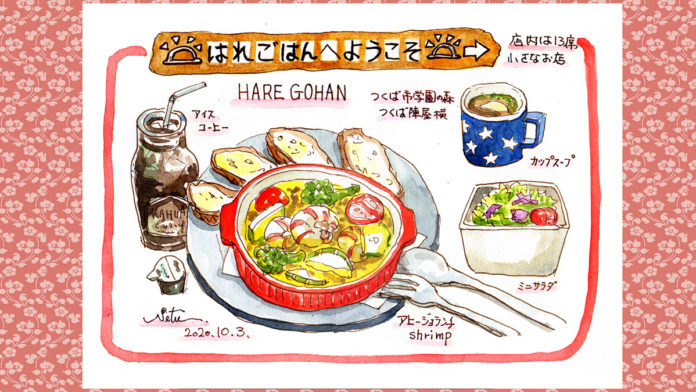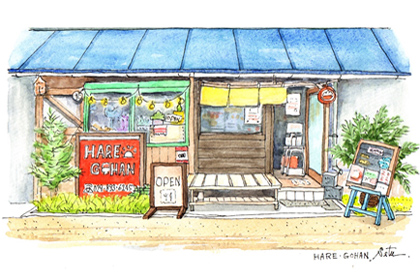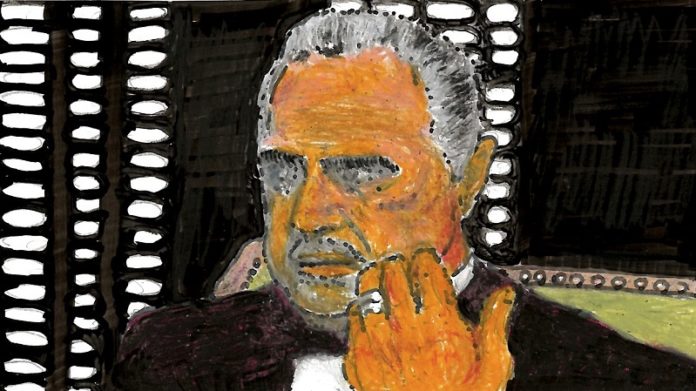【コラム・玉置晋】10月3日、防災推進国民大会(通称:ぼうさいこくたい)というイベントに参加しました。名前の通り、一般~専門家向けの防災を学ぶことができるイベントです。
僕は太陽フレアなどで、将来、社会インフラなどに甚大な影響を与える可能性がある宇宙天気災害に興味があって、大学院で研究をしています。そのため、地震や水害といった僕らがすでに被害を被っている災害の研究動向や社会の対応状況を勉強しておきたいと考えています。そこで、大学の先生から、このイベントをご紹介いただいたというわけです。
様々な講演を聴いて気になったのは、自分で守る「自助」、みんなで守る「共助」、国や自治体による行動「公助」の3つの「助」が必要だということを、皆さん述べておられた点です。
自助や共助は、僕ら自身のアクションになるけど、イザというときの備えができているかといえばちょっと自信がない。本コラムでは宇宙天気防災研究者という肩書になっていますが、本人の防災意識を問われると、ちょっとつらい。
本イベントの参加レポートは大学院の授業単位にも考慮されるそうなので、ちょっと本気で聴いています! 今年はオンラインで開催されており、発表の動画(https://bosai-kokutai.com/)はアーカイブされています。みなさんもよかったらいかが?
宇宙天気はどのような影響を及ぼすか?
最近の災害関係のトピックスがもう一つ。宇宙天気防災関係です。10月7日、情報通信研究機構(NICT)さんが「太陽フレアなどの宇宙天気による社会への影響と評価~宇宙天気は日本にどの様な影響を及ぼすか~」と題するプレスリリース(https://www.nict.go.jp/press/2020/10/07-1.html)を出されましたので、注目です。
ポイントは、
- 「科学提言のための宇宙天気現象の社会への影響評価」を作成・発表
- 大規模な太陽フレアが発生しても、地上での「健康」への影響はほぼないことを確認
- 各事業者が適切な対応策を取ることで宇宙天気現象に対して社会的な強靭(きょうじん)性が増すことを期待
―とのことです。
太陽活動が主な源である宇宙天気による災害はまれであるものの、一度発生すると広範囲で大規模に影響を与えることが知られています。でも、どれくらいの規模の現象がどれくらいの頻度で発生するかなど、社会への影響の定量的な議論は十分ではありません。
プレスリリースにも書かれていますが、この状況は「宇宙天気予報の警報を発信しても、そのために備えをどのようにしたよいのかについての指針がなく、その結果、ユーザは過剰な心配あるいは無関心に陥っていた」という現状につながっています。
ポストコロナ時代においては、宇宙天気の影響に対策が必要な自動運転やドローン物流が注目を浴びてくるでしょうし、数万機の小型衛星による通信網の構築はもう間近です。
「各事業者が適切な対応を取ること」で、災害レベルの宇宙天気現象に対して、正しい知識が普及し、社会的な強靭性が増すと期待されていますので、よろしくお願いします。つまり「自助」「共助」でございます。(宇宙天気防災研究者)