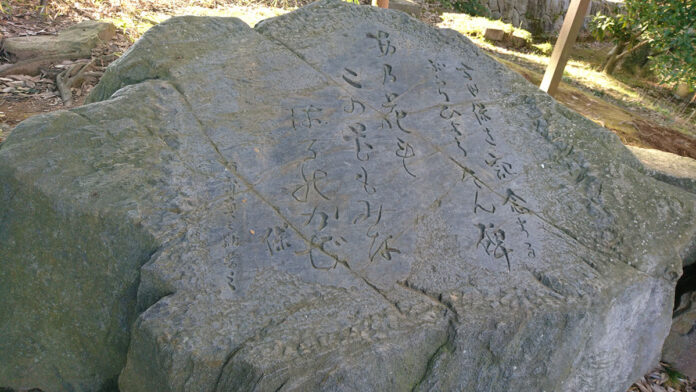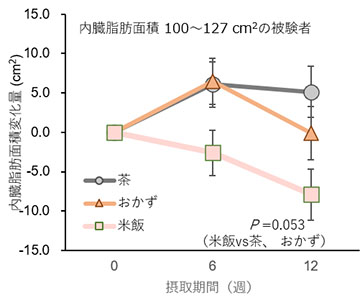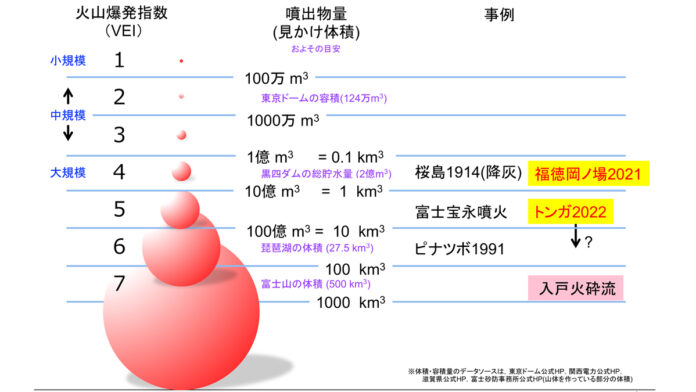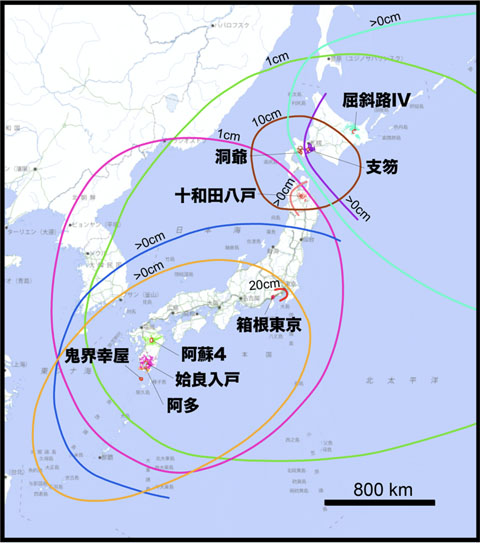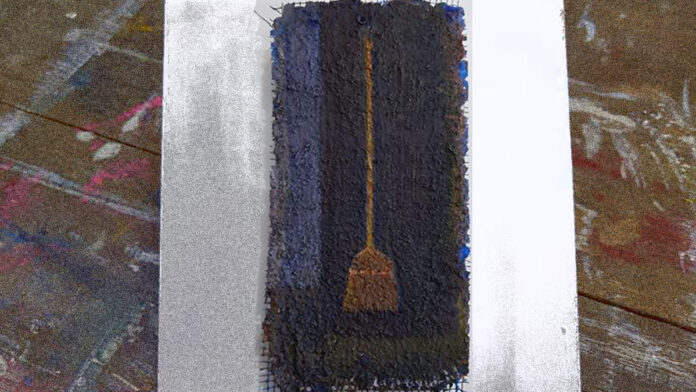土浦カレーフェスティバルで6年連続優勝を果たし、殿堂入りしている、レストラン中台(土浦市桜町)のレトルトカレー「つちうらカレー物語」5品が「カレーオブザイヤー2022」特別賞を受賞した。昨年発売された「弓豚スペアリブのスープカレー」「幻の飯村牛キーマカレー」「弓豚のプレミアムカレー」「土浦ホワイトレンコンカレー」「クリーミートマトカレー」の5品だ。
カレーオブザイヤー2022は、カレー総合研究所(井上岳久社長、東京都渋谷区)が運営する「カレー大學」が、革新的、画期的だがまだ世間に知られていないカレーに、1月22日のカレーの日に合わせて賞を授与しているもので、2017年から毎年名品カレーを選出している。
オーナーシェフの中台義浩さんによると、新商品のレトルトカレー5品は、佃煮加工の小松屋食品(土浦市大和町)の煮釜の1つをカレー加工専用にしてもらい製造した自信作だ。レシピだけを監修したのではなく、シェフ自身が味を確認し調整しながら作っているこだわりのレトルトカレーだという。
「コロナ禍の一昨年はお客さんが来なくなり従業員も呼べない状況だった。仕事がしたくてもできず、レトルトの新商品を作ろうと思い開発した。特に『幻の飯村牛キーマカレー』と『弓豚のスープカレー』は完璧な出来上がり。ぜひ食べてみてほしい」と話す。
材料にもこだわった。飯村牛や弓豚といった希少な銘柄肉のほか、野菜はなるべく地元産のものを使用。土浦、阿見などの契約農家と提携し新鮮なものを仕入れている。土浦特産のレンコンを使用しているのも特徴だ。
レストラン中台ではこれまで「幻の飯村牛ビーフシチューカレー」と「幻の飯村牛牛すじカレー」を発売しており、レトルトカレーは新商品を加え全7種類となる。同店のほか、スーパーマーケット「カスミ」やJA直売所各店、オンラインでも購入することができる。

今年で創業83年目となる老舗。今後の目標は霞ケ浦のテナガエビを使用したカレーを開発することだという。「テナガエビはまだあまり注目を浴びておらず、地元の漁師さんからもっとテナガエビを売りたいという声を聞いている。土浦や阿見の名産カレーとして商品化できたら」と中台さん。また、アスリート向けにタンパク質を増やし、カロリー計算した「奇跡のKOカレー」の商品化も目指している。冷凍食品も開発中で、店の味を完全再現したカレーやハヤシライスを試作中だ。(田中めぐみ)

![P1040287 (2)[2305843009276968614]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/02/P1040287-22305843009276968614-1-696x391.jpg)





![ことばのおはなし 42[8921]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/02/911ce8cbdd7daabf2ada98e11e15a42b-696x392.jpg)
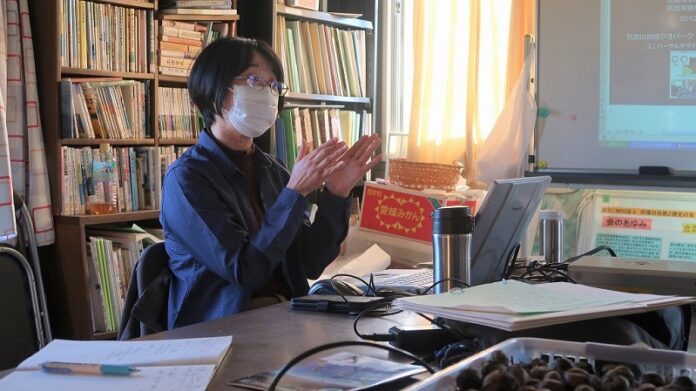

![雑記録 32[8900]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/01/7397587db3f3dec6a278dc6c25601a37-696x392.jpg)