【コラム・玉置晋】前回のコラム「宇宙天気キャスター」で僕は痛恨のミスを犯しました。宇宙人クラブ代表の福海由加里さんの名前の漢字を間違えてしまい、NEWSつくば編集室に修正依頼を出すという御迷惑をかけてしまいました。謹んでお詫び申し上げます。現在、責任をとって頭を丸めるという企画が進行しております。坊主頭は幼稚園生のころ以来なので、ドキドキワクワクです。
頭を丸めるに当たり、宇宙飛行士の方は宇宙での散髪をどうしているのだろうと疑問に思いました。だって無重力環境だと、切った髪がそこら中に散らばってしまいます(まさに散髪!)。万が一、宇宙飛行士の皆さんが誤って吸い込んでしまったら、大変なことになります。機械類に紛れ込んで、ショートでも起こしたらと考えると、散髪なんてしている場合ではないのではと思います。
調べてみたら、普通にバリカンで散髪している動画がたくさん出てきて動揺しました。どうやらバリカンが特別な構造で、掃除機のようなものが付いていて、髪の毛は吸引される仕組みのようです。
動画の多くは同僚の宇宙飛行士に刈ってもらっているものでしたが、中には自分で刈っている強者も(日本のベテラン宇宙飛行士の方)。想像するに、無重力環境で自らバリカンを入れて、散った髪を確実に吸引するのは、難易度が高いと思います。散髪の訓練もされているのでしょう。
宇宙で洗髪もしたい
国際宇宙ステーションにはお風呂もシャワーもありません。無重力環境で水を扱うのは非常に危険です。水が機械に付着して故障の原因になるだけでなく、顔面にへばりついて窒息する危険性もあります。でも日本人としては風呂に入りたいし、それが無理ならシャワーを浴びたい。散髪の後ならシャンプーもしたい。
1970年代~1980年代、宇宙を飛行したスカイラブ宇宙船にはシャワーがあって、宇宙飛行士の方は水泳用ゴーグルをつけ、鼻をクリップでつまみ、シャワーを浴びていました。溺れそうになった方もいたとか。宇宙でのシャワーは命がけであるようです。
現在、国際宇宙ステーションでは、タオルに石鹸を含ませた「衛生タオル」に、給湯器からのお湯を含ませて、頭や体を拭いているとのこと。宇宙でシャワーを浴びたいという欲求を満たすのは、大変なことのようです。(宇宙天気防災研究者)







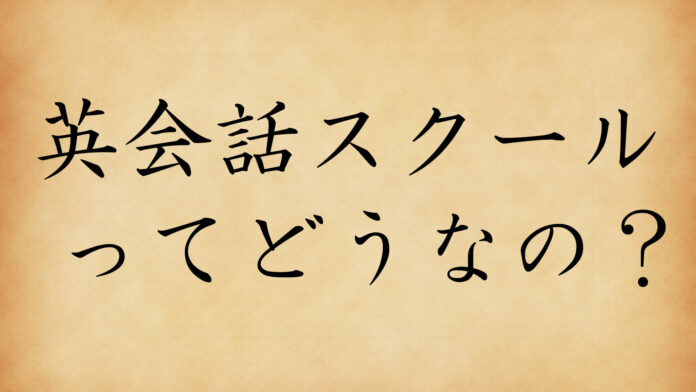



![9183882905242ef7bac5f723dc66cc23[1]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2020/02/9183882905242ef7bac5f723dc66cc231.jpg)
![川上美智子 15[6375]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/09/447f52b8f79d83b1fe4276dc671d84ec-696x391.jpg)

![斉藤裕之 94[6291]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/09/9c649e5e7869fb97b972e8a48b8036f0-696x392.jpg)
![田口哲郎 20[4511]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/07/cbc28d79db4c68e92f784ee5eb9ad4dd-696x391.jpg)






