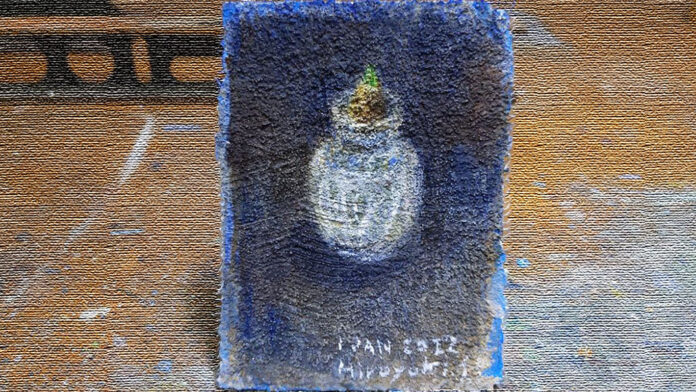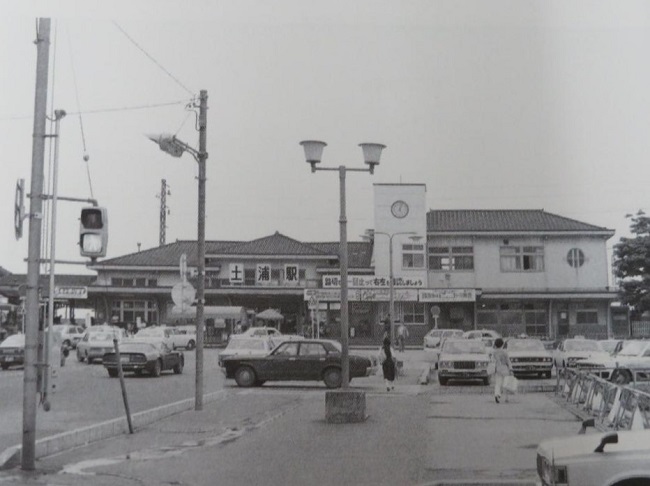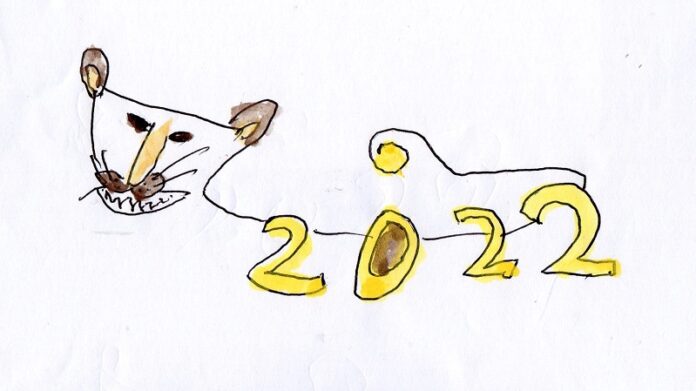【コラム・田口哲郎】
前略
初夏のころ、つくば市にある洞峰公園のプール棟前には薔薇(バラ)の花が溢(あふ)れます。ローズガーデンさながらの種類と本数です。この薔薇園を特に入場料を払わずに鑑賞できるのは、とてもありがたいと思います。色とりどり、鮮やかさなど、さまざま楽しめるのはもちろん、香りがとてもよいのです。あまり強くなく、かすかですが、ふわっと心地よく、非日常に連れていってくれるような匂い。デパートに売っている高級な香水を思わせます。
さて、私は夢中で写真を撮ったのですが、ある写真を見返して思わずつぶやきました。「こりゃ、イングリッシュだな」と。プリンセス・ミチコという品種が、プール棟のレンガ風外壁とガラス屋根を背景に濃いオレンジ色に咲きほこっています。
西洋の伝統を感じさせるレンガと近代を物語るガラスに薔薇とくれば、水戸偕楽園の好文亭に梅林といったおもむき。イングリッシュの本体もそばにありました。クィーン・エリザベス。「われらが女王陛下のために」と、どこかで聞いたことがある言葉が思い浮かぶほど、その薔薇は我こそ薔薇なりと言わんばかりに堂々と咲いていました。
クィーン・エリザベスで思い浮かんだ言葉は、シャーロック・ホームズのセリフだった気がします。19世紀、大英帝国華やかなりし時代の物語です。シャーロックは犯罪者を推理のすえ、いよいよ追いつめようと、相棒のワトスン君とベーカー街の部屋を飛び出すときにそう言います。そういえば、NHK BSでイギリスのグラナダテレビジョン制作の「シャーロック・ホームズの冒険」が絶賛再放送中です。
大西洋の島国と太平洋の島国の文化
主演は大手菓子メーカー、キャドバリー社の御曹司ジェレミー・ブレット。イギリス紳士を演じさせたら右に出る者はいないハマリ役です。テレビドラマを含めてシャーロック・ホームズ好きは、シャーロキアンと呼ばれて日本全国に大勢いるのはご存知の通り。ホームズが人気があるのは、推理小説としての面白さもさることながら、その背後にあるイギリス文化をぷんぷん匂わせているからでしょう。
思えば、イギリス文化は日本に絶えることなく入ってきますね。ザ・ビートルズをはじめとするロック・ポップスから、レ・ミゼラブルのようなミュージカル、シェイクスピア演劇、ブロンテ姉妹、ジェーン・オースティンの小説、モンティ・パイソン、ミスター・ビーンのようなコメディまで、数えればきりがないです。
慶應義塾の政治思想の講義で、イギリスは島国で、フランスのような大陸にある国より平和なので文化が熟成する、それは島国の日本も似ている、と聞いたことがあります。派手ではなくとも渋くて味のある文化が、洋の東西に位置する島国に蓄積しているのは愉快です。ヨーロッパ文明の波はますます押し寄せます。
今さらですが、英国から学ぶことは多いでしょう。そして日本もあちらに文化を大いに輸出するべきです。ごきげんよう。
草々(散歩好きの文明批評家)


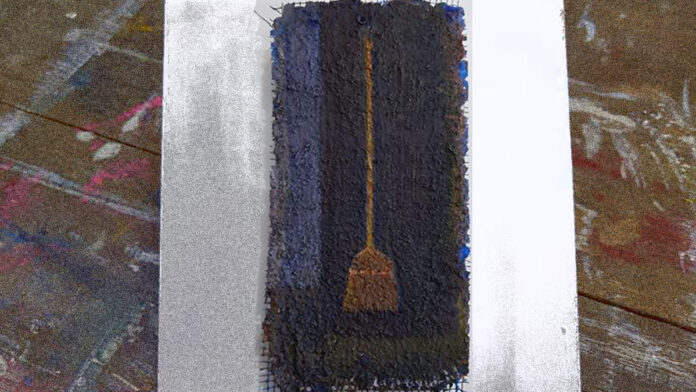



![くずかごの唄 101[8710]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/01/1a289ff6ecd168d97c7b739ab29b637b-696x392.jpg)
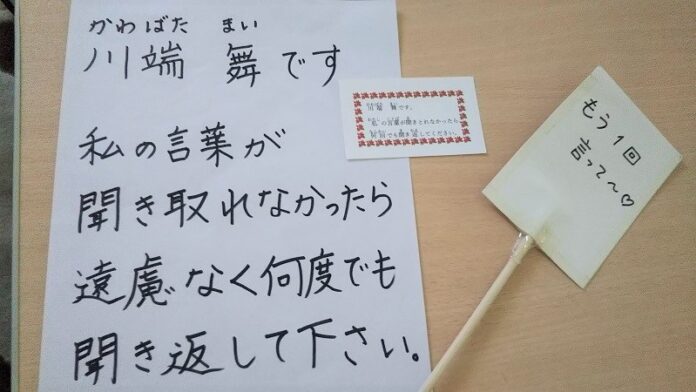
![川浪せつ子 43[8681]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/01/8e6d7d4134a1620502a3bb4fbea12bab-696x348.jpg)