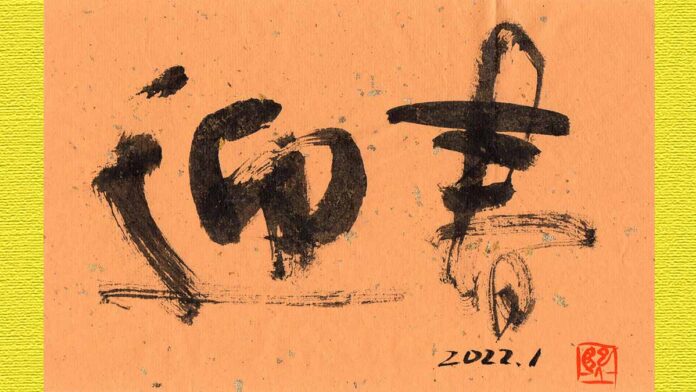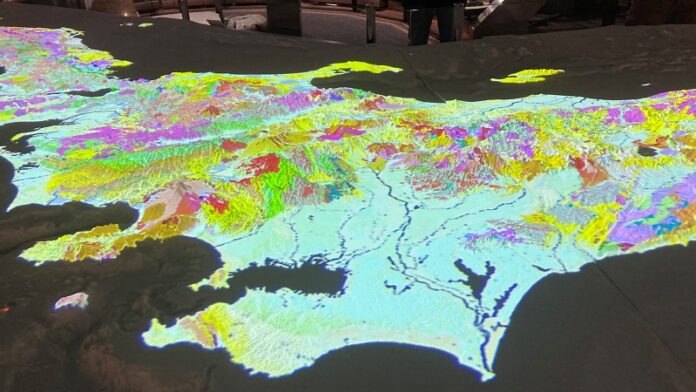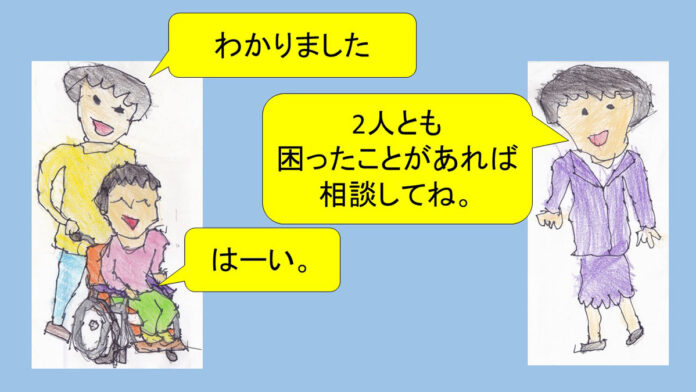【コラム・山口 絹記】外国語学習について、約半年間。やや長い連載になった。ここで書いた内容が少しでも誰かの役に立てていたら幸いである。
最後に、せっかくこういった場で語学学習について書く機会を得たのだから、純粋な営利目的ではなかなか書けないことについて書いて終わりにしようと思う。
最後の最後にこのようなことを書くのも気が引けるが、英語を習得する『利益』があるのか、ということについてだ。これに関してはいくつかの仮定を想定しなくてはならないだろう。
まずあなたが、義務教育や高等教育課程の途中ならば、悪いことは言わないから励んでおいた方がよい。ここでサボったツケは大きく、後で取り返すのは至難だ。もっと言えば、自分にとって必要になる瞬間というのは、学んでいた者にしかわからないことだってあるのだ。
問題は、学校教育を終えてから、自発的に英語を学ぶ場合である。例えば「英語ができると仕事に役に立つかも」というような漠然とした目的で学ぶ場合だ。
正直、厳しいと思う。無理やりやらされている者が、好きでやっている者にかなうことはまれだ。もしも他に身に着けたいと思っていることがあるのならば、素直にそちらに力を注いだ方が、毎日が豊かになるのではないだろうか。
英語による読み書きに限るならば、機械翻訳のような様々なツールを活用すれば、最低限の知識でかなりのことができる。セキュリティなどの問題で外部開発されたものを使用できない環境でない限りは、こういったものの使い方を熟知する方が効率が良い。
「まだ見ぬ景色に対する予感」
そう、『利益』を考えるならば『効率』を考えなくてはならないのだ。そして、語学に限った話ではないが、新しいスキルの習得と『効率』という考え方は非常に相性が悪い。
語学というのは、『利益』の名のもとに無理やり習得できるほど、楽なものではないと私は感じている。漠然と英語ができるようになりたいと思っている消費者は、利益を得るより利益にされる可能性のほうがずっと高い。
つまるところ、『利益』ではないのだ。連載の中でも書いたが、大切なのは『他者には理解されない類の情熱』だ。
世の中には、なんだかよくわからないけれど、山登りが好き、という人が結構いる。山登りというのは、基本的に危険な行為だ。筑波山だって遭難することはある。それでも、自分の足で登った者にしか見ることのできない景色というのがある。
語学だって同じだ。身につけた者にしか見えない景色がある。機械翻訳という、ロープウェイみたく便利なものもあるが、そういったものを使っては見えない景色。あなたの中に宿っている情熱には、そういった、まだ見ぬ景色に対する予感のようなものがあるのではないだろうか。
私から言えることは、「うん、そういう景色、あるね」ということだけだ。
ままならない世の中のまま2022年が始まってしまったが、己の信ずるところに従って、まだ見ぬ景色を目指して山道を登り始めてはいかがだろうか。無理にとは、言わない。(言語研究者)

![ことばのおはなし 41[8388]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/01/962cd0db2958c7ba4e3d7569ed2696d7-696x392.jpg)
![horikoshi[1]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2020/02/horikoshi1.jpg)
![瀧田薫 31[8371]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/01/f390f5b85695cf75775c2318b60c2890-696x392.jpg)