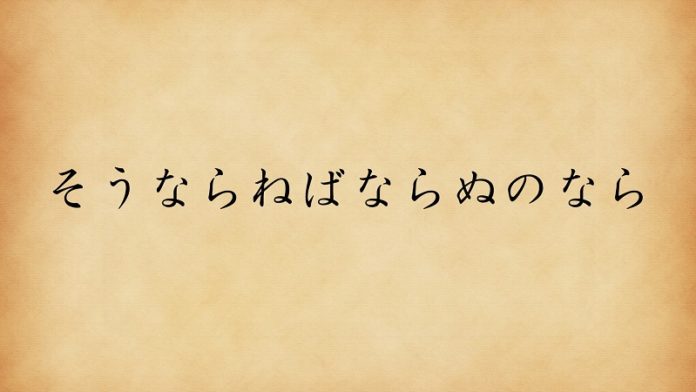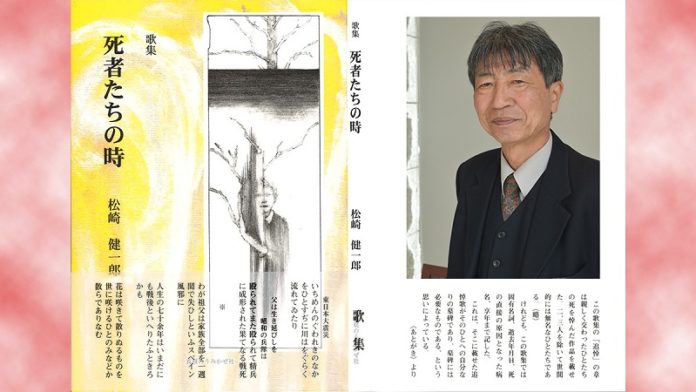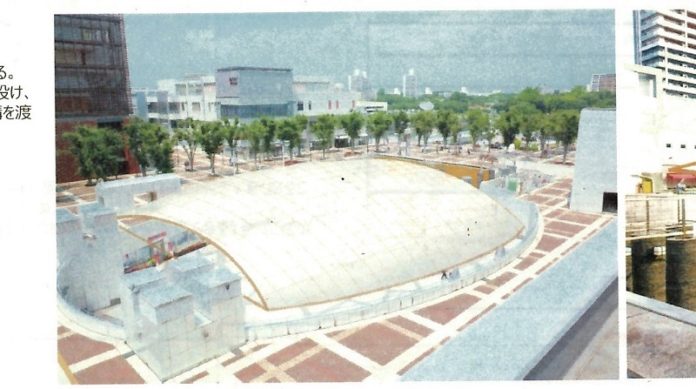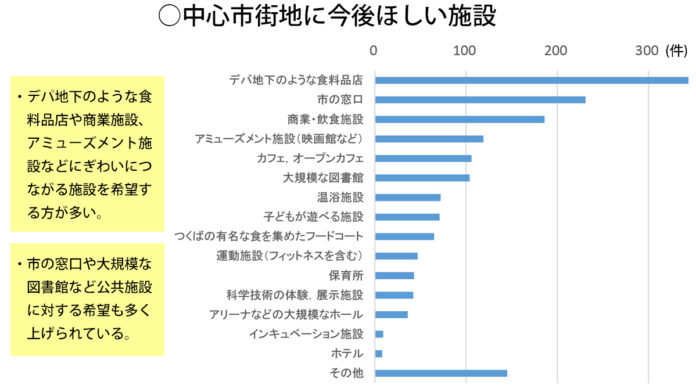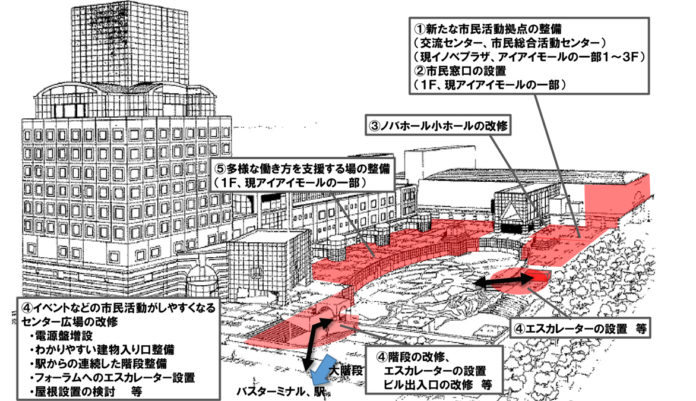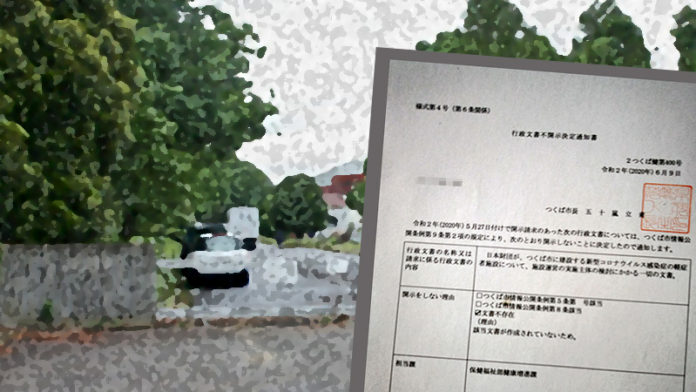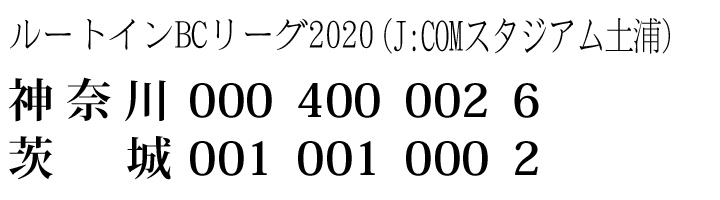【コラム・山口絹記】血管造影検査から2日後。
眠気でリハビリに集中できない。夜通し本を音読していたせいで寝不足である。2週間後に開頭手術が決まったことで、私は焦りを感じていた。というのも、手術で命を落とす可能性は低いらしいが、脳の出血している部分を摘出するため、失語や右半身の機能障害が再発する恐れがあるからだ。
明日手術です、と言われれば諦めがつくが、2週間時間があると言われると、いろいろやっておきたいと思ってしまうのが人情というものである。朝食後からノートに色々書いては悶々としていると、母からメールが届いた。「色々と考えておこうと思っているとおもいますが、窓辺で陽の光を浴びながら考えてごらん」。
やっと点滴も外れたため、メールを読み返しながら、病棟の廊下を歩いて日の差し込むベンチに座った。外はきっと寒いのだろうが、ガラス越しの日差しは優しく気持ちよかった。
欲をかけばすべて中途半端になるのは目に見えている。想定する状況は、術後2年間、失語症状と右腕の失行が続くこととしよう。それから、自分の口から今の状況を伝えたいと思う人を選定し、術前にリハビリも兼ねて会って話しておくこと。娘のために、できる限り本の朗読を録音しておくこと。自身のためのリハビリ教材の選定と作成、それを妻に託すこと。
手術は10時間近くかかることがあるというから、その間待ちぼうけになるであろう妻と母のレクリエーションも考えねばなるまい。せっかくだから長めの落語でも録音しようか。こんなときだから古典の「死神」なんてどうだろう。すんなり考えがまとまった。なるほど、陽の光というのは大切らしい。
数ヶ国語のAVM単語帳を暗記
その後の2週間はあっという間だった。
入院中の3日間は毎日日本語の文章を7時間、英語の文章を1時間音読、消灯後を含めた4時間は術後のリハビリ教材の作成にあてた。この3日間だけでかなりスムーズな発話能力を取り戻した。日記の誤字脱字もなくなった。
連絡をとった学生時代の友人は「今から行くよ!」と駆けつけてくれた。一児の母となった幼馴染(おさななじみ)は丸一日つくばに滞在してくれた。一時退院中は娘を連れて本屋に行き、子ども用の辞書を買い、一緒に辞書をひきながら絵本を読んだ。私がことばを話せなくなると、娘が暗記してしまったお気に入りの絵本を読んでくれた。日中は同僚や上司が家に遊びに来てくれて、家族が寝静まると、娘のための朗読と、妻と母のための落語を練習し、オンライン英会話で医療従事者と病気について話し合った。
再入院前日には父がふらりと家にやってきた。散々関係ない話をして、帰り際に父は言った。「血管の奇形って言われると、製造元としては責任を感じるんだが。まぁ返品できるもんでもないしな」。
そうなのだ、有りものでどうにかやっていくしかないのだ。
手術前日、再入院した病室では、数カ国語で作成したAVM(脳動静脈奇形)に関する単語帳を暗記しながら眠りについた。明日は久々にゆっくり眠ることができる。-次回に続く-(言語研究者)