【コラム・川上美智子】茨城県の教育委員は、それぞれ年に6校ほど県内小中高等学校の視察を行っています。つくば市の「みらいのもり保育園」の園長になってからは、できるだけつくば市内の学校を回るようにしています。その番外編として、4月中旬、以前から名前だけは耳にしていた「つくばインターナショナルスクール(TIS)」を見学する機会を得ました。
何の予備知識も無く訪れた学校は、まるで軽井沢の森の中に迷い込んだかのような自然あふれる中にあり、その建物は、アメリカ風の緑色を基調にした木造のおしゃれなものでした。
シェイニー・クロフォード校長先生の大歓迎を受けて、全ての学年の授業を見学することができました。TISには、3歳から18歳までの子どもたち、285名が在籍し、開設12年で生徒数が飛躍的に伸びたと言います。
ダイバーシティー(多様性)の言葉がピッタリの、様々な国の子どもたちがキャンパスに学び、親の国籍は25カ国に上ります。両親が日本人の家庭、片親が日本人の家庭、両親が外国人の家庭がほぼ3分の1ずつで、授業はすべて英語で行われていました。
また、3歳から12歳までを対象とするPYP(プライマリー・イヤーズ・プログラム)、11歳から16歳を対象とするMYP(ミドル・イヤーズ・プログラム)、16歳から19歳までを対象とするDP(ディプロマ・プログラム)のすべての国際バカロレア(大学入学資格・教育プログラム)が取得できるのは、県内では本校1校に限られるため、東京圏から通学する子もいるなど、大変人気があるとのことでした。
ユニークな国際人材育成カリキュラム
そもそも、国際バカロレアの目標は、①子どもたちが世界の複雑さを理解し、それに対処できるよう育成する ②未来に対し責任ある行動をとるための態度、およびスキルを身につけさせる ③国際的に通用する資格を付与し、大学進学へのルートを確保する―ことにあり、探求する人、知識のある人、考える人、コミュニケーションができる人、信念をもつ人、心を開く人、思いやりのある人、挑戦する人、バランスのとれた人、振り返りができる人を育成するとしています。
国際社会で活躍する人材育成のための教育カリキュラムはユニークで、例えばPYPでは、言語、社会、算数、芸術、理科、体育の6教科があり、「私たちは誰なのか、どのような時代と場所にいるのか、どのように自分を表現するか、世界の仕組みは自分たちをどう組織しているのか、地球を共有するとはどういうことか」などを教科横断的に学んで行きます。
私たちや人類にとっての普遍性や実社会の課題を、自分で考える、調べる、表現する、他人の意見も受容し共感する、解決法を探るなど、コミュニケーションを交わしながら学ぶアクティブ・ラーニングが基本のスタイルになっていて、TISでも、クロフォード校長先生の専門であるSDGs(持続可能な開発目標)のテーマで、どの学年の授業もアクティブに展開されていました。
今、日本は国際スタンダードなこの学習スタイルをようやくスタートさせたところです。小学校2年生の女の子の「私たちの体にはもうマイクロプラスティックが入り込んでいるの」の言葉を胸に刻み、学びの多い視察先を後にしました。(みらいのもり保育園園長、茨城キリスト教大学名誉教授)










![斉藤裕之86[3486]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/05/a92033595b7af0c7b36323d80b9bb3cb-696x392.jpg)









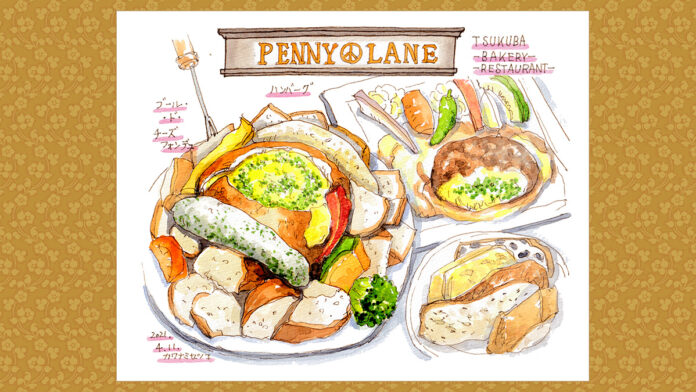


![映画探偵団 43[3344]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/05/73e5eb9d693274e658f8361f5e8373b5-696x391.jpg)



