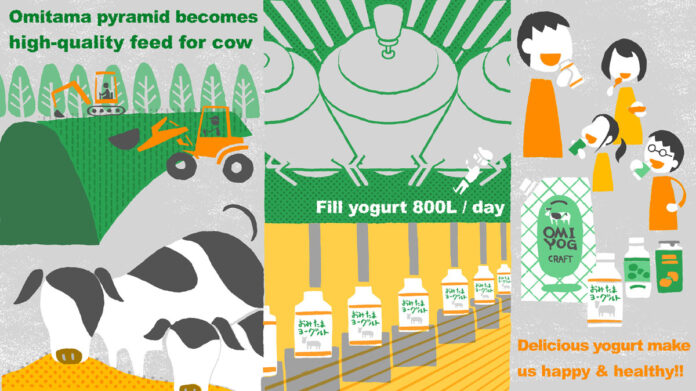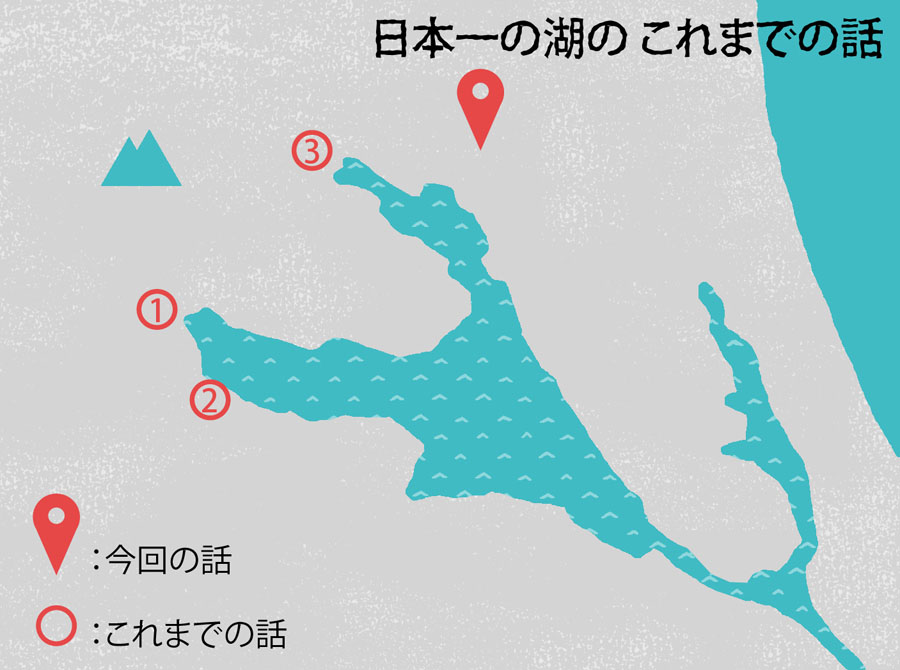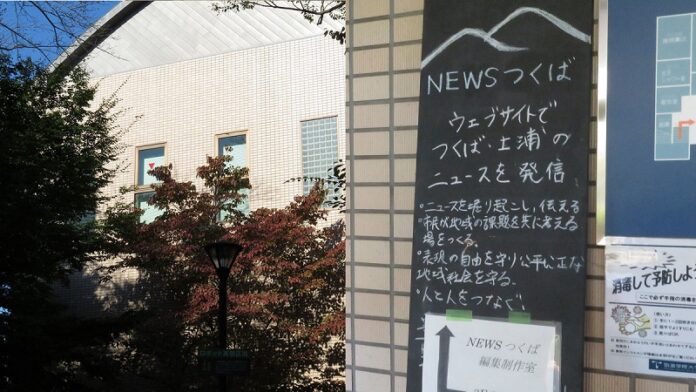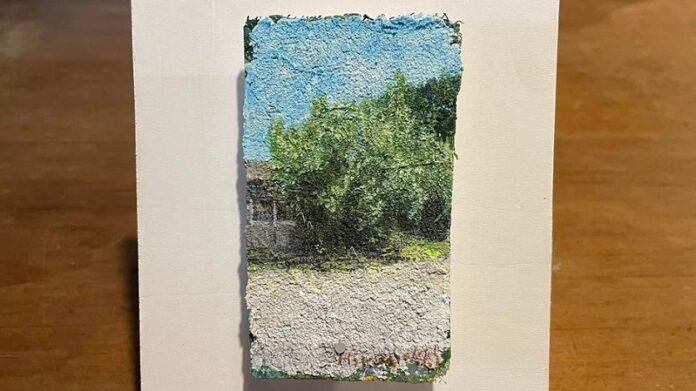【コラム・先﨑千尋】「賛否交錯の中 安倍氏国葬。分断の責任、岸田首相に」。これは、安倍さんの国葬儀の翌日の「東京新聞」1面の見出しだ。
同じ紙面に、豊田洋一・論説主幹が「国葬とは国家として故人を葬送する儀式である。国家とは、領土や居住する国民、政治権力で構成され、国家意思を決定するのは主権の存する国民だ。国民が同意しない国葬はありえない。(中略)報道各社の世論調査によると、この国葬には半数以上が反対する。故人を静かに悼むはずが、首相の浅慮により、国民を分断し、儀式から静謐(せいひつ)を奪った。その責任は首相にある」と、厳しく岸田首相を糾弾する。
自民党の二階俊博元幹事長は「黙って手を合わせて見送ってあげたらいい。議論があっても控えるべきだ」と語っていたが、その後もメディアは黙ることなく、国葬の是非について多くの識者の声を載せている。
その1人、評論家の佐高信さんは毎日新聞の記者と国葬当日に現場を歩き、ルポしている。「閣議決定だけで何でもやろうと思ったら、戦争だってできるんです。国葬、誰が喜んでいるか。いうまでもなくそれは統一教会です。「死」は私事の最たるものであり、その私事を『公』に利用するのが国家だ。『公』が『私』のもとに無制限に入り込み、公私の区別がつかなくなる。国は異論を封じる道具に使われる」(9月30日「毎日新聞」夕刊)。至極まともな考えだと思う。
G7首脳は誰一人来なかった
国葬で菅前首相が読んだ「絶賛弔辞」も話題を集めている。立場の違う会葬者の心をつかみ、静かな拍手が広がったという。しかし、この弔辞にはウラがある。ニュースサイト「リテラ」は「菅義偉が国葬弔辞で美談に仕立てた『山縣有朋の歌』は使いまわしだった。当の安倍晋三がJR東海葛西敬之会長の追悼で使ったネタを」(10月1日配信)と報じている。
それによると、菅さんは弔辞の最後に「かたりあひて 尽しし人は 先立ちぬ 今より後の 世をいかにせむ」という山縣有朋の歌を引用した。朝鮮の民族主義活動家・安重根に暗殺された伊藤博文をしのんで、山縣が詠んだ歌だ。伊藤と山縣の関係を、自分と安倍との関係になぞらえたのだろうが、この歌は、安倍さんが6月、盟友の葛西会長の葬儀の弔辞の最後に入れたものとネタバレしてしまった。
では、その山縣有朋とはどのような人だったのか。明治政府の軍事拡大路線を指揮した日本軍閥の祖。治安警察法などの国民弾圧体制を確立し、教育勅語を作らせた。安倍さんが最後に読んだという『山県有朋』(岩波新書)の著者岡義武氏は、山縣を「閥族・官僚の総本山、軍国主義の権化、侵略主義の張本人」と見ている。
戦前の軍国主義に引き戻そうとした安倍さん。抵抗する官僚を干し上げてきた菅さん。2人の体質は似ているようだが、税金を使った国葬の弔辞で、軍国主義の権化のような人間の歌を、美談仕立てに紹介するというのはいかがなものか。
そういえば、国葬の前後に弔問外交を、と岸田首相は言っていたが、G7の首脳は誰一人来なかった。挨拶程度の弔問外交で、どのような成果があったのかも伝えられていない。統一教会の問題はさらに広がりを見せ、岸田さんは「運の尽き」か?(元瓜連町長)