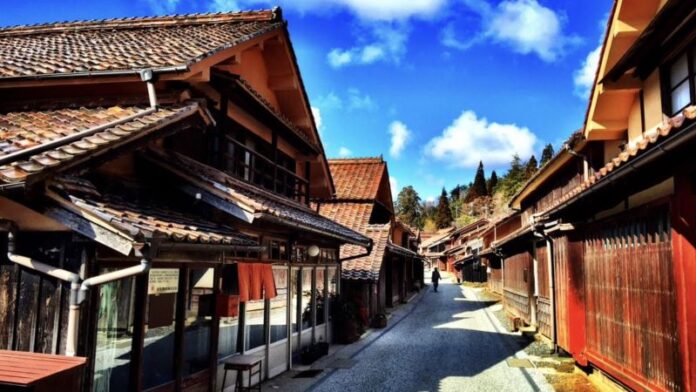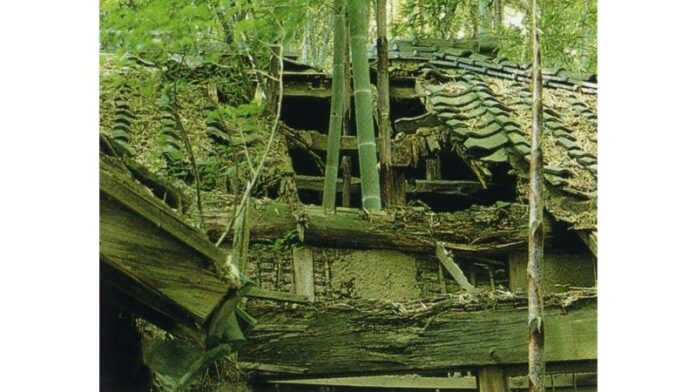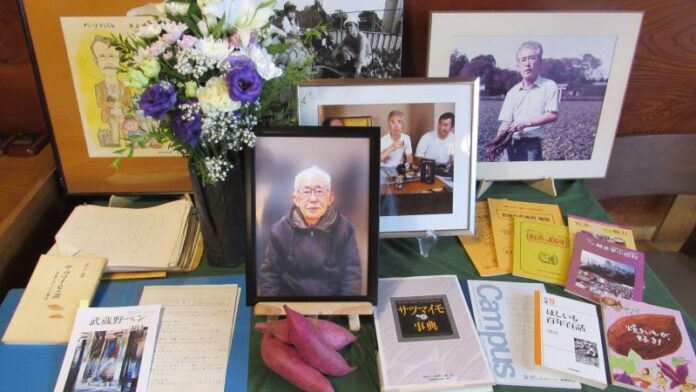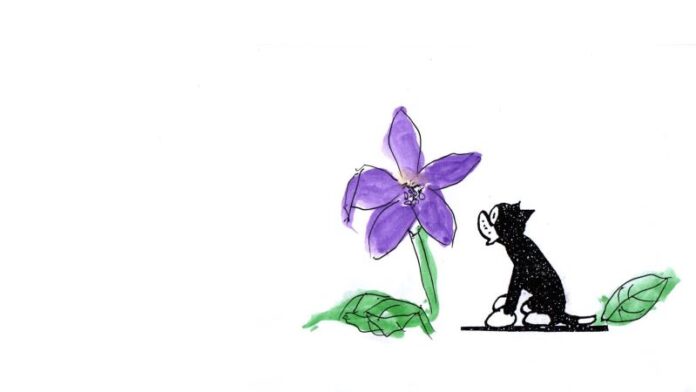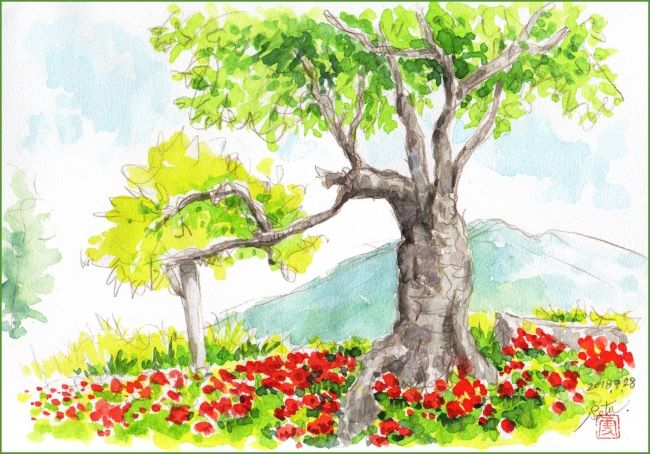【コラム・片岡英明】7月26日、茨城県の教育長は牛久栄進高校の1学級増と筑波高校の進学コース設置を発表し、つくばエリアの高校問題が動き始めた。このとき県が示した中学卒業数推計(2023年)では、水戸2490人、つくば2577人―となっており、両市の高校受験生数が逆転した。
逆転は「時間の問題」と言われてきたが、2023年は高校入試を考える上で大きな節目といえる。これを機に県の姿勢を問い、県への要望を考えてみたい。
今年3月の県議会で教育長は、星田弘司県議(つくば市区)の質問に、①生徒は市内及びエリア内外の県立・私立高など多様な選択肢から進学先を選んでいる、②エリア内の高校数は水戸もつくばも同程度である、③県立と私立の割合も両市とも6割と3割と同程度である―とし、そのため水戸とつくばの高校進学状況に大きな違いはないと答弁した。
この発言には驚いたが、私たちの要望は、つくばエリアの子どもたちの高校入試環境の改善にある。その中で、①県の県立高不足算定は県平均を基準に行っている、②歴史や交通利便性などの違う水戸とつくばを対立的に捉えた比較はなじまない―と考えてきた。
しかし、県の水戸とつくばの状況が同じという答弁があったので、以下、両市の比較を行ってみる。
つくばの入学枠は水戸の3分の1
水戸とつくばの中3生は約2500人で、水戸は全日制県立高校が7校(水戸一高、同二高、同三高、緑岡高、桜ノ牧高、水戸商、水戸工)、2023年の高校募集は52学級、2070人。一方、つくばは3校(竹園高、筑波高、つくばサイエンス高)、募集は17学級、680人である。
つくばの入学枠は水戸の32.8%で、3分の1以下である。両市の歴史や通学条件が違うのは確かだが、それでも、同じ中3生の県立高受験枠がこれほど違ってよいのだろうか。
水戸エリアの県立高校では、市内7校、水戸農高、笠間高、茨城東高の10校。募集枠は68学級、2690人。一方、つくばエリアは、市内3校、石下紫峰高、水海道一高、同二高、守谷高、伊奈高、牛久栄進高の9校。募集枠は53学級、2120人。学校数の差は1でも、つくばエリアは水戸エリアよりも15学級、570人少ない。
2023年の中3生は水戸エリアが3506人、つくばエリアが4229人。つくばエリアが723人多い。そのため2023年度入試の全日制県立高の県平均収容率は68.4%だが、水戸エリアの収容率は76.7%、つくばエリアは50.1%である。
水戸は県平均を上回り、つくばは県平均に届かない。つくばエリアを県平均レベルにする必要学級は72学級であり、現時点で19学級不足。また、水戸エリアに合わせるための必要学級は81学級で、現時点で28学級不足となる。
教育長は、水戸とつくばの共通性を強調したが、両市およびエリアの高校入試の状況は大きく違っている。
早急に県平均水準の県立高校枠を
私たちは水戸市・水戸エリア水準の募集枠を求めているわけではない。つくばエリアの小中学生のために、県平均水準までに入学枠の改善を検討して、11月の2024年県立高募集定員発表の場で、受験生に希望を与えてほしい。(元高校教師、つくば市の小中学生の高校進学を考える会代表)