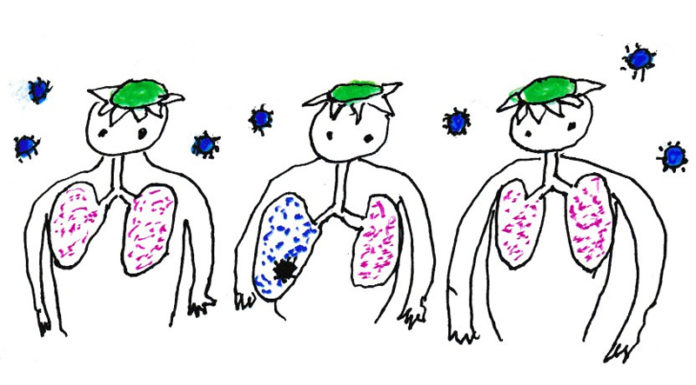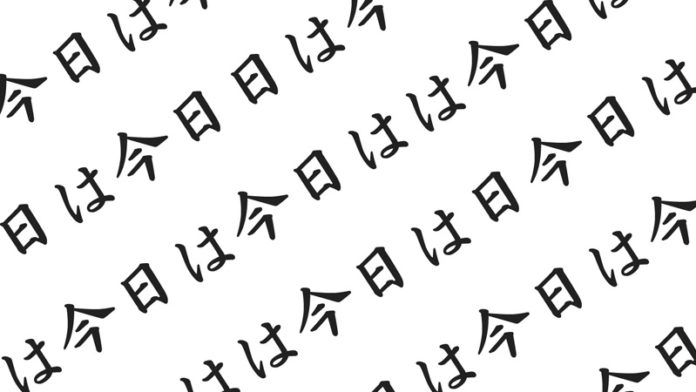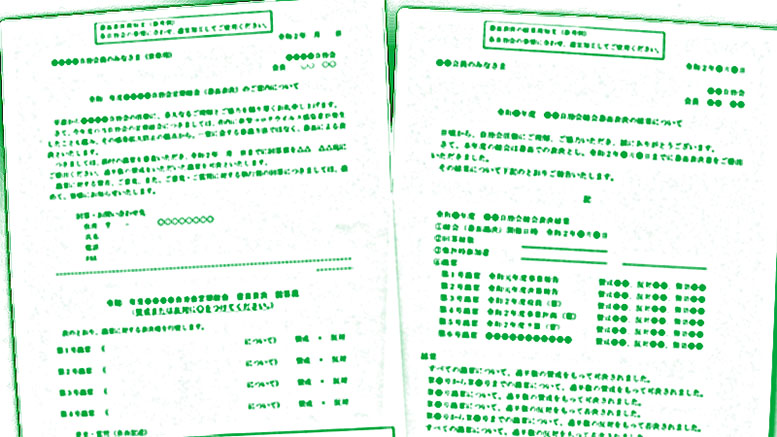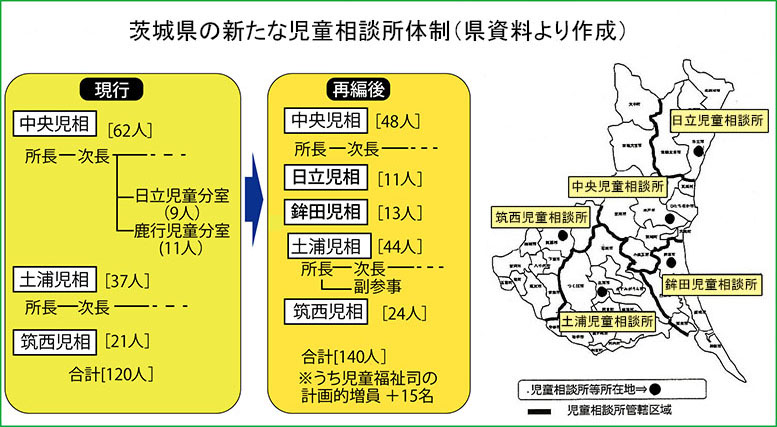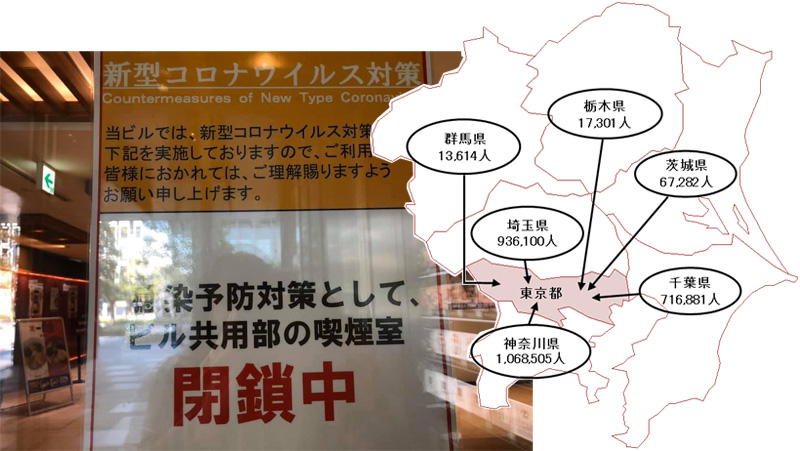【コラム・浅井和幸】前回のコラムでは、不安にも憂鬱な気分にもポジティブな意味があるということをお伝えしました。ネガティブに思える感情や感覚も、適切に作用すれば、それは大きな利点があるものです。しかし、「過ぎる」感情や感覚は、短期的にも長期的にもデメリットが大きいので、対処が必要ということになります。
例えば、不安についてです。不安は、これから起こるかもしれない「嫌なこと」に対する警報機のようなものです。それは、まるで「この先に行ったら電車にひかれてしまうよ」と呼び掛けているような作用です。
踏切の警報機の音は、人が聞いて嫌だなと感じる不協和音が使われているらしいですね。他の警報音も、なんとなく気持ち悪いな、怖いな、不安だなと感じる音になっているはずです。
不安があるから、なんとなく嫌な感覚だから、そこを避けられるわけですね。ですが、電車も来ないのに、この警報機が鳴りっぱなしだったらいかがでしょう。もしくは、まだまだ電車は遠くかなたで、踏切に到着するには1時間以上もかかるような時点から、遮断機が下り、警報機が鳴り続けたらどうでしょうか?
この文章を書いていて、具体的に想像してしまい、今、私は背筋が「ぞくっ」とするような感覚です。とても怖い状況であるからです。
不安をコントロール
警報機が鳴っている。不安になることは必要なことです。踏切に入らなければ安全だという事を知っていれば、不安はコントロールしやすいですね。音がうるさくて耳が痛いのであれば、警報機から少し離れたり、耳を少し塞(ふさ)いだりしてもよいでしょう。
少し、友達との会話の声を大きくして、楽しい話しに気を紛らわしてもよいかもしれません。カーラジオの音量を少し大きくしたり、鼻歌を歌ったりしてもいいですね。別の道を探したり、そもそも踏切を使わずとも、好い生活スタイルを計画したりしてもよいかもしれません。
どこから危険な電車か何かが自分にぶつかってくるかもしれないということにパニックにならないようにするには、知り合いや専門家などとコミュニケーションをとり、対処法を模索することが必要です。
私たち人間は、正確な現在の状況や未来を感じたり考えたりすることはできません。さらに私たちの脳は、勘違い、思い込みもドンドンするようにつくられているそうです。そのなかで、有効な心の警報機の聞き方と、対処法を繰り返しバージョンアップしていくことで、自分の行きたい生き方に近づけて行けるとよいなと思うのです。
あなたは、幸せになるために生きていますか? 不幸になるために生きていますか? 楽しむため? 苦しむため? 日々、選択の繰り返しですね。(精神保健福祉士)