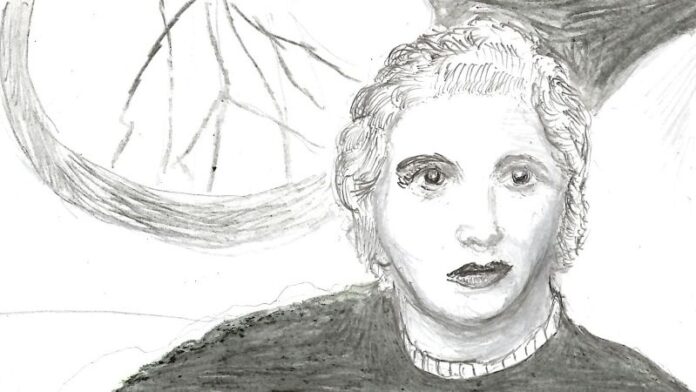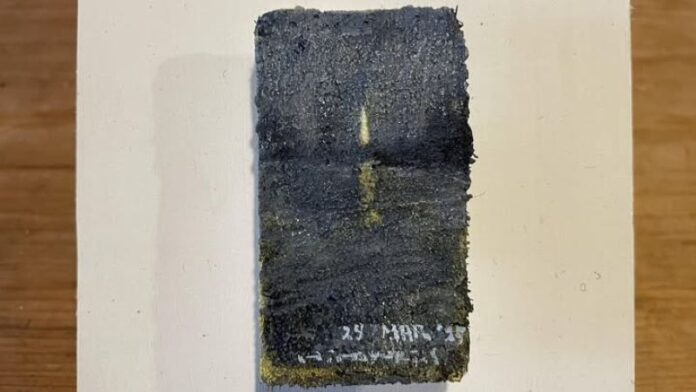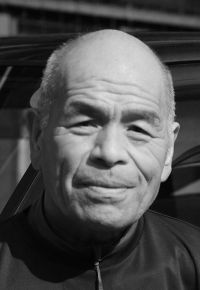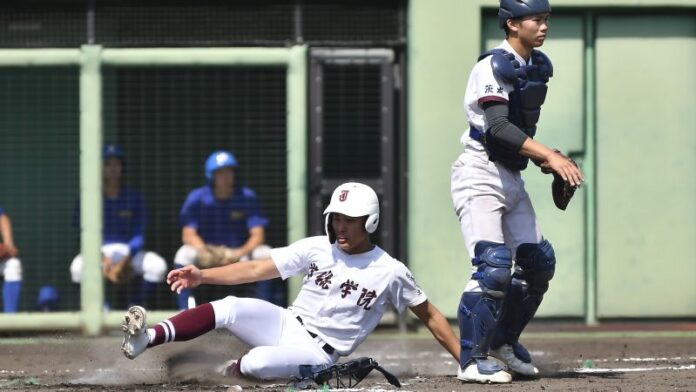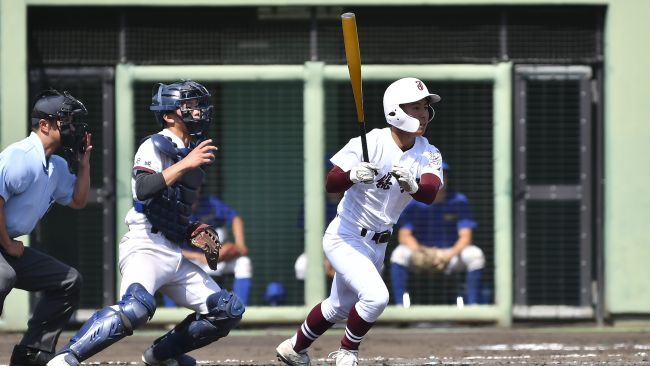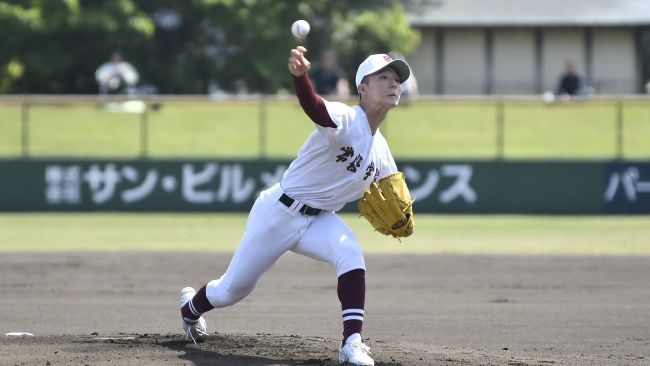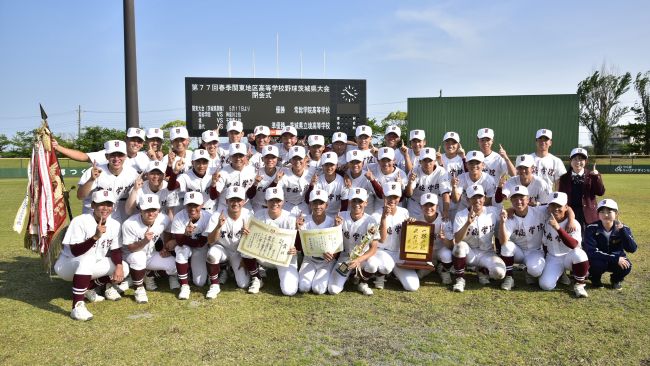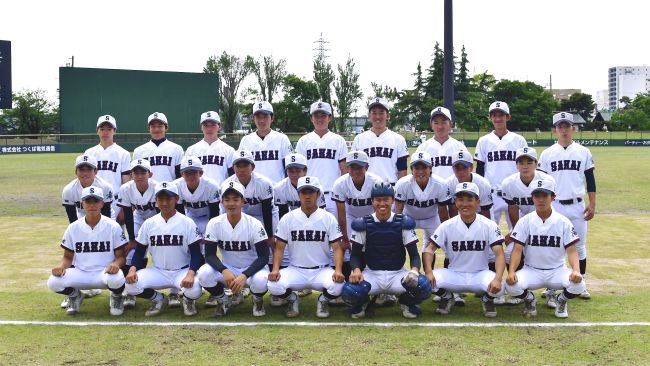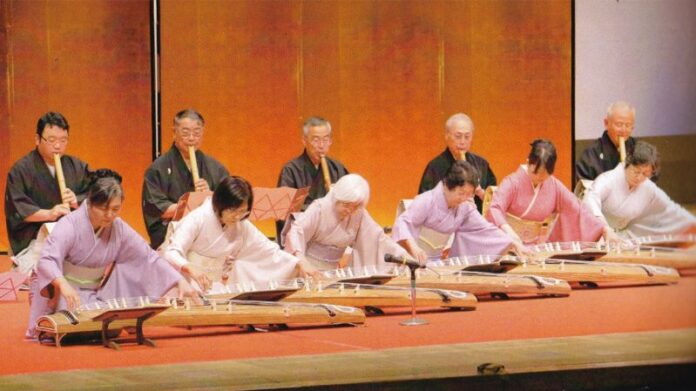一つのテーマをめぐり参加者らが意見を出し合い、考えを深める「哲学カフェ」を、土浦一高哲学部の生徒が市内の交流スペースで、一般市民を交えて開いている。イベントの企画、運営、進行は生徒自身が行う。子どもから高齢者まで参加できる開かれた場所で世の中の「当たり前」を問い直そうと、活発な対話が繰り広げられている。
自由って何?
「そもそも『自由』ってどんなこと?」「好きなことをするのが『自由』なの?」「選択肢が多いことが『自由』じゃないかな?」「でも本当に自分が『自由』な選択をしているのかわからないことがある」―
4月27日、土浦市中央のイベントスペース「がばんクリエイティブルーム」2階の和室では、高校生や社会人15人ほどが車座になり意見を出し合った。開かれたのは、土浦一高哲学部の生徒が市民と開く2回目の「市民哲学カフェ『語るカフェ』」だ。午前10時から始まり午後3時半まで、2部制で行われた。
 (左から)土浦一高の大野さん、三浦さん、飯島教諭、小関さん、神谷さん
(左から)土浦一高の大野さん、三浦さん、飯島教諭、小関さん、神谷さん
午前中のテーマは「『自由』とはなにか?」。午前・午後を通じたテーマである「我々は『自由』に生きることを求めているのか?」を話し合う前に、まずは参加者各自が思う「自由」について確認し合った。持ち寄られたお菓子や飲み物を口にしながら、自己紹介をしつつ和やかに進んでいく。高校生の孫を持つという市内在住の女性は、「チラシを見て興味を持った。孫がどんなことを考えながら暮らしているのか想像できればと思った」と、参加の動機を話した。
4月に大学生になったばかりだという男性が「大学に入って自由な時間が多くできたが、何をすればいいか悩んだ。大学では自発的に決めなければいけないことが多い」と思いを吐露すると、社会人の男性は「浪人時代に一番自由を感じた」と、自身の経験を語った。年齢も属性もさまざまな初対面の参加者同士が胸の内にある思いを語っていく。
40代の記者も午前中の第1部に参加した。昔の自分を思い出しながら、「大学を中退すると周りの目が気になった。その後、初めて旅した海外で感じた『自由』が今も忘れられない」と述べた。中年の自分が若者を前に自分語りをする気恥ずかしさを感じたが、揶揄(やゆ)する人はいなかった。
参加者にはいくつかのルールが課せられる。「専門用語を使わず、わかりやすく話す」「わからないことがあればその場で質問する」「人の話を最後まで聞く」「自分の意見や信条を押し付けない」「秘密は守る」などだ。人の話に耳を傾けるだけでもいい。誰もが対話の輪の中にいられるよう、工夫が凝らされる。
フランスで始まった哲学カフェ
哲学カフェは、フランスの哲学者マルク・ソーテが1992年にパリで開いたのが始まりとされる。96年にソーテの著書「ソクラテスのカフェ」の邦訳が日本で出版されると、国内の大学や高校、市民グループなどに活動が広がり、全国各地で哲学カフェが開かれるようになった。
土浦一高の哲学部ではこれまで、生徒同士やOB・OGが参加する「哲学カフェ」を学内で開いてきた。学外で行う市民参加型の催しを企画したのは昨年12月が初めて。現在、部員でつくる市民哲学カフェチームのリーダーを務める3年の神谷和奏さん(17)が、会場の関係者と出会ったのがきっかけになった。
同哲学部顧問の飯島一也教諭(57)は「土浦一高の哲学カフェで大切にしたいのが、生徒自身がイベントを運営し、議論を進めるファシリテーターを務めること」だと話す。「教員を介した高校生と市民の交流会ではなく、生徒が直接市民と向き合い、高校生も一人の市民として、多様な参加者のいる対話の場に参加させたかった」と思いを語る。
議論中も、生徒自身が工夫を凝らす。第1部でファシリテーターを務めたのは部長の大野耀大さん(17)。参加者間で議論が白熱し始めると、質問を挟むなどして話し合いのペースを調整する。抽象的な言葉が行き交い始めた際は、チームのサブリーダーで2年の小関凌輔さん(16)が、図やイラストをホワイトボードに描いて議論を整理する場面もあった。議論からこぼれ落ちる人が出ないよう、生徒自身が対話を成り立たせていた。
 対話の中で、イラストや図を描いて議論を整理する
対話の中で、イラストや図を描いて議論を整理する
チームリーダーの神谷さんは「異なる考えを受け入れ合えるのが『哲学カフェ』。私自身、他の人と違う考え方をしても受け止めてもらえることがうれしい。自分が帰属できる居場所だと感じている」とし、一般市民も参加することについては「子どもの私たちに対して、初対面の大人たちが自分の人生観や経験をもとに対等に話をしてくれる。新しい世界の広がりを感じられる」と思いを話す。
市民哲学カフェ運営スタッフで2年の三浦由宇さん(16)は「哲学カフェでは何でも議題にしていい」のが魅力だという。「『当たり前』だと感じていたことを真剣にみんなで議論できる。『これって疑問に思っていいんだ』と感じられる」。2年の小関さんは「参加する人の職業、年代、経験もさまざま。自分だけでは気づけない考え方に出合える」とし、この日のカフェでは「『浪人生時代が一番自由』という話題が衝撃的だった。勉強しなければいけない浪人生こそ一番縛られていると思っていた。参加して良かった」と感想を話した。
勝ち負けではない。
「哲学カフェで大切なことは『対話』。勝ち負けではない」と顧問の飯島教諭はいう。「対話を通じて同じ考え方を紡ぎ出していくプロセスを大切にすることが重要」だとし、「『対話』という形は人間関係のモデルになる」と考える。「社会的な分断が起きている現代社会の中で、多様性を認め合い、共通の言葉を使いながら思索を共にする経験は貴重。土浦一高の哲学部として社会的な意義を見つけることができたら」と話し、「哲学部としてどんな活動ができるのか。部員の中からアイデアがあれば今後も積極的に実現していきたい。他校で哲学をテーマにして活動する部活動があれば情報交換していきたいし、哲学カフェをする他校の生徒たちと交流することができれば」と、今後の活動への思いを語る。
次回の市民哲学カフェ「語るカフェ」は、8月の開催を予定している。(柴田大輔)