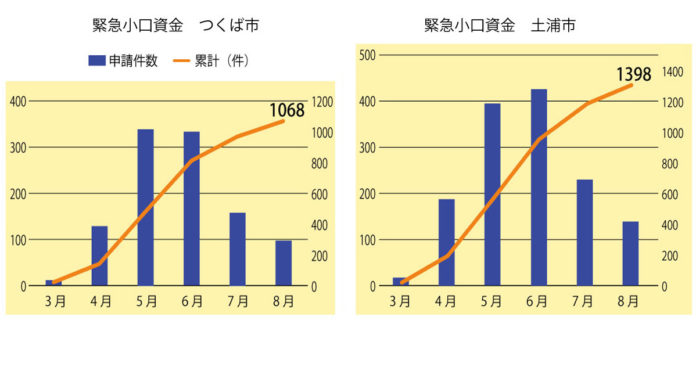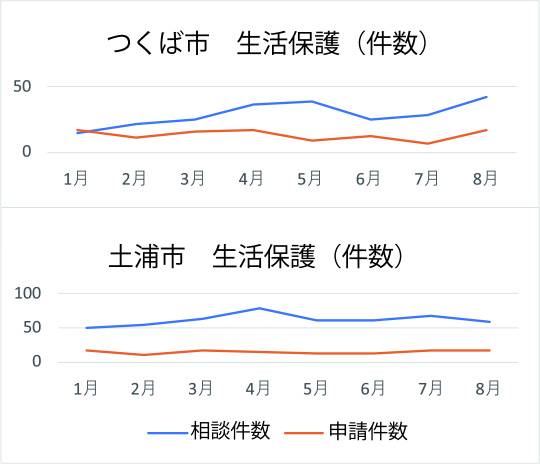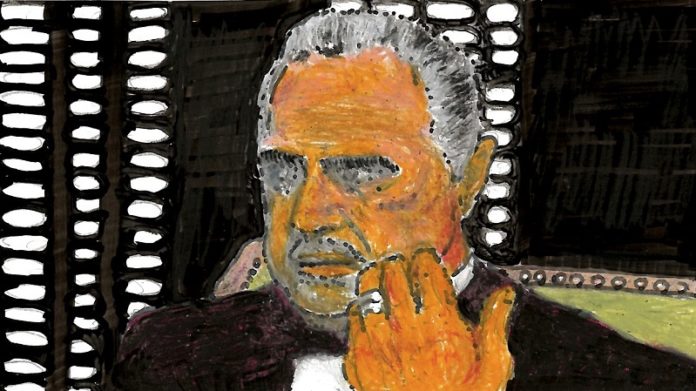【鈴木宏子】任期満了に伴い18日告示、25日投開票で行われるつくば市長選に、新人で元高エネルギー加速器研究機構研究者の酒井泉氏(71)=無所属=が12日記者会見し、立候補を表明した。同市長選にはすでに、現職で2期目を目指す五十嵐立青氏(42)=同=、新人で自動車販売会社などを経営する富島純一氏(37)の2氏が立候補を表明しており、三つどもえの選挙戦になりそうだ。
酒井氏は、現職の五十嵐氏が4年前、総合運動公園用地を買い戻させるため元所有者のUR都市機構と返還交渉を行うと公約に掲げながら、「URに要望しただけで交渉した形跡がない」と情報開示資料を示して指摘し、「言ったことをやらないのは最低最悪」だと批判した。
さらに昨年、五十嵐氏が、同用地を40億円で民間に一括売却しようとした点についても「わずか2カ月の公募で、買い値の66億円より26億円も安いのは極めて不自然な経緯」だと批判。「総合運動公園用地は研究施設用地として大事なところ。あそこがなくなったら、つくばにもう研究機関が立地しない。新しい研究分野のための施設用地として保全し、つくば研究学園都市の将来の発展の可能性を次世代に残すべき」だと主張した。
その上で、①URと再交渉し、総合運動公園用地を元の研究施設用地に戻して66億円を取り戻す②肥大化した部長・次長職を整理し市役所改革を行う③広すぎるつくば市を、地域ごと地区ごとに、議員と市民が政策提案して問題を解決できるようにするーなどを公約に掲げるとした。
総合運動公園用地の返還交渉について具体的には、まず研究所のリーダーを集めてつくばの将来計画をつくり、URによる買い戻しを国に働き掛けたいとした。返還交渉などの公約実現が困難だと分かった場合は、任期途中でも職を辞すと強調した。
酒井氏は同市上境在住。土浦一高、東北大学工学部卒。日立電線研究員を経て、高エネ研准教授、福井大学大学院教授を歴任した。現在、TX沿線開発地区の一つ、中根・金田台地区の地権者らでつくる桜中部まちづくり協議会副会長を務め、緑地と菜園と住宅が一体となった緑農住一体型住宅を提唱などしている。