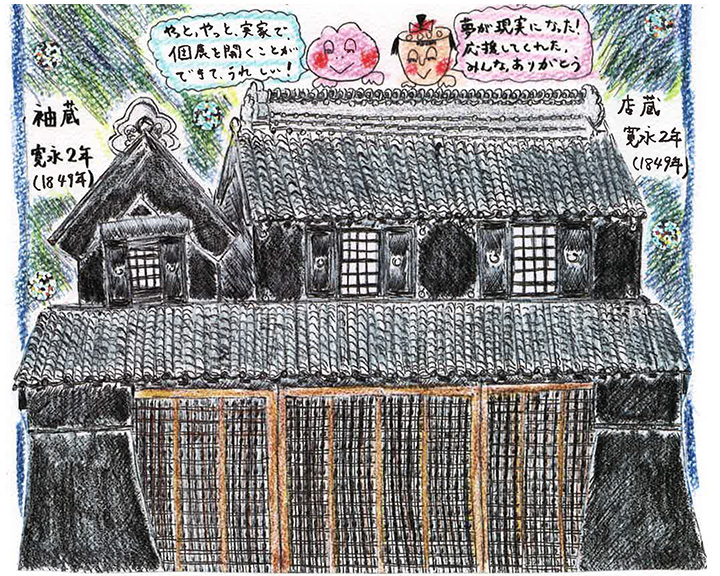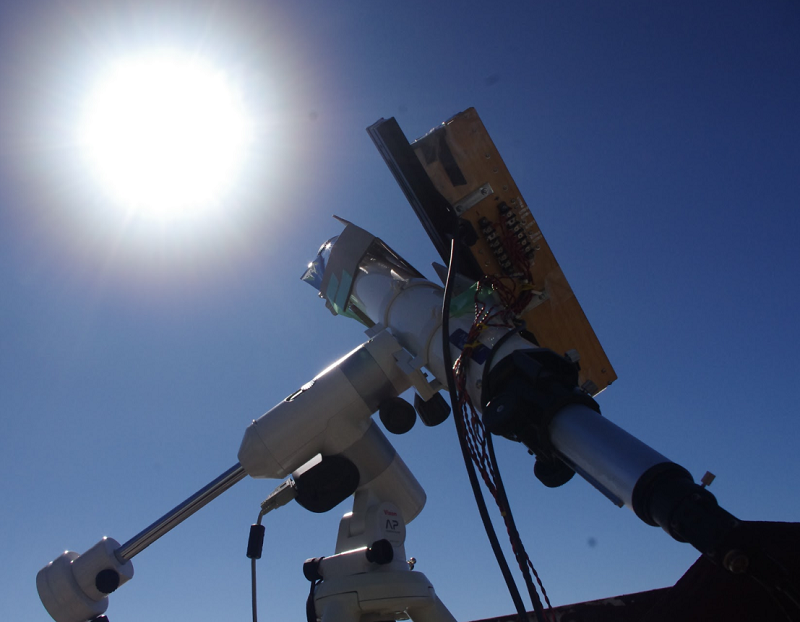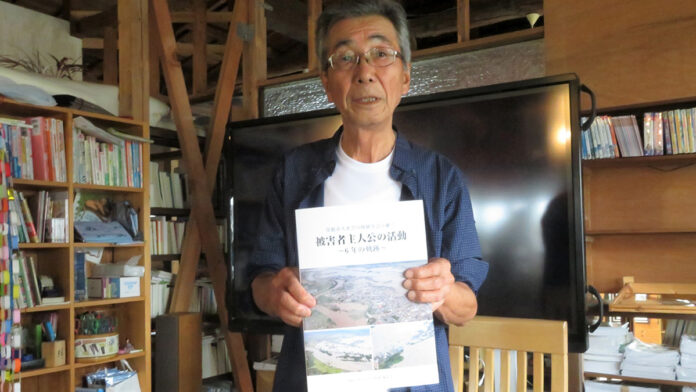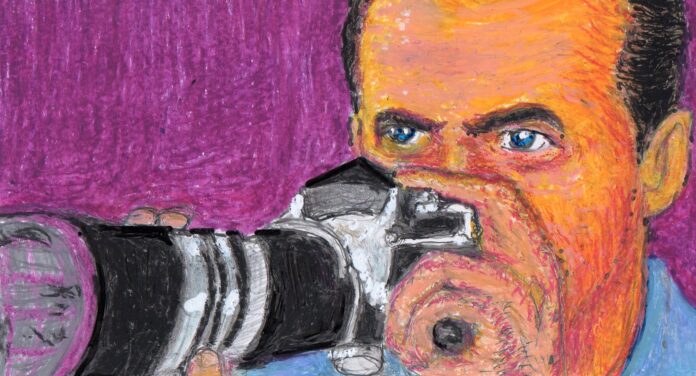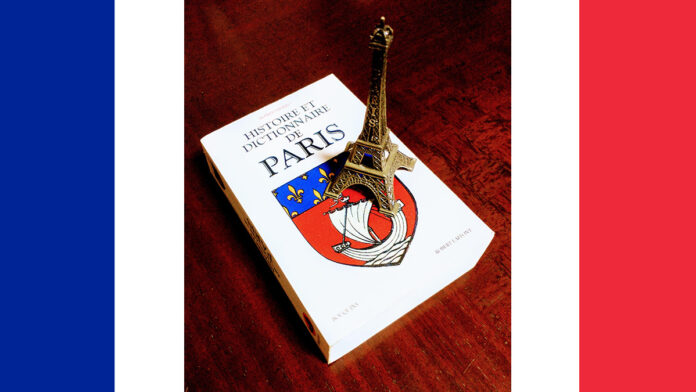「公園が借りられない」。そう話すのはつくば市の食料支援団体「学生応援プロジェクト@つくばPEACE(ピース)」の冨山香織代表(40)だ。コロナ禍、毎月1回程度、食材の配布を行っているが、今、開催の危機にひんしている。
筑波大学近くの松見公園(同市天久保)を中心に活動している。9月は25日または26日に開催する予定を立て、公園を管理する市公園施設課に申し込んだところ「緊急事態宣言の延長により屋外であっても公園は貸せない」と利用を断られた。
やむを得ず、つくばPEACEはツイッターなどのSNSで、25日か26日に必ず開催することを利用者に知らせた。安心してもらうために日付けのみの告知を行ったという。しかし配布日が約10日後に迫っているにも関わらず、いまだ開催場所は決まっていない。
2020年12月に食料支援活動を立ち上げた。コロナ禍でアルバイトが減って困窮する学生や母子家庭などに食材や日用品を無償提供することにより、生活の心配を減らし安心して勉強してもらうための活動を行っている。
猛暑となった夏期も、屋外の炎天下での活動は、食材が傷んでしまったり、利用者の学生やスタッフが熱中症になる危険を避けるため、屋内の公共施設の利用を申し込んだが、いずれもコロナ禍を理由に断られ、場所探しに奔走した経緯がある。

今回、松見公園の利用を許可しなかった市は、取材に対し「緊急事態宣言の延長もあり、すべての団体に(使用できない旨を)一律で伝えている。人流を抑制するためにも不要不急のイベントは控えてもらいたい」と話した。
市は、つくばPEACEに対しても「緊急事態宣言が出でいるから」の一点張りで、利用の基準等について何も説明はなかったという。一方、つくばPEACEは、コロナ禍で困っている人にとって食料支援はライフラインになる場合もあるとし、一律に使用させないのではなく、利用の基準を設けるべきだとする。
冨山代表は「毎月、必ず開催したい。活動を続けてほしいという声も多く聞く。仕送りが減り学業に専念することができない学生や、二つ以上の仕事を掛け持ちするWワークをせざるを得ない人がいる。(第5波の経済的影響が顕著になる)今からが本当に大変な時期になる。だからこそ支援活動を続けていかなきゃいけない」と語った。
食料支援を利用している利用者の一人で筑波大医学群看護学類3年の女子学生は「今、実習中でバイトが禁止されている中、様々なものを支援していただけて本当にありがたい。特に生理用品や即席で作れるレトルトはとても役立っている。コロナ禍でも支援してくださる人の温かさを感じることができてうれしく思う」とし「まだ開催場所が決まってないと聞き心配。早く会場が決まってほしい」と話す。
冨山代表はさらに「支援者の中には、毎月寄付金を送ってくださる方、配布会ごとに毎回、段ボール3箱ほど持ってきてくださる方もいる」とし「寄付は全国各地から集まってきている。また、スタッフの中にもレトルト食品や寄付金を行っている人もいる。活動を続けていくためにもより多くの寄付をお願いしたい」と話す。(武田唯希)



![川浪せつ子 39[2305843009251925318]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/09/de4e8b3374084b8af41cfbd414ea5cb1-696x348.jpg)




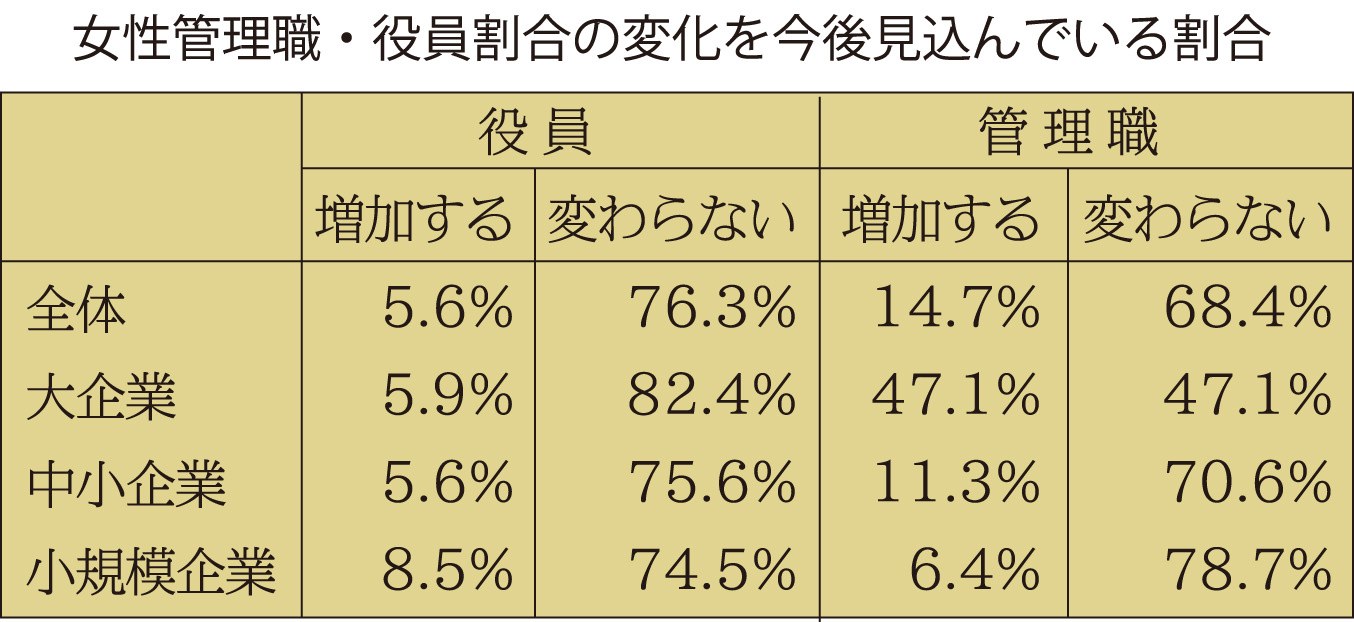
![斉藤裕之 93[6129]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/09/a9e8924eeb9a9407e944f06d9ab71adc-696x390.jpg)