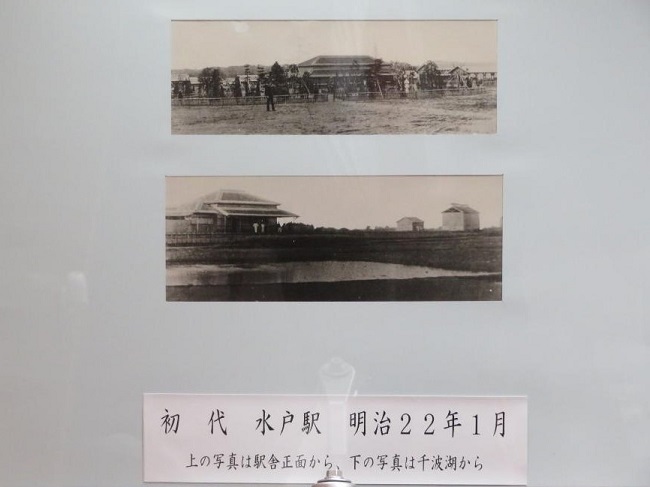住民投票で計画が白紙撤回された旧総合運動公園用地約46ヘクタール(つくば市大穂)を、市が民間に一括売却する方針案を出したことを受けた(11月11日付、26日付、12月1日付)市民説明会が10日と12日開かれた。10日は午後2時30分からと7時からそれぞれ大穂交流センターで開かれ、1回目は約35人、2回目は約15人が参加した。12日は午前10時から市役所で開かれ、約30人が参加した。参加者からは「(一括売却案は)何を実現したいのかが無い」「なぜ今、一括売却かの説明がない」など、厳しい意見が相次いだ。これに対し説明に当たった五十嵐立青市長は、財政の厳しさを強調し「前に進めたい」と繰り返した。
 一括売却案について説明する五十嵐立青市長(中央)
一括売却案について説明する五十嵐立青市長(中央)第1回目の説明会の主なやりとりは以下の通り。
参加者 (防災拠点施設を整備することについて)水、交通について質問、意見したい。水は、上水はいろいろな給水方法があるが、下水はトイレの汚物を含む下水、汚物処理どうするのか。道路がうまく使えない災害を想定すべき。ここの地点(大穂)は遠い。汚物処理拠点としての機能が必要。交通は、道路が(地震などで)割れたらどうするのか。航空によるしかない。まっ平らな広いところが必要。46ヘクタールは滑走路を確保するにはぎりぎりの広さ。ドローンで運ぶ場合もある。そういうことが全く抜け落ちている。航空は高いものを建てるともうだめ。そこを計画に入れていただきたい。
五十嵐市長 汚物処理は危機管理課から説明する。道路は滑走路確保は厳しい。ドローンの活用など災害時は様々な可能性がある。1カ所だけですべてまかなうのは難しいと思っている。ヘリポートは、このスペースがあればいくらか離着陸できると考えている。高い建物は、10階建てが建つことはない。
市部長 処理場は下横場にある。災害時はそこに流して滞留させる。市の容量の2日分をためることができる。
参加者 流路が割れたらどうするのか。(汚物を)一次的に置いておくことを一番最初に考えないといけない。
市長 市全体としてどういうことができるか考えたい。
参加者 (売却)価格設定は簿価ベース、68億円以下はないということか。(方針案では)公共施設は備蓄倉庫とか避難場所になっている。広報つくばやかわら版を読むと、最大のポイントは地域の活性化だと言っているが、倉庫だとか備蓄倉庫だとか、活性化じゃなくて空洞化を起こすような施設しか出てない。事業者はメリットがないと地域の活性化を前提にしない。地域の活性化がポイントであれば、より具体的に、どういう施設を置くんだと言うことをポイントにしてほしい。防災倉庫は、利用者が整備したものをリース契約のようにするのか。
市長 価格設定は用地取得費66.1億円と利子2.4億円を足した金額以上と考えている。地域活性化は、物流施設では雇用が生まれないというが、聞き取りの範囲だが、物流施設ができたとしたら6000人ぐらいの雇用が生まれるだろうと聞いている。働く場として大きな期待感をもっている。防災倉庫はリース契約ではなく賃貸契約。民間が整備したものを市がお借りしていくという形のもの。
参加者 用地を購入したのは運動公園をつくるのが大きな目的だった。施設の半分を売却して、後は運動施設、野球場、サッカー場、グランドゴルフ場、テニスコート、体育館などをつくる予定はないのか。小学生の孫がサッカークラブに入っている。土浦市の新治運動公園、下妻市のほっとランド・きぬに行く。つくば市には運動施設がない、ぜひとも整備をお願いしたい。
市長 当初、運動施設が目的だった。何より305億円かかると、結果として住民投票でなくなった。スポーツの拠点をつくることは必要だと考えていて、上郷高校に陸上競技場を整備する計画を立てて(大規模事業評価の)審議をしていただいている。サッカーができるスペースもできる。障害者スポーツをしやすくしたり、高齢者スポーツや、地域の皆さんが集まってスポーツができる環境を上郷高校で準備している。お孫さんにもそういう場所が出来れば使っていただきたい。
参加者 当初のこの土地は運動公園として使うため取得した。研究学園駅につながなきゃ利用価値がない。どのように道路をつくるのか。
市長 南側の道路をどうするかは、事業者からの全体計画が出てきてからになると思っている。災害の時、市の防災備蓄品が取り出せないとか、そこは(売却事業者選定の)評価項目になってくる。
参加者 市執行部、議会の怠慢ではないか。
市長 この土地について少しでも早く解決することが重要と考えている。議会から提言書をまとめていただくことができた。(一括民間売却案は)基本的には議会の提言書に沿ったものと理解している。急ぎ過ぎという意見もあるが、かなり議論を積み重ねている。前に進めたい。方向性を出していきたい。
参加者 つくばには平地林がたくさんある。木を使って、バイオマス発電をつくって、つくば地区の環境整備、林業再興を目指し、地元でつくったエネルギーを地元で使う、あれだけの土地を地元のエネルギー供給源にできないのかとパブリックコメントで提案している。将来に対する投資という意味で、一緒に環境を改善していく企業を誘致してはどうか。
市長 どうやって環境を守るか、さまざま取り組んでいる。ゼロカーボンの問題意識を持っている。街路樹も守らなきゃだめだと、工事が始まったのを止めてもらったこともある。(事業提案の中に)発電施設の提案もいくつかあった、EV(電気自動車)開発の複合施設の提案もいただいている。どの事業者も、エネルギー、環境に配慮をしないことのマイナスを理解している。どういう形になっても確実に環境に配慮する様々な工夫はされるだろうと思う。(売却先の事業者選定では)事業の中身と価格の両方で審査する。中身の審査も環境に配慮しているか審査する。化石燃料をどんどん使ってCO2を出しまくる場所にはしてはいけないと思っている。
参加者 いちはら病院のメディケアレジデンスに住んでいる。(用地の)南側を散歩コースにしている。見事な木がはえており、建物に代えられない資源だと思う。そこを生かして快適な素晴らしい散歩コースを残していただきたい。
市長 私も歩いて通っている。あの辺り、いい環境になっていると感じている。多くの企業から聞き取りしたところ、南側に病院と住宅地があり、新しくできる施設と病院との緩衝地帯にしていくことは理解を得ている。南側を全部丸坊主にすることはしたくない。そこは安心をしていただければ。
参加者 大穂で、通勤・通学時間に子供たちの誘導をやっている。通勤時間は交通渋滞となり、安全性も含め危険な状態になっている。運動公園のときも幹線道路含めて(配布資料の図面の)左側に道路が予定されていたが、今の計画では6年後と聞いている。運動公園跡地の開発では間に合わないと思ってる。全体の交通インフラを含めて早急に進めないと大変な問題になる。
飯野副市長 北部工業団地から東光台を結ぶ都市計画道路のことだと思う。(高エネ研との間の)県道213号を拡幅したら、結ばれてネットワークができる(計画がある)。県の方も、用地買収しながら北部工業団地に続く道路の事業計画をしている。未買収のところも残っているので、この事業と合わせて進めたい。
参加者 住民投票(で計画の白紙撤回)が決まった時、跡地の利用を考えないといけないよ、と五十嵐さんに言ったことがあるが、(プランは)何もなかった。(今回の一括売却方針案は)一体、何をやりたいんだろうか。何を実現したい、ということが無い。大事なことは何も言ってない。やるべきことはたくさんある。今慌てて売るんじゃなくて、市がやるのがいいのかも含めて、きちんと(市が用地を)持っている必要がある。自分たちはこういうのを実現したいんだというのが無かったら、待つ方がいい。つくば市は研究学園都市にある。つくば市は地方自治体だけれども、もっと日本全体のことを考えることを期待したい。早急に決めることは絶対に反対。
市長 つくば市がここをどうしたいか、それは明確。どういう形で地域に資するものにしていくかだが、研究所は待っていれば来るというものではない。この土地をずっと持っていることはできない。66億円で買ってしまった。運動公園の目的がなくなった。土地を返すか、有効活用するか。日本を代表するエリアは必要。それはこの土地でなく、つくば駅に隣接する(吾妻地区の)70街区。(70街区は)放っておいたらマンションに売られてしまう。つくばの最先端の研究機関のショーケースとして、国や県と一緒に整備していきたい。取捨選択するのが市長としてすべきこと。運動公園は上郷高校(につくる)。何もしたいことがないのではなくて、今回の方針案のような施設を誘致することが将来のつくば市にとってプラスになる。
参加者 反対というより(市の方針案では)何をやりたいか分からない。何をやりたいのかが出てないから困ってしまう。ここを使って何を実現したいのか、今もお話いただいてない。
市長 1期目では結論が出なかった。その時と何が違うかというと、議会が特別委員会をつくってくださったこと。1期目は議会側の意見がさまざまあった。その中で委員会として提言書をまとめてくださった。そうやって確実に進んでいる。陸上競技場も基本構想ができた。着実に進めていけると思っている。きちんと伝わられないのであればいろいろな方法を使って伝える方法をしていきたい。
参加者 水守のクリーンセンター近くに住んでいる。いい空気ではない。もしこの土地(旧総合運動公園)を利用できれば、第2クリーンセンターをつくりたい。それから半導体不足で、TSMC(台湾の世界的半導体メーカー)は(熊本県の)ソニーの敷地に工場をつくっている最中。つくばにつくってもらえればよかった。世界一有名な半導体工場を誘致していただければ活性化になる。TXの駅にも使いたい。膨大な敷地があり、駐車場もバスも入る。ぜひ検討してほしい。今つくば駅前では国の研究所の宿舎を次々に壊している。つくば市は終わりだと感じる。よし、私(市長)がやるんだと、もうちょっと市民の先頭に立ってやっていただきたい。
市長 クリーンセンターは地元の理解を得ながら(現在地の施設を)長寿命化をしながら使っている。ここにつくることは考えられない。TX延伸はいろいろな意見があるが、その先の整備費は国は出さない。整備するとした地元がやっていくことになり現実的でない。TSMCは熊本に工場をつくるが、つくばの産総研に研究開発拠点をつくる。つくばが世界の最大手に選ばれる場所であることを示すことができた。世界経済フォーラムに呼ばれて参加しているが、そこでつくばの注目度が上がっていると紹介してもらったりしている。メディアで取り上げられる回数も増えている。つくばは確実にいい方向に進んでいる。
参加者 民間の4事業者から提案があったということだが、4事業者の案は示してもらえないのか。
市課長 4事業者の提案は(配布資料の)1(工業団地等)、2(物流倉庫施設等)、3(物流施設・データセンター等)、5(EV実験場等)だが、公募したとき、4事業者が応募するとは限らないし、それ以外の民間事業者の応募を妨げるものではない。
参加者 選考はどなたがどういう過程で選考するのか
市課長 事業者の事業計画提案、価格提案の両方の観点から評価したい。いくつかの手法があるが、公募型プロポーザルが望ましい。ガイドラインに従い、評価委員を選定して、公募期間が過ぎた後にプレゼンしてもらい、評価を行って候補者が決定する流れになる。
参加者 案が示されてない。案が決まった後、再度、住民説明会を開いてほしい。つくばみらい市では70町歩の工業団地の造成が進んでいる。市でお困りであれば、具体的な案をもって県に相談いただければいくらでも力を貸す。
市長 当然、事業者が決まったら皆さんにきちんとお話する機会をつくりたい。先日も県の担当者に来ていただいて意見交換したところ。県ともさまざまな形で随時話していきたい。
参加者 問題は、46ヘクタールの公有地、66億円の購入費用、民間一括売却が果たしていいのかということ。歴史を考えてみると、URが全面買収し、平成11(1999)年に研究施設用地として不要と判断した。(前市長の)市原さんが総合運動公園用地として購入した。五十嵐さんは、URと交渉したが、らちが明かなかった。民間事業者1社に売却し地域にプラスになることを進めるというが、URに返還することが一番いい。臨海副都心のように暫定用地として使うこともできる。五十嵐さんは「URと返還交渉する」「裁判も辞さずにやる」と言った。拍手喝采した。交渉をどの程度やったのか。研究施設用地の発展余地として残しておくことが絶対必要。交渉すれば66億円は返ってくると思っている。暫定利用として地元のために使うことができる。民間事業者に売る前にURとの交渉をもう一度考えるべき。売るにあたっても一括売却が本当にいいのか、昨日(9日)の議会(一般質問)の答弁で部長が固定資産税が入ってくると言ったがちょっと違う。固定資産税は行政サービスに対する対価。地主は税金を払っているが、つくば市は土地をもっていても税金を払わないで済む。市は46ヘクタールの土地を保有コストなしにもっていける。もっとじっくり利用を考えるべき。民間売却しかないのか、民間に貸与する方法もある。売らなくも税収相当分がはいってくる。一括売却して地域にとってプラスになるのかというと、中根・金田台地区に物流施設がきたが、ちっともプラスにならない。熱に浮かされたように一括売却するというのは危険。URは(坪)1000円で買った土地を4万6000で売った。まずURと本当の交渉をやった方がいい。
市長 国の方針としてURに資産の整理をさせ、URは全国で資産を手放している。交渉は事務方とさまざまな話をした。プロセスに瑕疵(かし)があれば瑕疵を交渉の材料にしていくと徹底して調査したが、契約に瑕疵はなかった。(当時は)ソーラー(発電会社)が買おうとしていて、早く買わないと売っちゃうよとなった。URに返還は現実的でないと考えているが、仮に返還しても、URが売ります、というとソーラー発電になってしまうかもしれない。暫定利用は簡単にできない。造成費として1ヘクタール1億円かかる。(売った場合は)68億円、市として極めて大きな金額。恵まれた自治体なら別だが、現在のつくば市はそういう自治体ではない。66億の土地をそのままにしておく余裕はとてもないというのが、市長として仕事をしている実感。貸与と言ってもそう簡単ではない。民間利用だが、商業施設は筑穂に影響を与える施設にはしていかない。前に進んでいかなければならないタイミングが来ている。
参加者 財政的に厳しいのは分かる。だからこそURに元の研究施設用地に戻せと返還交渉すべき。それをやらないで民間売却と言っているからおかしなことになる。URと交渉をやったというならその内容を知りたい。
市長 繰り返しになってしまうが、先ほど申し上げた通り様々な話はしている。今、国は売却をどんどんしている状況。必要な土地は残さなきゃいけないから、つくば駅前(吾妻70街区)は2段階で売却していく。UR交渉は現実的ではない。
参加者 (研究機関や大学などで構成する)筑協(筑波研究学園都市交流協議会)に(用地活用の意向を)聞いたが何もなかったということだが、つくばの研究機関は余剰の土地を持っている。追いつけ追い越せ型の研究機関ではなく、新しい分野の研究用地が必要になる。
市長 URとの交渉内容はお話している。(質問した参加者が)納得してないだけ。市長、議員は選挙で選ばれた。議会に伝えて議会がOKと言えば、それが民主主義。
参加者 五十嵐さんは住民の力を忘れている。住民投票で8割が反対だった。それを背景に交渉してはどうか。五十嵐さんは研究状況を分からない。民主主義どうのというのは間違い。
市長 (質問した2人に)納得していただくことは難しいと考えるが、何もしないでこのままにしておくのは無責任な姿。
参加者 民主主義の原則は情報共有、対等な議論、少数議論を見逃さないこと。情報共有をしてない。
参加者 上郷高校跡地の運動公園はここと比べてどのくらいか。
市長 6分の1か5分の1、上郷高校は7ヘクタール。
□ □ □
「買戻し特約は必須」 第2回説明会
 2回目の市民説明会の様子
2回目の市民説明会の様子2回目の市民説明会では、一括購入した民間事業者がその後、切り売りしたらどうするのかという質問が出て、市から、10年間の買戻し特約を検討していると説明があった。主なやりとりは以下の通り。1回目と重複したやりとりは省略した。
参加者 問題は取得価格。URがつくば市に66億円で売ったことが大きな問題、どういう交渉があったのか。400メートルトラックの運動施設をつくるという話があった。そんなにかけなくても整備できる。400メートルトラックはどのように位置づけているのか。
市長 土地を取得した交渉過程は第三者の弁護士に調査していただいた。結論として、URは国から(資産の)処分を強く求められている、市は運動公園をつくりたがっている、ソーラー発電に売りますよ、市が買いたいのだったら早く表明してくださいと、価格もある意味でURの言い値になっていった。総合運動公園は305億円という大きな金額になってしまった。大きなお金をかけなくても陸上競技場をつくることができる。上郷高校に400メートルトラックがある陸上競技場を整備したい。現在、評価をしていただいているプロセスにある。高エネ南側(旧総合運動公園用地)は防災拠点としての施設にする。(防災拠点は)1カ所では心もとないので、上郷高校跡地も役割を果たしていきたい。
参加者 土地の取得の経緯は終わった話。これからどうするかを考えなくてはいけない。気になるのは(市長は)一括売却にこだわられているが、売却した後に切り売りされたら一体性は確保できるのか。最も大きな懸念だ。短冊にされて、ばら売りされたら一体性が保てるか。全体を行政がやるのは難しいかもしれないが、4分の1とか3分の1は公共活用を図り、未来永劫維持した上で、付加価値を上げてから売却する方法もある。なぜ今、全面売却しなければならないのか、そこのところの説明がない。
市長 もしそういうこと(一括取得後、民間事業者がばら売りする)が起きてしまえば市が目指している計画は実現できない。買戻し特約を設定するのは必須と考えており、公募要領の売買契約の条件にして事業者公募を行っていくことを考えている。ご懸念のことは起きない。
参加者 譲渡後を縛る契約ができるのか。一般的な土地取引でそれができれば世の中の土地問題は起こらない。
市課長 他自治体を確認している。債務不履行があった場合(他自治体では)10年間の買戻し特約が主流。
参加者 債務不履行とは、お金を払わなかった場合ではないか。
市課長 第3者に移転する場合も法的に(買戻し特約の対象になり)妥当だ。
参加者 仮にデータセンター、物流センターができたとして、流星台に行くと、あの巨大な施設は圧迫感がひじょうにある。将来につながるものなのか。
参加者 買戻し特約は学校用地ならあり得るが、46ヘクタールを全部買い戻すのは大変。買戻し特約を付けても買い戻すことは非常に難しい。
副市長 土地利用方針に沿った土地利用を将来どう担保するか、担保の仕方の一つの方法として契約上で買戻し特約をするのも一つの方法だ。期間は10年間とする。基本は地区計画、都市計画で、将来的に(ばら売りされないよう)担保できる手当てをできるように考えていくことが必要。
参加者 日本は所有者の権利が強い。地区計画で禁止することは難しい。こういうふうに利用しなさいというのも、一括売却のものについて買戻し条項は現実的に不可能。一括売却を考え直さないといけない。
副市長 担保できないと言われちゃうと、法治国家の中で、後ははない。法的なものを根拠とする。
参加者 現実的に66億円の買戻しができるのか。実効性のない計画だ。
副市長 無理だといわれても、一つの方法として(買戻し特約が)ある。
参加者 であれば、できるというなら(説明の)資料として付けるべきだ。できるというなら資料に付けなければ説明にならない。実現しようとするのであれば、実現を担保しようとする資料が出るはずだ。
副市長 土地利用方針が定まってない中、まず土地利用方針が定まらないと先に進めない。
参加者 土地利用方針は一括売却でしょう。一括売却で話をしている。
参加者 結局どうしようとしているのか。
市長 今さまざまな自治体の調査をしている。地区計画も合わせてやっていく。法の下でさまざまな検討をしている。
参加者 陸上競技場が上郷にできていけばとてもうれしい。経済的なものはとても大事。(旧総合運動公園用地に)子どもの城をつくってほしいという願いはあるが、一括売却が一番、経済的にいい。担保を法的にやるならきちんとした文書に起こせる。安心できるためには文書に起こす、文書ができたら、有効に使っていただきたい。もっと費用対効果があれば提案してもらわないと進まない。
市長 財政に余裕があればいいが、そういう状況ではない。利子を少しでも減らす努力をしている。貯金をためて返済をなんとか終えて1億円ぐらい影響を減らす努力をした。しばらく寝かせて持っておくべきだという意見もあるが、今はそういうことをしている余裕はつくば市にはない。できる限り有効に活用していきたい。建物が建てば固定資産税も上がる。建物で3億数千万円は見込んでいる。税収を増やすためにやっているのではなくて、実現をしていくことが私の使命。
参加者 今日は(市民が市の)説明を聞く場なのか、市民の意見を聞く場なのかー。都市計画はものすごく大事。中根・金田台の物流施設はあの始末だ。用途を準工業地域に変更して(中根・金田台では)現実にそういうことが起きている。買い戻し特約をつけるということだが、66億円を積むのか。それこそつくば市の財政が大騒ぎになる。一括売却はものすごく危ない。
副市長 一括売却の優位性を話したい。土地利用方針に沿った内容できちんとした土地利用を図ってくれる業者が出てくるかを(つくば市が)いかに選べるかが大変重要。家を建てる時、角に電柱が建っている土地より、まっさらな土地の方がいい。真っさらな土地の方が参加してくれる事業者が多くなる。(事業者が)プランニングしずらい前提条件を取り除くことが、選択肢が広くなる。
参加者 この話はいつもつくば市単独で解決するストーリーになっているが、県とか、近隣自治体、国などに、この土地を一緒に使ってほしい、一緒に考えようという相談はしたことがあるのか。国レベルとして、首都直下地震の防災拠点の最前線基地として使えないでしょうかという相談を内閣府などにしたことはあるか。
市長 周辺自治体とはさまざま話をしている。陸上競技場について土浦市長と整備の可能性はどうですかと話をしたけれども、それぞれ議会の皆さんがいるし、土浦には土浦の計画がある。(自治体による)共同の整備は、広域でやろうとしてうまくいかないで、プロセスだけでものすごい年月が経っていることがある。複数の主体が一体となって整備するのは20年、30年かけられるのであれば、選択肢として有効。運動公園は県に整備してほしいと繰り返ししている。
参加者 国とは話をしてないのか。
市長 国とは防災拠点の話はしてない。
参加者 防災拠点とは限らない。民間にぽんと売却するのはもったいないという印象をぬぐえない。
市長 つくば駅前の財務省がもっている宿舎跡地(吾妻70街区)はかなり交渉を重ねて2段階の入札にすると、国と共同でサウンディング調査をしている。つくばの拠点となる場所を構築していく。夢物語を語ることは大事、いろいろな連携をしていくことも大事だが、前に進めていかなければならない。
参加者 (旧総合運動公園の活用方法について)国に話したことはないということか。
市長 国会議員に随分前に聞いてみたりした。国もなかなか新しい場所をつくっていく状況にはほとんどない。県にはいろいろ、知事とも話をしている。
参加者 一括売却して地域にとってプラスになる望ましい施設を整備するということだが、何が地域にとって望ましいのか分からない。それが示されないで一括売却すると言っている。駅前の公務員宿舎用地と違って、ここは研究施設用地だ。望ましいまちが何になるか分からないのに、あまりにも楽観的だ。
市長 できることをできる限りしていく。
参加者 市議会が特別委員会を立ち上げて、こういう視点でやってくれというのが民意だと思う。(一括売却を)進めていただきたい。市がやると伐採費も相当なお金がかかる。これだけ大きい面積になると(何かあった場合)業者は日本中で信頼を失う。(一括売却して)損はない。
市長 お金の件は最低価格を68億とし、市の財源になっていく。二元代表制であり、市議会の皆さんの話はすごく大事に思っている。市議会が提言としてまとめてくださった。市民25万人が満足するとは思っていない。総合運動公園の計画も(反対)8対(賛成)2だった。それぞれにそれぞれの思いがある。全員が納得できない状況は分かるが、私は前に進めていかなければならないという決意のもとにやっている。
参加者 今の、市長がおっしゃることが心配だ。ここにいる(参加者の)大人の人たちはそれで大丈夫なの?って思って控えめにお話になっている。市長さんに自信があればいいでしょうけど、そういう事業をやったことがない。そういうことを皆さんがひじょうに心配していることが分かりますか。そこのところをもう少し謙虚にお答えいただかないと、ご返答を聞いていて心配になる。
市長 この計画が完璧なものと言うつもりはない。方針案として出して、変えるところは一緒に改善していきたい。
参加者 市長が先ほど、議会は、議会は、とおっしゃっているので議会として一言、言いたい。特別委員会の提言書は作業部会の中で意見が分かれて、一括売却したほうがいい、しない方がいいという意見があって、一括売却すべきだということを議会では出していない。11月11日に方針案が示されて、これから議会がもんでいくのかと思ったら、次の週からパブコメをやります、(議員は)意見をそれぞれ特別委員会の中で出してください、パブコメで出してくださいとなっていた。こんな乱暴なやり方はおかしいと思っていたら、今度は(12月1日発行の)市報の1面で(一括売却の方針案が)出た。市報は2カ月前に内容を決める。(市長は)議会に丁寧な説明をして進めて参りましたというが、市はこういうやり方をずっと続けてきた。
市長 山中議員のおっしゃったことが議会の総意であれば、多くの議員が不満を表明すると思う。
参加者 (土地開発公社の契約書を一部書き換えて民間売却を可能にする)契約書の議案が(開会中の12月議会に)出ている。
副市長 (契約書の議案は)今ごろ出てくるのがおかしい、白紙撤回と同時に議決をしておかないといけない。
参加者 (契約書を書き換えると)民間に転売できるという内容も入ってくる。
参加者 民主主義で一番大事なのは約束を守ること。嘘を言ってはいけない、不確定なあいまいな情報も出してはいけない。五十嵐さんが最初に約束したURとの返還交渉も、一番大事なことは(情報開示された交渉の資料には)書いてない。URとの交渉はどうでもよくて、売りたくて売りたくてしょうがないのかな。(他の参加者から出た)全国レベルの話はそれ。46ヘクタールは研究学園都市にとって研究施設用地としてなくてはならない土地。つくば駅前の土地が高いのは研究学園都市というブランドがあるから。
参加者 広大な土地を市民としてどうやって保全し生かしていくか。一番大事なのは用途指定だ。46ヘクタールもあるのだから、それを変えればいい。用途指定で土地の値段が変わってくる可能性がある。(買戻し特約は)10年保証でなく、私たちは永遠に住んでいる。研究施設用地をURがつくば市に売ったことはおかしいと思う。時間かけてでも交渉していくべきだ。もともとそういうことで研究学園都市ができている。
参加者 土地開発公社が取得していた負担金は市が清算して今、銀行からの借り入れはないということか。それを市が取得しない理由はなぜか。
副市長 取得目的がないから。地方自治法上、取得目的がない取得はない。
参加者 では売却する目的はあるのか。
副市長 現在、土地開発公社の所有地になっている。運動公園用地なら市の方で取得する。
参加者 目的が出れば取得できるということか。今は目的がないから取得できないということか。
参加者 つくば市ではなく土地開発公社がもっているのは、つくば市が取得する場合、事業をやろうとしたときに国から補助金が出るから、ということを聞いている。市長と副市長が説明しないので付け足す。つくばは研究者のまちではないけれど、研究施設あってのつくば。研究施設の発展余地がなくなったらつくばは死んでしまう。
参加者 ここは研究学園都市に残されたいい土地、そこをまず使おうとしないで、売ろうということにひじょうに違和感を感じる。何で使おうとしないのか。使おうとするためには予算がいる。予算を確保できる案を出すべき。(市長が)何をやろうとしているのかわからない。お金がほしいというのが目的のようだが、そこの土地はそういう土地ではないのではないですか。
参加者 あそこが研究用地として活用できるのであれば、長い間残っていたのでしょうか。そこで(URは)つくば市に話をもってきた、URの現状を皆さんご存知のはず。これから市民が活用していくのは膨大な拠出になる。経済的に埋めていきたいという提案でよいと思う。ぜひ前に進めてほしい。(一括売却案以外の)提案があるならどんどん出してほしい。
参加者 研究用地の発展余地をもっているから研究学園都市であり続けられる。
□ □ □
参加者同士、怒鳴り合う場面も 第3回説明会
 第3回市民説明会の様子=12日、つくば市役所
第3回市民説明会の様子=12日、つくば市役所
3回目の市民説明会は、12日午前10時から市役所で開かれた。参加者同士が怒鳴り合う場面もあった。3回目の市民説明会の主なやり取りは以下の通り。
参加者 政治家は本当に信用できない。研究所を持ってこい、はあり得ない。66億で買って2億5000万の金利がかかった。固定資産税が年7000万無くなっている。こんなことを永遠にやっていては市民のためにならない。早く売却した方がいい。伐根伐採するだけでも46億円かかる。それをどこから金を出すのか。いつまでもいつまでもあーじゃこーじゃと言わないで、あんなもんは早く民間に売っちゃった方がいい。体裁だけ考えずにつくば市民のことを思うのであれば、早く売って子供たちのために使ったらどうか。
市長 政治家の一人として少しでも信頼を取り戻せるよう様々仕事をしている。研究所用地として使われなくてずっとそのままになっていた土地。研究所を引っ張ってくるというのは現実としては無いということ。これまでの土地のプロセスは、元々国がURに売却を求めた。URはつくば市に、買うか買わないか、買わないんだったらソーラー発電にするぞといって、つくば市は半ば慌てながら買ったということが(総合運動公園事業検証委員会の)報告書で示されている。財政にゆとりがあればうれしいが、とても遊ばせている余裕はない。就任して貯金を積み上げて(借入金の)土地代は払った。年間利子3000万円だけでも大きな負担だが、(利子を前倒しで返済したため)結果として1億円ぐらい市の財政にプラスになった。これから、どの事業も精査しながら来年度予算の査定が始まる。無駄なものを削って浮いたお金で市民サービスしないといけないということでやっている。今のような話(一括民間売却)でまとめていくのがつくば市にとって必要なことと考えている。
参加者 お金の面から売却がいいと言う話もよく分かるが、しかし住民として純粋な希望だが(配布資料の)この写真を見ても分かるように(旧総合運動公園用地は)緑が多くて貴重な土地だと思う。ここをどのように市民のために使うか、お金のことは置いておいて、純粋な希望として、今、市民が必要としているのは高校用地であったり、周辺小学校では生徒が増えてパンクしているので小学校をつくる案もあるだろうし、図書館も駅前の図書館は駐車場がないので子ども図書館であったり、ウオーキングコースやマラソンコースもある。地球環境を考えたとき、森をそのまま残すこと、お金をかけてもこの場所を守る方法もある。森林保全など環境関係で補助金をもらえる方法はないのかなと思う。
市長 私も木にこだわりを持っている。就任前に街路樹が伐採される計画があったが、残した。まだつくば駅周辺に街路木が残っている。そのままだったらほぼ木は残ってなかった。森林保全のお気持ちは理解する。しかし木として持っているだけでは森林保全にならない。この土地の南側の緑を少しでも残して、散歩コースであるとか(にする)。地域住民にとって貴重な緑だと思っている。しかし管理されていないので、すべての緑がいい緑だといえない。高校や図書館は市に必要な施設だ。高校は繰り返し知事に対し、つくばの高校対策をきちんとしてほしいという話をしている。ようやくいくつかの高校、まだ一つだが、定員を増加することをしてもらったりしている。小学校は人口試算をして、大穂地区は小学校が必要になる状況ではないが、数字を見ながらやっていきたい。図書館は十分でないという話をいただいているが、市に図書館を整備していく財政的な余裕はない。土浦市は20年くらいかけ、お金も総額で100億円近くかかったと聞いている。つくば市は10年後を目途に市としての図書館の方向性をつくっていきたい。いろんなご希望がある。お金があればかなえた。現実の制約の中でやるのが高エネ研南側未利用地。必要なところに必要な整備をしていく。
参加者 計画の中にスポーツ施設は入ってないのか。地域の活性化とは人が集まること、気軽に集まること、それはスポーツ施設。市原さんが総合運動公園を提案したとき説明会があった。いろんな話があった。プロ野球の2軍がくるとか。高校野球の県大会をつくばでやってほしい。土地を買い取りたいところがあるそうだが、ぜひスポーツ施設を盛り込んでほしい。
市長 サウンディング調査では(事業提案者が)全部で12件あった。そのうち1社からスポーツツーリズム拠点の整備という提案をいただいている。ただし土地を買うのではなく、つくば市から借りたいという提案なので、つくば市は土地を持ち続けなければいけない。公募の際、一括売却とする方針だが、もしこういう事業者が、買うとか手を挙げてくれればそういう施設の可能性もあるが、全部買い取りを希望する企業にスポーツ施設は入ってない。私もスポーツがもつ価値は大きいと思っている。そういう拠点がないというのがつくば市の大きな課題。今、上郷高校跡地に陸上競技場の整備を計画している。スポーツの重要性は私が肌で体験してきた。今後もできることをそれぞれの場所でやっていきたい。
参加者 民間の経済活動がくるとき、市が稼ぐことができるかを考えると、都市計画税、固定資産税が入ってくるが、法人税が市に入るかという視点も大事。つくば市で活動しても東京に本社があって税金は東京都に収めると市が潤うことはない。そういう視点も必要。雇用を生むこともつくば市の将来を考えると必要。そういうことも考えて経済活動する法人が必要。データセンターは、すごい電力がかかる。小型原発1機分くらいの電力を使う。これをやられるとSDGsの面から、日本は火力発電がメーンなので二酸化炭素排出量が増える。データセンター等、環境に悪い経済活動をする法人は入れないという視点も必要。
市長 市民サービスのために税収を確保することは重要だと思っている。法人税はつくば本社でなくても、働いている人の数によって税金が入ってくる。東京本社の大きな企業から、つくば市に法人税をいただいている企業もある。(旧総合運動公園用地の売却は)法人税の収入にもつながる。大きいのは働く場ができること。物流施設ができると6000人くらいの雇用を生み出すことができるとサウンディング調査の企業から聞いている。雇用を生み出すことは地域活性化や地域が持続可能になるのに重要。環境への配慮は重要。公募してプロポーザルで審査する。環境への配慮がどうされているかも審査の評価対象に入ってくる。もくもくと煙を上げて環境を汚す企業がつくられることはない。多くの企業が環境に配慮して持続可能な事業をしないと企業価値を下げる。ただデータセンターがダメとは申し上げていない。
参加者 もう一度、ここの土地の原点に戻ってみたい。(配布資料の)土地利用方針の三本柱だが、「敷地の一体的整備」は異存ない、「公的利活用」もいい、「用途地域変更」だが、現在、利潤を上げなければ使えないような用途地域にしようとしている。今は研究開発用地(第2種住居地域及び第2種文教地区)だから、そこを変えてしまって、お金の問題になっている。市長さんは、研究学園都市という世界でまれな都市の市長さんになったのだから、そこまで考えていただきたい。(第1回、第2回の説明会で)用途地域や法律で縛ろうという話があったが、つくば市はそういう方法で土地の管理ができていない。農地も(用途、法律で)整備されていない実績がある。1社で購入すれば、つくば市に対して1社が対応する。つくば市は対応できない。一番心配しているのは、資本系列を調査しているのか。外国資本は欲しがる。(資本系列などを)まだ調査してないとしたら自分たちは満足に土地を扱えないということ。やるならきちんと調査すべきだ。もともとはURから高価な買い物をしてしまったことがある。つくば市が損害を受けた、市民が損害を受けたということ。今のままでいくと、もっと大きな損害を受けることになる。研究用地の需要がないとおっしゃっているが、あなたが(市長が)そう思っているだけ。例えばDX(デジタルトランスフォーメーション)をみても、中心的にやる研究所が必要。日本は技術を下で支える教育がされてない。日本は給料が安いから。そんな状況を変えようと思わなかったら研究学園都市ではない。
市長 研究学園都市としての使命を捨てることではない。
参加者 (市長の言うことが)理解できない。
市長 この土地についてはこういう利活用をするということ。つくばのショーケースとなる場所がないということに対しては、つくば駅前(吾妻70街区)につくるよう、国とサウンディング調査をやっている。DXの人材が足りてないことは明らか。私もさまざまな関係者とそういう話をしている。原点に戻ると言う話だが、研究学園都市の使命は人類に貢献することだと思っている。(つくば市は)それぞれの事業を通じてモデルをつくってやっている。この土地がなくなると研究学園都市の使命を果たさなくなるということはない。(発言者が)現役でいらっしゃったときと国の方向性が違っている。国と話ができればという状況にはなってない。
参加者 今のようなことを常識と考えていることがおかしくないかと言っている。
参加者 五十嵐さんは市民無視の政治を改めると言って市長になった。市報とかわら版で情報発信しているが、これだけ大きな問題になるといろいろな角度からの検討が必要だ。情報共有、対等な議論、少数意見を見逃さないことが必要。少数意見は、どんな革新的な意見も最初は一人だから。市報は民間のちらしと一緒に宅配(戸別ポスティング)されている。宅配でちらしを入れようとしたが、政治のちらしはだめだと断られた。やむなく折り込みで入れた。新聞を購読している人は半分しかいないので、新聞折り込みでは市民からの情報はなかなか伝わらない。市民や議員が対価を払った上で、意見広告などを(市報と一緒に)宅配できるようにしたらどうか。五十嵐さんは名誉棄損で市民を訴えているので、お互いに誤った情報を出さないようチェックしてもらってもいい。市の広報と一緒に市議会議員の広報とか、市民の意見とかを(宅配で)入れていただきたい。情報の共有と対応な議論、少数意見の尊重をぜひ実現させてほしい。
市長 政治のちらしがダメということはないと思っている。私もちらしの折り込みをお願いしてきた。事業者の判断を行政から言うことはできない。情報共有や対話は重要。情報量は市役所の方が多い。双方向で対話しながら進めている。(双方向の対話は)就任以来、一貫して続けている。(市民の意見広告などを)行政の広報と一緒に配布するのはなかなかハードルが高いのかなと思うが、皆と直接お話をすることを続けていきたい。情報が基本というのは大事にしながら取り組みを進めていきたい。
参加者 子供たちとか市民が気楽に使える用途にしたらいいんじゃないかという話があったが、子供たちを育ててきて、将来を見据えて子供たちが楽しめる場所があったらいい。つくばは小さい子が雨の日に行く場所がない。民間のゲームセンターがいっぱいだったりする。防災備蓄とあるが、トレーラーハウスとかキャンピングカーがいっぱい置いてあって、万が一のときは仮設住宅になるなどを民間に提案していはどうか。子供たちが気楽にのびのび遊べる場所が拠点としてあればいい。
市長 私も子供が4人いる。雨が降ればショッピングセンターにはあまり連れて行きたくないし、どうすればいいか苦労してきた経験がある。(雨の日に遊べる場所は)つくば市に必要だと思っている。最近は泥だらけになって遊べばいいかなと思っている。つくば市にはプレイパークがある。泥だらけになったり、全身を使って遊べる場所を順次整備していっている。(サウンディング調査には)賃借だが、道の駅、農業自然体験エリアなども提言としてある。どうなるかは別として、子供たちが全身を使って遊べる、元気に過ごせる場所が必要。どういう場所がいいか、現役の子育て世代として、意見として承る。
参加者 2,3年前、神栖の防災・多目的施設(かみす防災アリーナ)を見たことがある。アリーナみたいだったら子供たちに開放してスポーツに使える。46ヘクタールのうち、市が使えるのは4ヘクタールというのは狭いのではないか。その中にスポーツ施設があればいい。神栖の施設はカフェがあって皆が集まれる場所だった。
市長 神栖の防災アリーナはかなりの金額がかかる。現時点ではアリーナや体育館をつくることは想定してない。芝生の広場になる。上物(うわもの)の建設は考えてない。体育館をつくると数十億の整備になる。テニスコートは、つくば市は市内各地に整備されている。きちんと補修しながら皆さんの使いやすい環境にしたい。公共投資はあまりにも過大になる。
参加者 市の方では一体的な整備でやっていくということだが、公的活用は意外とできる部が広がると思っている。引っかかるのは利益追求だ。民間活用についてサウンディング型調査をしているということだが、そういうやり方もあると思うが、先のことを考えると、何のための利益追求か、何のためにお金が欲しいかがあいまいだ。他市ではブランデングを一生懸命進めて、生き残れる施策を練っているところがある。目先で、民間に任せて利益を上げるのではなく、もう少しブランディングを考えて、つくばならではのものを生かして何かやっていけないか。一次的な利益でなく、つくばならではの強みを生かす活用方法をぜひ考えてほしい。つくばは他の自治体と比べてやりやすい思う。
市長 利益を追求しているわけではない。これまでの過程が重要だ。ここに地域活性化のお題目で305億円の事業が計画されていたのを、住民がそれは違うと結論を出した。陸上競技場が(旧総合運動公園用地に)つくれないかと検討したが、最終的には上郷高校跡地になる。つくばだからこそ4社が(一括購入に)手を挙げてくれたんだろうと思っている。つくばは様々な取り組みをしているおり注目度が高い。そういった意味でつくばの特性を生かしたものになる。公共で全部整備していくのは現実的には不可能。決してお金のことだけを考えて言っているのではない。つくば全体にとってプラスになるものだと思っている。
参加者 土地利用方法の決定をこれから進めるということだが、市長の説明は防災拠点にしていくことだけ。あとのことは、全体としてこうしたいという説明がない。一括で土地業者に買ってもらうにも、土地業者任せの利用方法になっていくのではないかと不安。インフラ整備が必要になることは総合運動公園でも問題になった。もともと研究施設用地として計画されていた。商業用地や事業用地として活用されていくことや、408号の共同溝や下水道を想定したことはなかった。歩道も、左折車線をつくるため、歩道を壊さなければ左折用地がつくれない。インフラ整備がネックになるのではないか。
市長 今示しているのは土地利用方針案。先日も(市は)何をしたいか分かっらないという話があったが、従来であればこうした説明会は開かない。すっと延ばして、こういうことが決まりましたというところで説明会になる。事業計画が決まった際も説明会を開催して、より具体的な提案をしたい。次のプロセスでより具体的な話ができると思っている。インフラ整備や道路をどうしていくかは、事業者が実際にどうしていくのか、地区計画の協議で進めたい。
飯野副市長 道路拡幅とか408号線の右折、左折帯をつくるのは、どういう事業提案があっても必要になる。もっと具体的に、道路幅員をいくらにするとか、408号だけでなく西側のアクセスをどうするか必要になる。事業者提案によって発生する交通量が決まってくる。物流倉庫なら大型トラックとか勤務する従業員の車とか。事業が決まったら推計をして、それをもとに決める。現段階ではどういう土地利用がされても必要となる道路などを(方針案に)示している。
参加者 基本はこの土地の取得のいきさつが間違って、相当高い金額できていること。つくば市の負の遺産だ。いろんな意見があるが、お金があればつくば市はどんなことでもやってくれる。問題はお金がないから売るしかない。自分の懐を傷めないで、あーじゃこーじゃと同じことをやってもしょうがない。売れば固定資産税が3億ぐらい入ってくる。早めに処分した方がいい。今は7000万円の固定資産税が入ってこない。カネがなければ売っちゃえばいい。基本はカネ。カネがないから売るしかない。
参加者 観光ボランティアガイドで県内ほとんどを歩いている。つくば市の評価を聞くと、つくば市は頭脳都市だという評価。すばらしい評価がされている。
参加者 お金の問題だということだが、お金がないから苦労されているのは分かっている。しかしお金を確保するにはいろいろな方法がある。一つはURとの交渉が中途半端で終わっていること、一つは研究所だが、皆さんに声を掛けてどうしたらいいだろうかと考える機会をつくってはどうか。そういうことも試みていない。あれだけの土地を利用する計画はそう簡単につくれない。一括で売ってしまうとそういうことはできない。そう簡単に売ることをやっていただいては困る。市は収益を上げなければならない土地をもっていいいことにはなっていない。市が買った結果(URと)裁判をすることまで考えられたのですよね。五十嵐さんは5年間苦労されたが、今のような心配なことばっかりある形で進んでいいいのかな。1社に売るときいろいろな条件を付けたとしても、つくば市は実行させたことがない。用途変更、こんな簡単なことですらやってない。ましてや相手は資本系列が外国じゃないの?そういう確認はしましたか。
五十嵐 サウンディングにきた会社は分かっているが、明かせない。
参加者 何をやりたいかわからない。つくば市として何を実現したいのか。借金を返したいだけなのか。防災用地を借りるのに費用がいくらかかるかも聞けない。皆さん、それを聞けないから、いろんなこと言う。防災用地をつくるなら、お金がかからないで済む用途にして(市が)もっているべき。
参加者 3回出席して、3回で明らかになったことは、URとの交渉が十分でないこと、つくば市が何がほしいのかが明確でないこと、一括売却に伴う不安要素として土地利用が将来にわたって保証されるのか明確でないことだ。お金のことはその通りだが(将来、旧総合運動公園用地が)国レベルの新しい研究分野のためのスタートアップ支援拠点になるかもしれない。そのことを国が分かれば66億出してくれるかもしれない。その辺の交渉をやった方がいい。
以上
※3回目の市民説明会の主なやりとりを、12日付で追加しました。




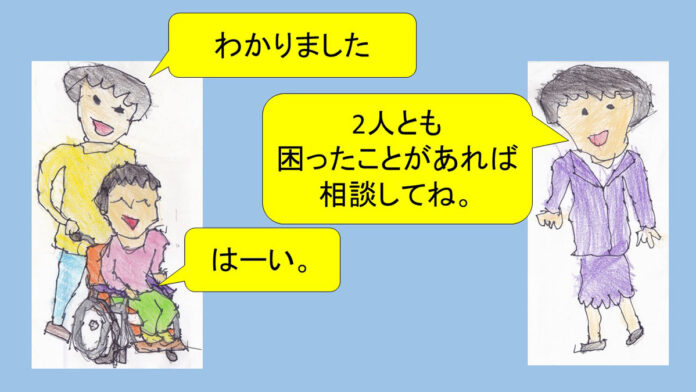


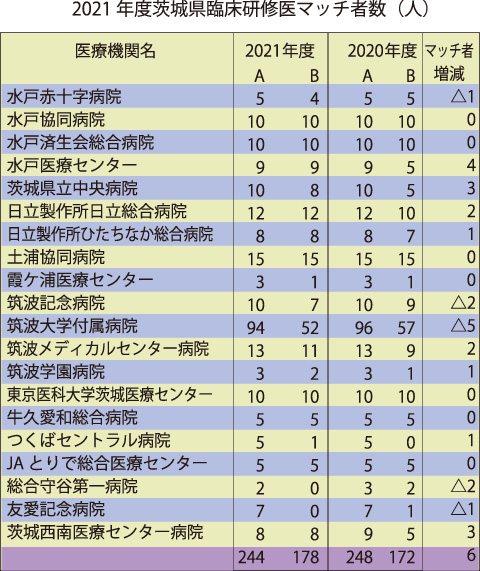

















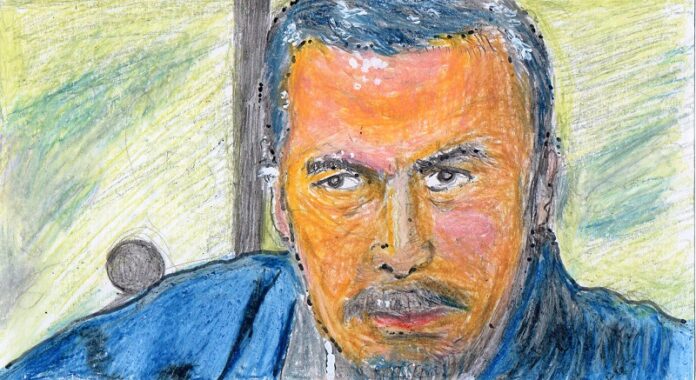


![塚本一也 18[7980]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/12/9deddef5caab252451c910c03c66fed8-696x392.jpg)