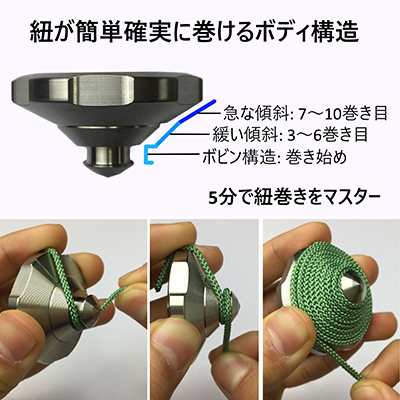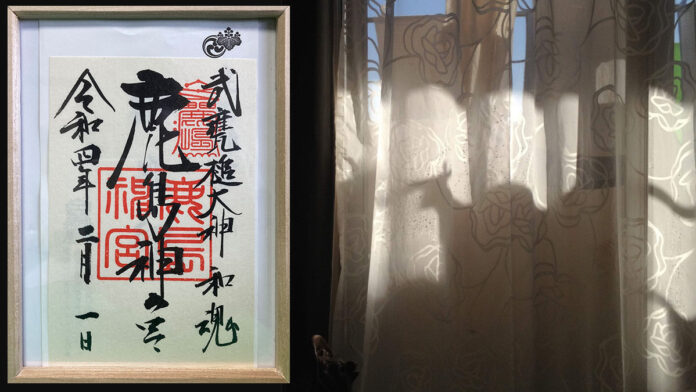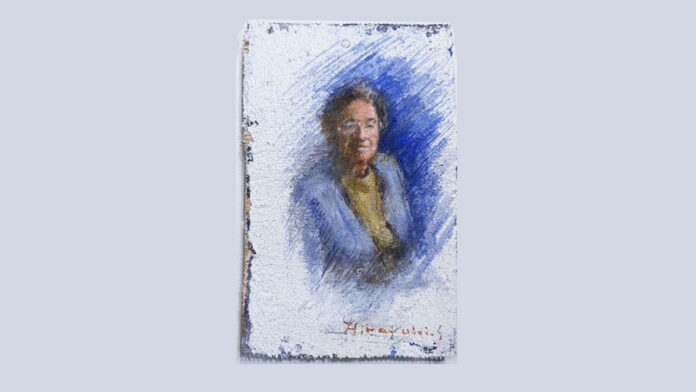つくば市議会3月定例会が14日開会し、五十嵐市長は新年度の施政方針を述べた。不登校学習支援委託事業者の選定をめぐって、保護者会が事業者の継続を要望している問題(1月20日付)について触れ、「結果として、現在の利用者や保護者に多大な不安を与えてしまっている」と話し「今後決して同様の事態を招かないために私自身が深く反省し、寄り添う市政という心を全庁に徹底的に浸透させていく」などと述べた。
昨年12月に市が公募した委託事業者のプロポーザルでは4社が応募し、現在、不登校児童生徒の学習支援をする「むすびつくば」を運営するNPO法人リヴォルヴ学校教育研究所が次点になり、別の民間事業者が1位に選定された。
選定について五十嵐市長は施政方針の中で「さまざまな事情を背景に学校に通えなくなっていた子供たちが、ようやく自分の居場所を見つけることができたにも関わらず、事前の周知もなく突然、実施主体が変更されることを知らされ、不安な状況をつくってしまった原因は、寄り添う市政の徹底を実現できていない私のまぎれもない力不足であり、子供たち、保護者の皆さまに本当に申し訳なく思っています」と謝罪した。
一方、具体的にどうするかについては「現在、保護者、関係者から意見をいただきながら子供たちの不安を何とか解消できるように努力をしているところ」と述べるにとどまった。
2050ゼロカーボンシティを宣言
新年度の市政運営の所信については、新型コロナ対応を最重要課題として自宅療養者への物資支援、市独自のPCR検査などをする、科学技術都市つくばの強みを生かしスーパーサイエンスシティ構想の実現を引き続き目指す、中心市街地ではつくばセンタービルのリニューアルの一環で新たな市民活動拠点の整備を進め、周辺市街地では空き店舗を活用したチャレンジショップの開設や地域振興を担う人材発掘に取り組む、誰一人取り残さない社会を実現するため生活困窮者自立支援、障害者の日常生活と社会生活の支援、子どもの貧困対策、高齢者の買い物支援などに取り組む、教育ではスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、学校サポーター配置を充実させるなどと話した。
さらに2050年までに二酸化炭素排出量を実施ゼロにする「ゼロカーボンシティ」を目指すと宣言した。国は2020年10月に、2050 年までに二酸化炭素の実質排出量をゼロにするカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言している。
低炭素社会の実現に向けた新年度の具体的施策としては、宅配便の再配達回数を減らし二酸化炭素排出量を削減するため集合住宅の所有者に宅配ボックス設置費用の一部を補助する、家庭から排出される生ごみの減量と自家処理を目指し電気式生ごみ処理機やコンポスト購入費の一部を補助する、リサイクルのさらなる促進のためプラスチックごみの収集回数を現在の月2回から月4回に増やすーなどを挙げた。(鈴木宏子)