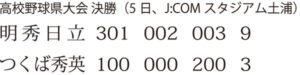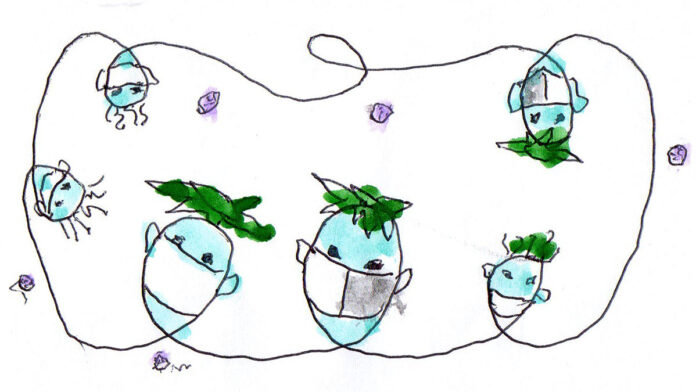つくば市二の宮にある茨城県営の都市公園、洞峰公園(約20ヘクタール)をめぐって、県が民間事業者に委託してリニューアルする計画(洞峰公園整備運営事業)を立てているのに対し、つくば市が異議を唱えている問題(4月14日付)で、市と県のやりとりがNEWSつくばの情報開示請求で分かった。
市民の公園か 県民の公園か
洞峰公園の位置づけについて市は「開業当初から現在まで、つくば市民をはじめとした周辺住民に利用されている」などと利用実態を強調し、県の今回の事業コンセプトは「県外を含む広域から新規来園者を取り込むこと」だと指摘した上で、「長年にわたり周辺住民のための憩いの場であり、緑豊かで穏やかな住環境を支える役割を担ってきた公園の意義・形態を著しく損なう」「質疑事項や懸念点が改善されない限り、実現は難しいとの立場をとらざるを得ない」などとしている。
これに対し県は「研究学園都市建設で複数整備した公園を県と市が分担」してきた中、「洞峰公園は、広く県民に利用される広域的な公園として県が管理してきた」とし、「開園から40年以上が経過し、今後、老朽化施設の改修や巨木化した樹木の伐採など多額の費用がかかり、これまでと同様の維持管理の費用確保が困難」だとした上で、民間による公園リニューアルへの期待として、維持管理費の県負担の軽減、老朽化する公園の魅力創出と利便性向上をあげ、県全体で取り組む「コロナ禍での新たな観光・楽しみ方として、アウトドアを活かした観光誘致の取り組みの一環」であると述べる。
さらに五十嵐市長が4月の記者会見で問題だとしたグランピング施設とバーベキュー施設の「周辺に対する臭いやアルコールなどの懸念」に対して県は、臭いについて「ふた付きの高級ガスグリルを使用するため煙やにおいが周囲に拡散することはほとんどない」「炭を使用するレンガ造りのバーベキューコンロも併設する計画だが、煙や臭気が出にくい、ナラ炭、クヌギ炭、オガ炭を採用するなど対応を検討する」とした。アルコールについては「飲酒は所定の場所で楽しんでもらうことを促す」「飲酒マナーが悪い人にはスタッフが注意する」「夜9時以降は『サイレントタイム』として静かに過ごしてもらうよう案内する」などと回答している。
洞峰公園リニューアルをめぐるつくば市の質問(21年12月28日)と、茨城県都市整備課長の回答(22年2月7日)の概要は以下の通り。
Ⅰ. 周辺住民や既存利用者への対応について
1, 市 グランピング施設やBBQガーデンについて、既存の公園利用者や周辺に住む人たちが本当に求めている施設かどうかについてのアンケートや調査及び設置に当たっての住民説明などを行い、理解・合意を得る必要があるのではないでしょうか。
県 アンケート調査については、年に数回、定期的に実施している中で、飲食施設を充実してほしいとの意見が毎年挙げられています。本公園は近隣の市町村をはじめ、県内外からの来園者が訪れる県営都市公園であることから、公園のホームページや新聞・広報誌などにより広域的に周知します。また、公園内に施設計画を掲示し利用者に周知すると共に、公園隣接者に対して説明を実施します。
2, 市 公園内での飲酒や喫煙等による風紀の乱れや交通の集中により、良好な住環境が害されるリスクをどう阻止するのでしょうか。
県 飲酒については、飲酒施設の所定の場所で楽しんでいただくよう促します(後述18)。喫煙については、現在も保健所の指導に基づく園内指定の喫煙所以外は禁煙としており、喫煙者には引き続きマナーを守っていただきます(後述13)。交通の集中については、新規施設が集まる南側駐車場は拡張を予定しており、交通集中への対策を実施しております(後述22)。
3, 市 既存の公園施設が多用途に変更されることにより、長年利用されてきた公園本来の機能が削られ、公園本体の目的であるレクリエーションや健康増進活動の場が縮小することは問題ではないでしょうか。
県 新規施設の配置場所については、既存の公園利用者の利用状況を勘案したうえで、影響を最小限に抑える計画としています。特に、多くの既存利用者でにぎわいを見せている多目的フィールドや水と緑の広場、園路、体育館、プール棟、テニスコート等については、一切改変しない計画としていることからも、既存のレクリエーションや健康増進活動の場は維持できているものと考えます。
4, 市 十分な合意形成なく事業が遂行されれば、クレームの大半はつくば市に殺到し、市として対処を求められることになるが、県はこうした状況にどう対応するのでしょうか。
県 本公園に関するクレームやご意見に関しては、公園管理者及び県が対応しますので、市に連絡があった際は、公園管理事務所または県の連絡先を伝えていただくようお願いします。
Ⅱ. グランピング施設について
5, 市 つくば市の施設では、土日・祝日の野球場等の予約が取りにくい状況となっています。洞峰公園においても、土日・祝日の野球場利用者は多い状況です。この施設を閉鎖してグランピング施設に改修することにより、既存利用者及び周辺住民から野球場を利用した活動機会を奪うことは問題があるのではないでしょうか。
県 野球場については年間稼働率が1割程度で、このうち、つくば市内の方の利用が3割程度となっています。また、定期的に利用している団体がいないことから、よりニーズの高いドッグランなどに改変することで、この場所をより有効活用できるものと考えています。なお、つくば市が管理する公園の野球場でも、過去に多目的広場へ転用している事例もあることから、大きな問題はないものと考えております。
6, 市 グランピング施設について、既存の野球場フェンスや低木などでエリアを明確にするということですが、それでは、セキュリティー面について問題があるのではないでしょうか。セキュリティー面が脆弱(ぜいじゃく)な施設を安易に設けることにより、犯罪を誘発することが懸念されていますが、どう対処するのでしょうか。
県 全国で展開されているグランピング施設の先行事例を参考にしながら、セキュリティー面への配慮として、グランピングエリアのフェンス・植栽による区画のほか、機械警備システムの導入を行う計画です。なお、夜間に不審者がグランピングエリアに侵入した場合には、直ちに警備会社に発報され、警備員が現地に急行することとしています。
7, 市 植栽エリア境界を設けた場合、園路の交差点等の見通しが悪化し、ランニング利用者や自転車、子供等が衝突事故を起こす危険性が高まるのではないでしょうか。
県 グランピング施設のエリア境界は、現在野球場を囲むように連続設置されているフェンスの位置(園路から奥まった位置)を想定しているため、園路利用者の見通しが悪化し、衝突事故の危険性が高まることはないと考えています。
8, 市 グランピング施設の管理人が不在の時間帯があり、機械警備システムの導入などで対応するとのことですが、トラブルが発生した際には問題があるのではないでしょうか。管理人不在時のトラブルには、誰がどう対処するのでしょうか。
県 不審者の侵入が確認された場合には機械警備システムが発報し、警備会社の警備員が直ちに現地に急行するとともに、運営スタッフに連絡が入り、必要に応じて運営スタッフが現地に急行する計画としています。先行事例においても同様の取り組みにより大きなトラブルが生じたことはありません。
9, 市 プライベートデッキのトイレ・風呂の排水はどのような計画となっていますか。
県 グランピング施設の各宿泊棟には、新たに排水管等のインフラ設備を敷設する計画です。今後、施設計画の設計を行った上で、詳細については下水道管理者と協議します。
10, 市 宿泊施設である場合、つくば市ラブホテルの建築等規制条例が適用されます(質疑事項ではありません)
県 条例に従って対応します。
Ⅲ. BBQガーデンについて
11, 市 BBQガーデンと遊具スペースが仕切られていないと、飲酒者と非飲酒者でトラブルが発生するのではないでしょうか。
県 BBQガーデンの各サイトは建屋となっており、BBQ利用者と公園利用者が接触する機会はないものと考えております。今後、設計業務の中で、必要に応じてBBQエリアを区画するフェンスの設置や植栽等による目隠し等についても検討します。
12, 市 BBQガーデンからの臭いや煙の拡散は、植栽や樹木による吸着を図るだけでは防ぐことはできません。有効な防止策はあるのでしょうか。
県 BBQガーデンは、高級ガスグリル(蓋つき)を使用することとしており、煙や臭いが周囲に拡散することはほとんどありません。また、レンガ作りのBBQコンロ(炭利用)も併設する計画ですが、煙や臭気が出にくい炭(なら炭、くぬぎ炭、オガ炭)を採用するなどの対応を検討します。
Ⅳ. グランピング施設・BBQ施設の共通課題について
13, 市 公共の場は喫煙を制限しているケースが多いですが、飲酒を伴うと喫煙を抑制することは難しくなるのではないでしょうか。飲酒を伴わなくても、長時間滞在するBBQやグランピング利用者に対して喫煙を禁止しても、実質的には遵守させることは不可能ではないでしょうか。公園利用者への副流煙の問題をどう解決するのでしょうか。
県 現在も、保健所の指導に基づく園内指定の喫煙場所以外では禁煙としており、今後も同様のルールを徹底します。なお、新設するグランピング施設、BBQガーデンにおいては、施設内は原則禁煙とし、喫煙者を確認した場合には、スタッフが注意喚起します。
14, 市 屋外施設である以上、煙や臭気の拡散は不可避です。洞峰公園は幼児から高齢者まで幅広い年齢層の憩いの場であるとともに、ウオーキングやランニング等による健康増進を目的とした利用者が多く、緑の中で憩いのひと時を過ごす人にとって、また呼吸器に負荷のかかるランニング等の運動中の人にとって、臭い・煙は極めて不快なものです。タバコの副流煙やBBQの煙・臭気等が、公園利用者のレクリエーションや健康増進活動を阻害し、公園本来の設置目的が損なわれることは問題ないのでしょうか。
県 たばこの副流煙については、前述(13)の通り、現在も、保健所の指導に基づく園内指定の喫煙所以外では禁煙としており、今後も同様のルールを徹底します。なお、新設するグランピング施設、BBQガーデンにおいては、施設内は原則禁煙とし、喫煙者を確認した場合には、スタッフが注意喚起します。BBQの煙や臭いについては、前述(12)の通り、BBQガーデンは、高級ガスグリル(蓋つき)を使用することとしており、煙や臭いが周囲に拡散することはほとんどありません。また、レンガ造りのBBQコンロ(炭利用)も併設する計画ですが、煙や臭気が出にくい炭(なら炭、くぬぎ炭、オガ炭)を採用するなどの対応を検討します。
15, 市 グランピング施設やBBQガーデンの利用に伴う費用は高額で、利用者は県外の人がメーンと想定されます。地域住民や既存利用者に親しまれている活動の場・憩いの場を削ってまで、県外を中心とする地域外の人のためのレジャーの場を新設することの意義は何でしょうか。
県 グランピング施設やBBQ施設の利用は、県外の人をメーンとしている訳ではなく、県内・市内の方々にも広く利用いただきたいと考えています。また、カフェ施設やカフェスタンドなど、既存公園利用者にも気軽に利用いただける施設も計画しています。
16, 市 グランピング施設やBBQガーデンを整備することにより、にぎわいを創出するとありますが、洞峰公園及びその周辺は文教地区に指定されており、文教的環境の保護に相反するのではないでしょうか。過去15年間につくば市に寄せられた「市民の声」を見る限り、洞峰公園周辺の騒音対策や渋滞対策、近隣から漂う野焼き等への臭気への対策を求める要望は多数ありますが、この地域に新たな賑わいを創出する要望は皆無です。この地域における「賑わいの創出」を求めているのは誰なのでしょうか。
県 文教地区(周辺住宅環境)への配慮については、野球場周辺エリアの位置であれば南側が気象研究所であり隣接する建物がないことや、西側・北側の住宅地までは200メートル以上離れていることから、騒音問題など住居の環境を害するおそれはないものと考えています。本公園は近隣市町村をはじめ県内外から来園者が訪れる広域的な公園であり、公園利用者アンケートなどでも飲食機能の充実など、にぎわい施設を求められています。また、県全体としてコロナ禍の新たな観光の楽しみ方として、アウトドアを生かした観光誘致に取り組んでいます。
17, 市 警官の保護、火災の延焼の防止の観点から、樹木の保護は重要であると考えますが、グランピング施設やBBQガーデンの整備、南側駐車場の拡張に伴い、樹木の伐採は行われるのでしょうか。
県 樹木の保護については、開園から40年が経過し、巨木化している樹木があることから、専門家の意見を聞きながら、樹木が密集してうっそうとしている場所など計画的に伐採し、良好な樹林環境を維持していきます。南側駐車場の拡張は、現状及び将来の駐車場不足問題の解消と新規施設へのアクセス向上のため必要不可欠と考えており、計画と合わせて必要最小限の樹木を伐採します。
Ⅴ. 飲酒・アルコールの提供について
18, 市 酒気帯び者がスポーツ施設エリアを通過すること等により、公園利用者が不快に感じることのないよう、飲酒に関するルールを設けるべきではないでしょうか。また、具体的にどのようなルールが設けられるでしょうか。
県 飲酒については、各飲食施設内や椅子・テーブルが置いてある所定の場所で楽しんでいただくことを促します。飲酒に関するルールとして、以下を徹底します。①公園内でのアルコールの販売時間は18時までの計画となっています。(レストラン、カフェ、カフェスタンド)②飲酒マナーが悪い方にはスタッフが注意します。飲酒マナーが改善されない場合、販売時間の短縮や販売数の縮小を検討します。
19, 市 飲酒マナーの悪い方への周囲が必要な際、管理人不在時は対応できないのでしょうか。その際、どのように対処するのでしょうか。
県 BBQ施設は18時30分、レストランは20時で閉店します。グランピング施設は、早朝6時〜深夜23時頃までスタッフが管理棟に常駐する予定です。宿泊者に対してはチェックイン時に注意事項として、夜間21時以降は「サイレントタイム」として静かに過ごしていただけるよう案内します。選考事例においても同様の取り組みより大きなトラブルが生じたことはありません。
20, 市 酒類の提供方法については、事業者が変わった場合でも引き継がれるのでしょうか。
県 本計画の事業期間は20年間であり、原則、事業者は変わりません。酒類の提供方法を含めた公園施設の管理運営については、事業者が変わる時点において、新しい事業者と県で施設継続の必要性や運営方法等を検討・協議し、継続しても問題ないと県が判断すれば引き継がれることになります。
Ⅵ. 駐車場その他
21, 市 駐車場127台増で周辺渋滞解消とした根拠は、どのように算出したものであるか、詳細をお示しください。
県 現指定管理者から、行楽シーズンにおける本公園駐車場への待ち渋滞状況(多くても10台未満)をヒアリングしたうえで、127台の台数拡張を行えば、新規施設への新規来場者の車両台数を考慮しても、現状の駐車場不足問題の解消につながると考えています。なお、駐車場台数127台については、駐車場拡張範囲や新規施設へのアクセス向上なども考慮の上、最大限確保できる台数として設定したものです。参考までに、グランピング施設は宿泊棟18棟あり、定員は最大6名/棟の想定。1団体あたり2台の駐車場利用とした場合、最大で36台となります。また、BBQ施設は10サイトあり、定員は最大6名/サイトの想定。1団体あたり2台の駐車場利用とした場合、最大で20台となります。これらを合計すると、最大でも60台程度の駐車場利用となりますが、127台の駐車場拡張により、十分に余裕を持った駐車場台数となると考えています。
22, 市 駐車場127台増で周辺渋滞解消とした根拠は、どのように算出したものであるか、詳細をお示しください。
県 県指定管理者から、行楽シーズンにおける本公園駐車場への待ち渋滞の状況(多くても10台未満)をヒアリングした上で、127台の台数拡張を行えば、新規施設への新規来場者の車両台数を考慮しても、現状の駐車場不足問題の解消につながると考えています。なお駐車場台数127台については、駐車場拡張範囲や新規施設へアクセス向上なども考慮の上、最大限確保できる台数として設定したものです。参考までに、グランピング施設は宿泊棟18棟あり、定員は最大6名/棟を想定。1団体当たり2台の駐車場利用とした場合、最大で36台となります。またBBQ施設は10サイトあり、定員は最大6名/サイトの想定。1団体当たり2台の駐車場利用とした場合、最大で20台となります。これらを合計すると、最大でも60台程度の駐車場利用となりますが、127台の駐車場拡張により、十分に余裕をもった駐車場台数となると考えています。
23, 市 市外・県外からのマイカー利用者が増えることにより、周辺の交通渋滞が悪化するのではないでしょうか。
県 グランピングやBBQ施設などを新設することにより、マイカー利用者が増えることが想定されますが、南側駐車場を127台拡張することで、22で前述したように駐車場不足による周辺の交通渋滞が発生する可能性は低いものと考えております。
24, 市 BBQ場やグランピング施設は、チェックイン・チェックアウトの時間帯に車両の出入りが集中する特性があるため、駐車場台数を増やしても同時刻に多数の車両が集中して渋滞が発生することは避けられず、周辺渋滞悪化は必然的であると考えられますが、どのような対策を行うのでしょうか。
県 チェックイン時における車両の集中については、他のグランピング・BBQ施設の先行事例からも、利用者ごとに来場時刻は異なるため、すべての利用者がチェックイン時刻に同時に来ることは考えにくいと思われます。
25, 市 BBQ場で飲酒した利用者が、駐車場の車内で長時間休憩してスペースを占拠することで、他の利用者の駐車場利用に支障が生じたり、混雑が発生したりするのではないでしょうか。
県 駐車場台数は十分確保してあるので、他の公園利用者の駐車スペースに影響を与えるものではないと考えます。また、他の駐車場利用者に迷惑をかける行為を確認した場合などは、スタッフにより注意喚起することとします。
26, 市 24時間営業のトレーニングジムの管理体制はどのように考えているのでしょうか。
県 警備体制については、警備会社と連携し入退館の管理や、室内に非常ボタンを設置することで非常時は駆けつける体制になります。日中の洞峰公園の体育棟が開いている時間帯は、スタッフが管理します。夜間のスタッフ不在時間帯は警備会社が管理します。入退場に利用者登録されたIDカードを使用するため、利用者・時間を特定できるようになっています。
これ以降の県・市対立の動向については(下)で報じる。(柴田大輔)









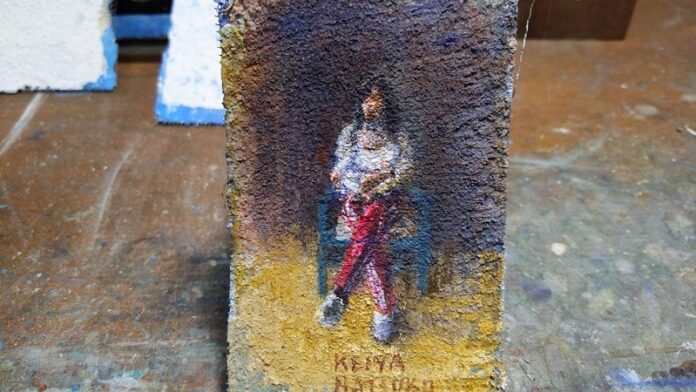





![horikoshi[1]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2020/02/horikoshi1.jpg)