【コラム・奥井登美子】結婚して土浦の家に来て驚いたのは、本宅と呼ばれていた我が家が親戚中の行事をすべて統括し、まかなっていた。今の業務に例えれば、健康保険、介護保険、年金機構、生命保険に相当する仕事である。昭和の初めまで、それらすべてに相当する仕事を本家が負担していたらしい。
私は、仕事をしている以上、社会保険に入るのが当たり前と思っていたので、奥井薬局として入ることを勧めてみた。
私の主張に対して、親戚の人たちがたくさん押し寄せてきた。昔から本家が中心で、病気のときも本家が面倒をみる。それが奥井家の美徳なのだから、そういうことを言い出す嫁は許せないという。私が親戚の人たちと対立するたびに、誠一兄がすっ飛んで来て、間に入って親戚たちを説得してくれた。その時も、社会保険に無事入ることができた。
兄は親戚の業務を遂行する長男として、次男、三男とは食事の中味まで、特別のものにして大切に育てられたという。こともあろうに、その兄が1967年、45歳の若さで亡くなってしまった。
結婚のときに言われた「のんきでしがらみのない3男の妻」。しばらく土浦にいて東京に帰る予定だった私の予定は、兄の死であっけなくつぶれてしまった。兄の葬式は、仙台での東北大学医学部葬、土浦でのフレンド教会葬。たくさんの人たちが来てくださった。
3人の兄弟の中で、体も一番大きく頑健で、頭もさえていて、東大卒業のときは恩賜の短刀をいただいた兄が、子供を残して先に亡くなるなんて考えられなかった。
奥井家当主の名は「吉右衛門」
親戚の人たちは、主人の名を「吉右衛門」に改名してくれと私にせまる。吉右衛門などという名を知らなかった私は、「歌舞伎役者ではありません」と言ってお断りした。吉右衛門は徳川時代の奥井家当主の名である。
毎日のように仏壇を拝みにくる親戚のおばさんたち。「仏壇掃除評論家」となって、私の掃除の仕方、花の生け方を批判して、不満を私にぶっつけて鬱(うつ)状態を晴らす。医者にかかるほどでないにしろ、一人一人が暗く、私も鬱っぽくなってしまっていた。
本格的な老人性鬱病になってしまったのは舅(しゅうと)。「死にたい。誠一に会いたい」と言い出すと、大変だ。細いひもの類を探してきて、ぐるぐる首に巻き付けてしまう。(随筆家、薬剤師)

![くずかごの唄 77[1073]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/01/af550c6e893e45dc02ab402f9f332b9d-696x308.jpg)
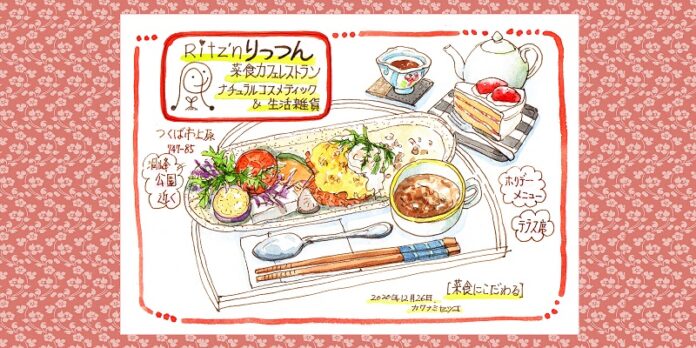

![霞ヶ浦から朝焼けの筑波[969]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/01/e31d9c7963771de40b11f7fa2796a7c2-696x392.jpg)
![冬の筑波山麓[967]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/01/3314700160ba6d2a577068f8c6247c20-696x392.jpg)

![映画探偵団 39[930]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/01/e9c9f369008a208eb61cb2924b6c9902-696x389.jpg)













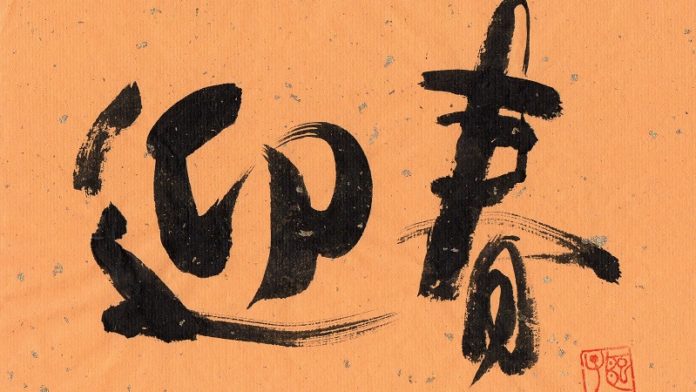
![吉田礼子 9[748]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2020/12/443e5a93fdd553e82d4563ce37f4619e-696x391.jpg)