【コラム・田口哲郎】
前略
この世には誰にも疑えない現実がある一方で、「信じるも信じないも、あなた次第」としか言えない超現実があります。神秘体験はそれを垣間見ることです。でも、自分が不思議だと思うことは他人にとっては不思議ではないことがあります。神秘体験を他人と共有することは難しいです。
5年ほど前に奈良を旅行しました。東大寺や平城京、薬師寺を観光しましたが、メインは二上山(にじょうざん)でした。折口信夫の小説『死者の書』を読んでぜひ行きたいと思っていたのです。山頂には大津皇子(おおつのみこ)の墓があります。物語は藤原南家の郎女(いらつめ、中将姫)が大津皇子の亡霊に導かれて神がかりのように曼荼羅(まんだら)をひと晩で織り上げ、自らも極楽浄土に誘われるというもの。その曼荼羅は山麓にある當麻寺(たいまでら)のご本尊になっています。
二上山は藤原氏に所縁(ゆかり)深い場所で、藤原氏の祖・藤原鎌足が天皇のための清水を探し彷徨(さまよ)っていたところ、二上山で発見したという伝承があります。私の父方の家紋は藤原氏の家紋、下り藤です。長崎平戸藩の家老の家系ですが、たどれば藤原氏に行きつくはずです。
さて、二上山は標高500メートル程度ということで、簡単なガイドブックを頼りに上り始めました。二上神社口駅から山頂に行き、當麻寺方面に降りるというコースです。最大の過ちは持参したペットボトルに少量の水しか入っていなかったこと。
鎌足公の水? 癒しの清水
山頂には難なく着きました。大津皇子の墓に拝礼し下山する段で水が切れました。高尾山頂のように自販機はありません。仕方ないと歩き始めたら見知らぬおばさんに話しかけられました。當麻寺に行きたい旨を伝えると、「こっちが近道やで」と指さされた方に進みました。
ところが行けども當麻寺に着かず、断崖絶壁に行き当たり、出遭った人に聞くと當麻寺とはまるで反対方向だと言われ、山頂に戻ることに。その途中でも堂々巡りをして喉の渇きと疲労に絶望していました。すると水の音がします。湧き水です。清水が竹筒から涼し気に流れ落ちています。飲める水だと札が立っています。私は夢中で飲みました。
あれほどおいしい水はなかったです。渇きが癒され、力を得たら見落としていた道に気づき、進むと木漏れ降り注ぐ緩やかな林道になり、しばらくして當麻寺に着きました。當麻寺の曼荼羅を眺めているうちにハッとしました。あの水が鎌足公の清水だったのでは…。ここは藤原氏の山で、自分は遠い祖先に導かれて無事に曼荼羅を拝めているのではないか。
言葉にできない感覚に満たされ、阿弥陀(あみだ)仏の前で感涙を零(こぼ)しました。後で地図を見返したら、おばさんのお節介がなければ、水がある道には入れなかったことも分かりました。私はこれを神秘的体験だと思いますが、ただの偶然の連続とも言えます。この手の体験は当事者でない場合、信じるも信じないも、あなた次第ということになってしまいます。ごきげんよう。
草々(散歩好きの文明批評家)


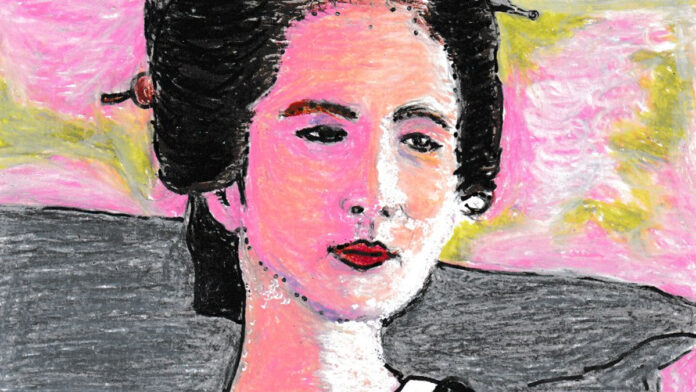


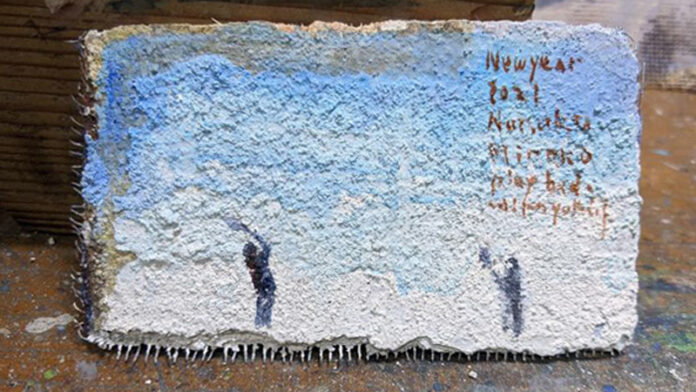




![ことばのおはなし 30[1298]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/02/1b96ceee15dfd4e09c31feef4c6ed613-696x460.jpg)
![雑記録 20[1255]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/01/ba5d946e93534ea8197018a89c942bf5-696x522.jpg)








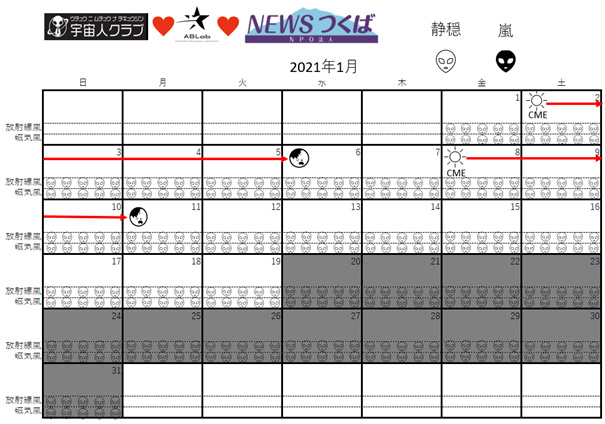


![霞ヶ浦plus[1083]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/01/e1e381f302fcbe436a7fad16a735df15-696x392.jpg)