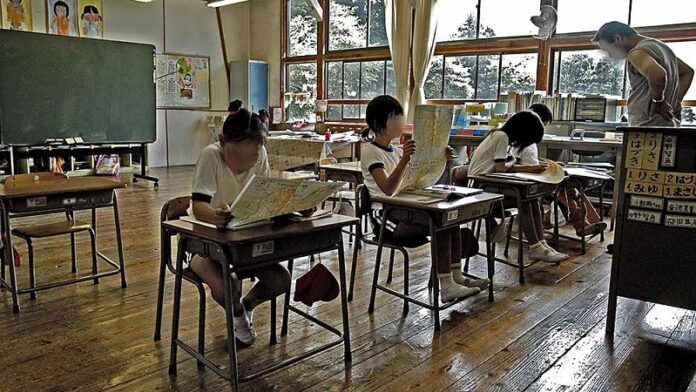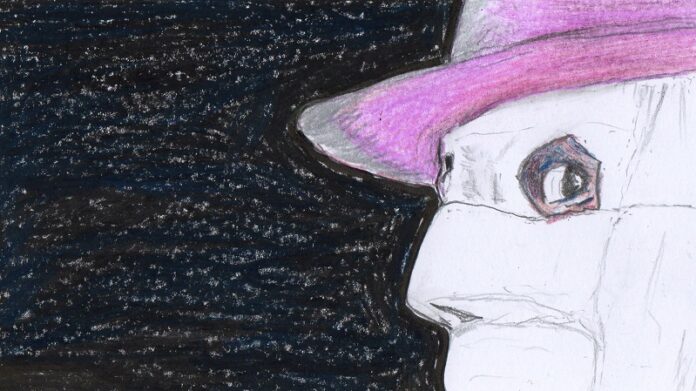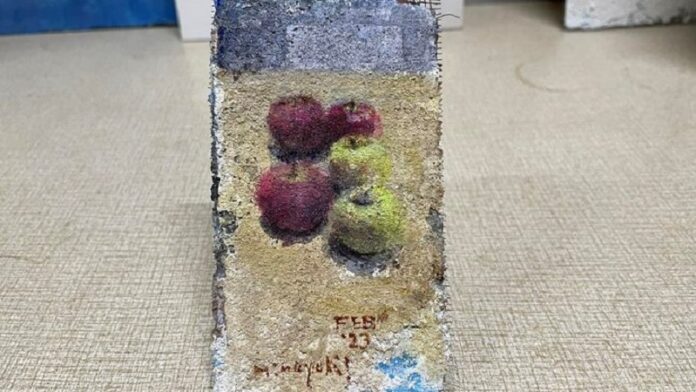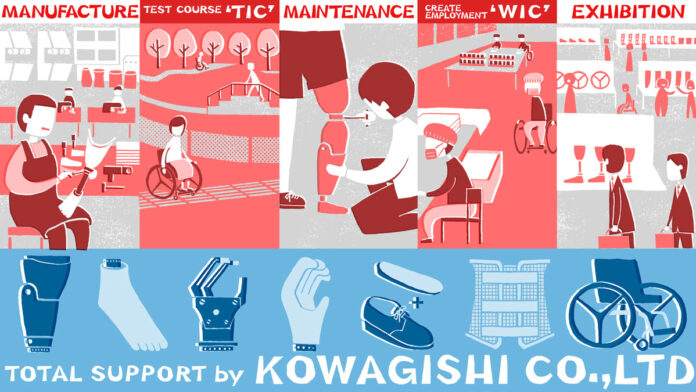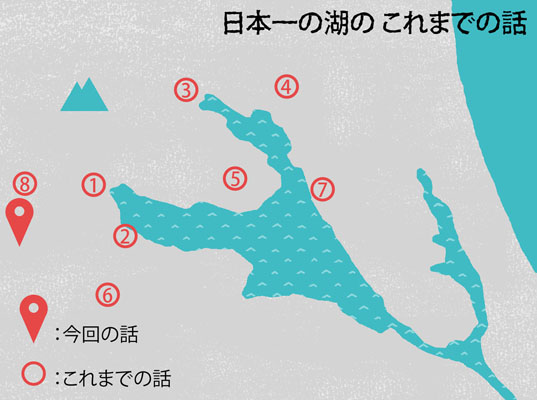【コラム・浅井和幸】船は軽いから水に浮きます。と言っても鉄の塊が軽いと言えるのでしょうか。地球上にあるものはすべからく万有引力の法則をもって地球に引っ張られている。いわゆる物は下に落ちる。あれっ? ヘリウムが入った風船は浮いているなと思う。そうだ、ヘリウムが入った風船は軽いから浮いているんだと考える。
この流れはおおよそ間違っていないと思います。でも、風船より軽いと思われる、ティッシュ1枚や糸くずは下に落ちますね。軽いから浮いて空まで届いていたヘリウム入りの風船と、ゆっくりでも落ちていく糸くずは何が違うのでしょうか。何か引っかかりますね。
この「軽い」という抽象的な言葉が、「引っかかり」の原因となります。軽いとは、何キロ以下が軽いのでしょうか?と考えるのは間違いです。この場合、軽いというのは風船や糸くずの重さが問題ではありません。それぞれの体積に対する重さが、同じ体積の空気より軽いか重いかで、空気に浮くか落ちるかの違いとなります。
冒頭の鉄の塊である船も同じです。船は中が空洞で空気がたくさんあるので、同じ体積の水よりも軽いから浮くわけです。
分かろうとする努力や姿勢が大事
このように基準が違うと、同じ言葉でも全く別のことを指し示し、全く別のふるまいをしてしまいます。明日はいつもよりも早めに家を出るから、早めに用意をするんだよと伝えます。いつもは、8時に家を出ているとします。さて、「いつもより早い」は何時を指すでしょうか。6時30分でしょうか。それとも7時59分59秒でしょうか。
一つの場所でほうきを動かしているだけの子どもがいました。教室全てを掃いてほしいと思った先生は、もっと一生懸命掃除をしなさいと注意しました。その子は、一生懸命一つの場所を倍のスピードで掃き始めました。
一生懸命に頑張っているけれど悪循環を起こしている人に対して、もっと頑張れと言うこと。我慢することも、頑張ることと似た性質があります。頑張ること、我慢することにも、ある程度の心身の余裕が必要です。場合によっては、頑張ることや我慢することのためには、休憩することや手を抜くことも必要になってくることもあります。
うまくいっていない時には、より慎重に、より正確に状況を把握して、より慎重に言葉を選んで使うことが大切です。「より正確に」が大切で、私たちは真に物事を正確に捉えること自体が出来ないのですから、「より正確に」なのです。
分かった気にならず、分かろうとする努力や姿勢を取り続けることは、分かり合えることに近づくとても重要な要素となるでしょう。(精神保健福祉士)