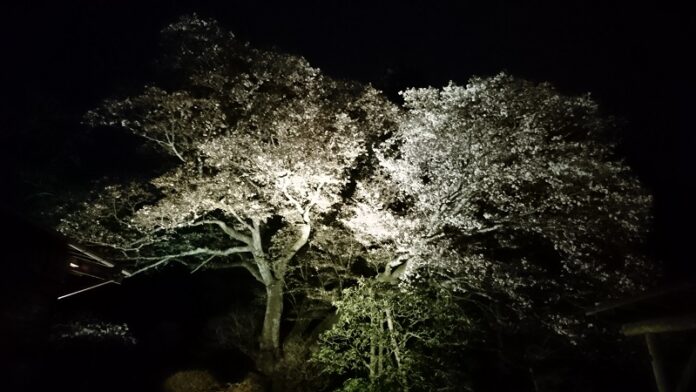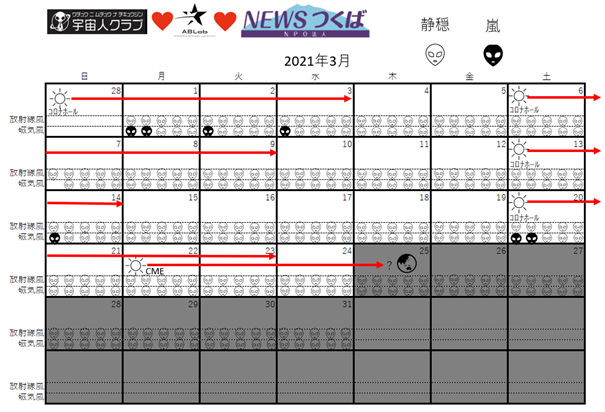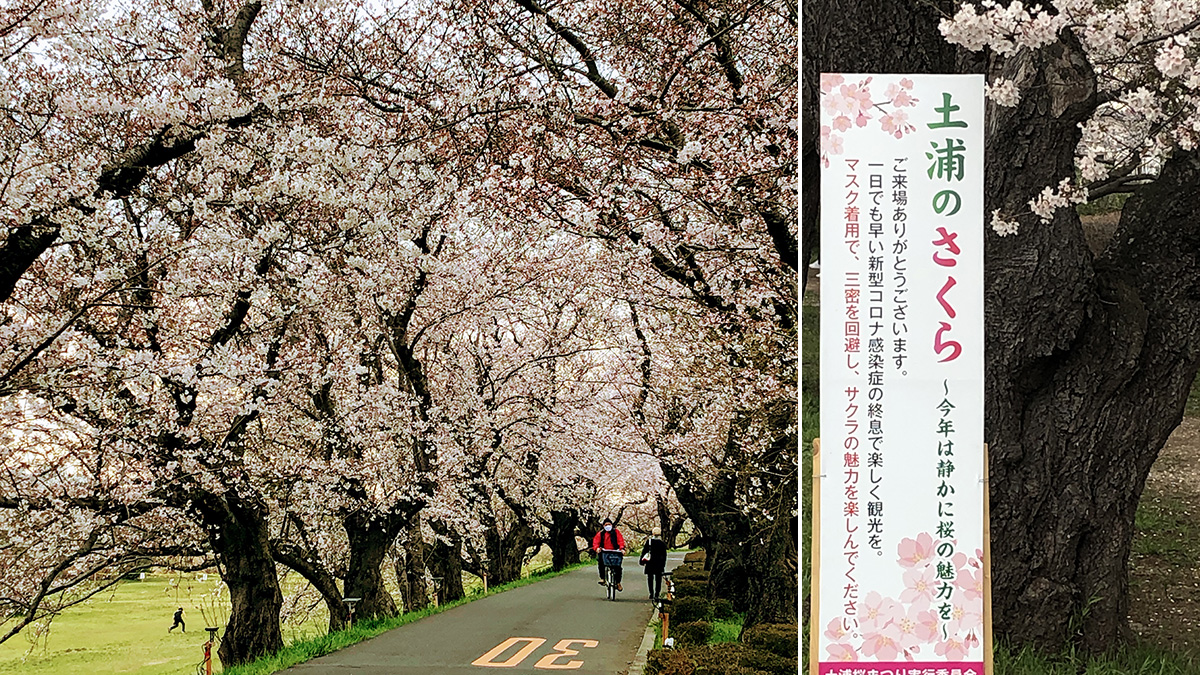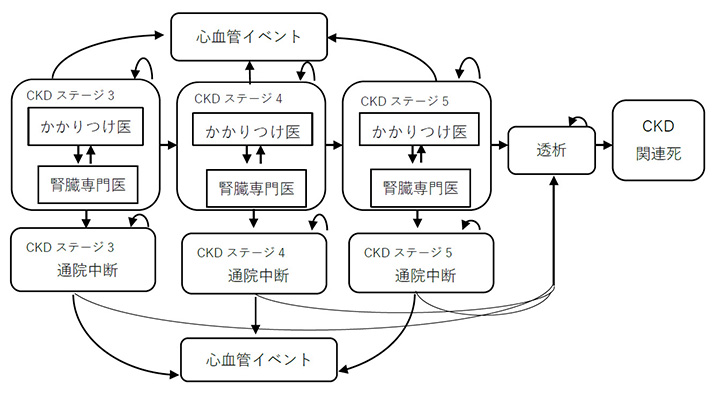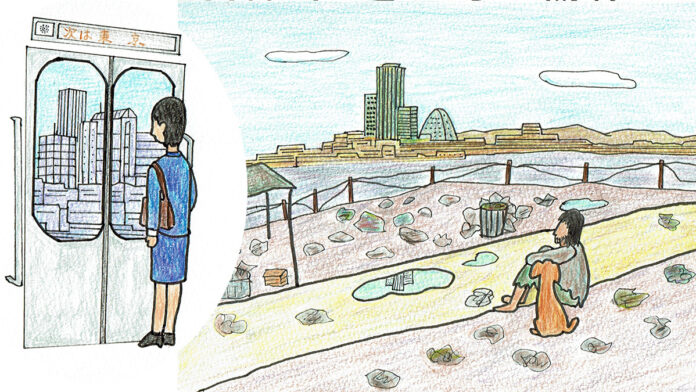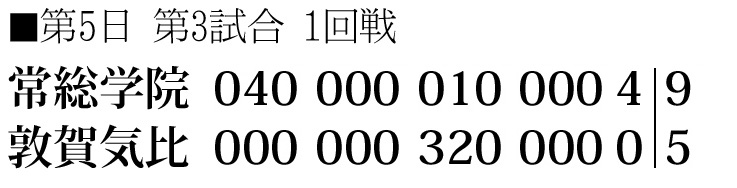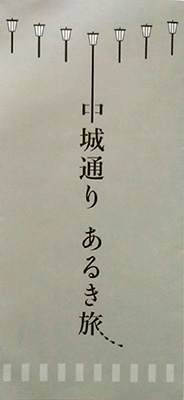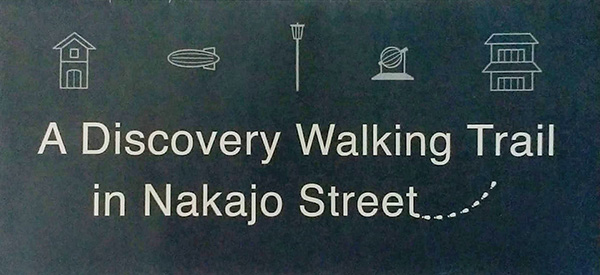3人制バスケットボールの日本一を決める第6回3×3(スリーバイスリー)日本選手権大会(日本バスケットボール協会主催)のファイナルラウンドが3月22、23の両日、新宿住友ビル三角広場(東京都新宿区)で開かれ、男子の部で茨城県代表のアルボラーダ(ALBORADA)が準優勝した。戦い終えて、代表の中祖嘉人さん(3×3日本代表サポートコーチ)や選手たちに話を聞いた。
 気合を入れる4人。左から改田、小澤、山本、石渡(写真提供:日本バスケットボール協会)
気合を入れる4人。左から改田、小澤、山本、石渡(写真提供:日本バスケットボール協会)ファイナルラウンドの相手はいずれもプロチーム。1回戦は唐津レオブラックス(佐賀県)を21-13、2回戦は八戸ダイム(青森県)を21-15と相次いで撃破。準決勝ではウィル(東京都)と対戦、点の取り合いから延長21-19で勝ちきった。メンバーの山本陸は「相手は1対1に自信を持つチームで、タイトな守備が必要。自分たちが重視する攻撃から守備への切り替えで、パスアウトのカットを狙うとか、リバウンド時のポジション取りなど、タフでハードな守備を心掛けた」と振り返る。
決勝の相手ビーフマン(高知県)は、保岡龍斗(3×3日本代表候補、B1秋田ノーザンハピネッツ)、湊谷安玲久司朱(元B1横浜ビー・コルセアーズ)らを擁する強豪。チーム平均身長189センチと、体格差の大きい相手にゴール下で押し込まれ、14-21で敗れた。「シュートファールからフリースローを与え、楽に点を取らせてしまった。ファールにならない守備が必要だった」と改田拓哉。
生え抜き選手で挑む
アルボラーダは2013年につくばで結成された、3人制と5人制バスケのクラブチーム。中祖代表にとって今回の日本選手権準優勝は、昨年のチームつくばを率いての優勝に続く2年連続での決勝進出。だがその価値は昨年とは全く異なるという。
「チームつくばは、つくばから世界を目指すというコンセプトで、元B2茨城ロボッツの大友隆太郎(現B1滋賀レイクスターズ練習生)ら、プロ選手を集めて作ったチーム。それに対し今年は、子どものころから一緒に練習してきた生え抜きの選手たちで挑んだ」
 決勝戦、体格差のある相手と競り合う石渡(左から2人目)と山本(右端)(写真提供:同協会)
決勝戦、体格差のある相手と競り合う石渡(左から2人目)と山本(右端)(写真提供:同協会)メンバーは小澤峻(つくば市、土浦二高出身)、山本陸(牛久市、土浦日大高出身)、石渡優成(牛久市、藤代高出身)、改田拓哉(我孫子市出身)の、いずれも20代前半の4人。平均身長は177センチで、出場チームの中では格段に小さく、身体能力でも突出したものは持っていない。それでも3×3のU-18日本選手権では、2017年の第3回大会優勝など、3年連続で上位入賞を果たしてきた。オープンカテゴリーの大会は今回が初めてだが「優勝しかない」との意気込みで臨んだ。
次に続く選手らの目標に
道のりは厳しく、県予選では最終戦を延長で制し、東日本予選では11チーム中5位というギリギリの成績で勝ち抜いた。ただしその中にはプロリーグ「3×3エグゼプレミア」の今季優勝チームであり、小林大祐(茨城ロボッツ)ら日本代表候補2人を擁する宇都宮ブレックス(栃木県)を破るなどの快挙もあった。
「残念ながら優勝は逃したが、ここまで勝てたことが本当にうれしかった。彼らのことは子どものころから見てきた。体が大きくなり技術も上達したが、それ以上に人間としての強さ、メンタル面での成長が感じられた」と中祖代表。
 準決勝戦、ドリブルで切り込む山本(写真提供:同協会)
準決勝戦、ドリブルで切り込む山本(写真提供:同協会)「彼らはいわゆる普通の選手ばかり。中学や高校でも目立ったキャリアはないが、時間をかけて努力し、正しいトレーニングを積むことで、日本のトップと渡り合えるまで成長できた。後に続く選手たちに希望を与えられる存在」と小山涼コーチ。彼らの活躍を見て、一緒に練習してきた小中学生らのモチベーションがいま、非常に高まっているという。
4人は今大会を一つの区切りとして、今後はそれぞれ次のステージへ進む。改田はプロチームから日本代表や世界での活躍を目指す。指導者として後輩の育成に携わる山本は「高校生や大学生のメンバーを伸ばし、次は彼らに日本一をつかんでもらいたい」と目標を語る。(池田充雄)