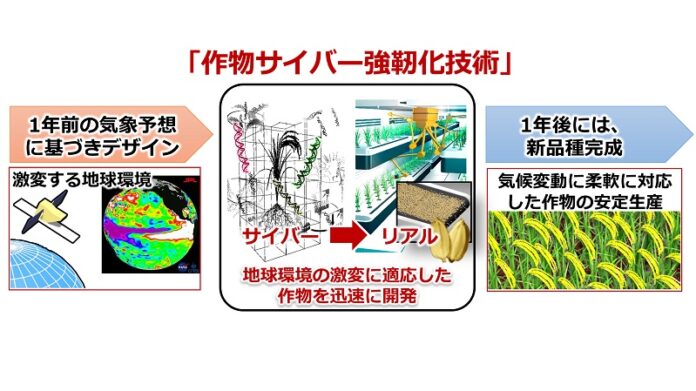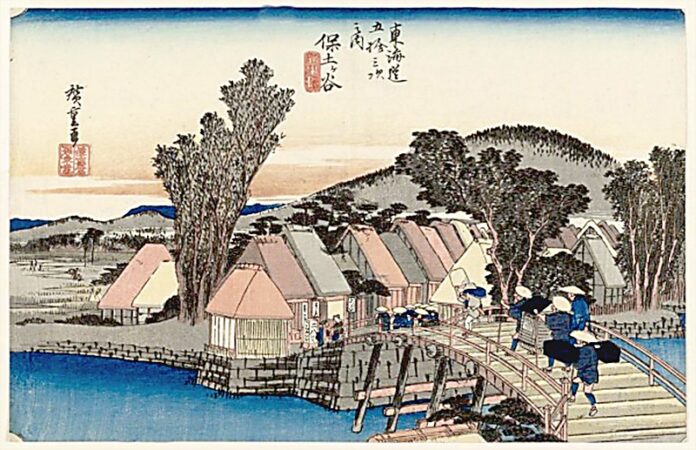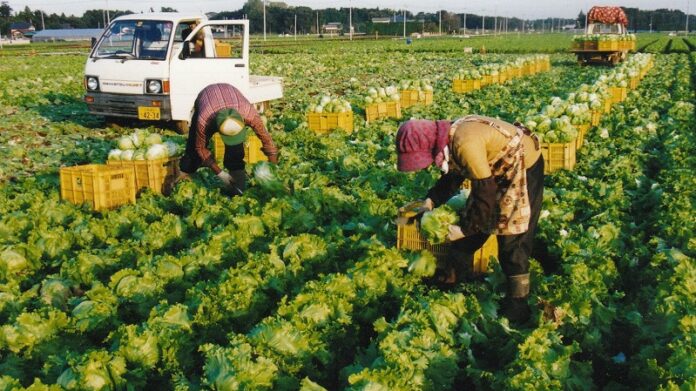明治時代にはどんな町や村にも存在した染物屋は、衣料品の近代化とともに姿を消していった。染物屋という業種が潰えたわけではないが、その多くは工業化の道をたどっている。そのような現代において、「染」の世界を通してネットワークを築く人々と出会った。つくば市、土浦市で染色を営む染色人を4回にわたって紹介する。
藍は地域の歴史と文化
つくば市神郡で藍染工房・藍染風布(あいぞめふうぷ)を営む丹羽花菜子さん(36)を訪ねた。神郡のような場所で染色ができるのか?という素朴な疑問だったが、丹羽さんの話はまったく逆であった。
「野良着などの需要から、明治以前はどんな小さな町や村にも必ず一軒は『紺屋(こうや)』があったと言われていて、藍染は人々の暮らしの中で身近な存在だったんですよ」
 丹羽花菜子さん
丹羽花菜子さん丹羽さんの場合、それだけではなかった。神郡を選んだことは偶然だったが、定住してみて藍染との不思議な縁に恵まれたという。
「大学では選択したコースがテキスタイルデザイン(織物・染物のデザイン)に特化していました。私は日本古来の伝統的な染色に興味があったので、4年生の時に東京の青梅市にあった藍染工房にアルバイトで入り、そのまま就職したのです」
それが藍染との出合いで、9年ほど働き、独立した。夫の実家がある常総市で、藍染の原料となる植物・蓼藍(たであい)の栽培を始めたものの、常総市から眺める筑波山の姿に魅せられ、山麓で藍染をしながら過ごせたらいいねという単純な気持ちで土地を探しに出た。
無事だった4甕
「そこで、地主さんの近所に50年ほど前まで藍染をやっていた職人さんがいらっしゃることを聞き、訪ねてみると、藍甕(あいがめ)が残っていたのです。本当はいくつも保管されていたのだそうですが、東日本大震災の際にほとんどが割れてしまい、無事だったものが4甕だったと。それを譲っていただき、偶然にも筑波の藍染を受け継ぐこととなりました」
 受け継がれた藍甕
受け継がれた藍甕丹羽さんはそれまで、ポリタンクを使って染液の藍建てをしてきた。工程はタンクでも甕でも同じだが、地域に眠っていた歴史を受け継ぐという意味で、丹羽さんは筑波山麓にいざなわれていたのである。
「天然の藍は世界最古の染料とも言われていて、日本では奈良時代以降全国に広まりましたが、明治に入ってから化学合成で合理的、効率的に染色できる技術、俗にいう『インディゴ染』が、地域の藍染を衰退させました。自然界で藍以外に『青い色』を出せる植物は、世界的にも少ないのです。日本では現在、徳島県が蒅(すくも)の一大生産地ですが、少しずつ後継者不足が取り沙汰されるようになっています。でも、かつてはどんな土地でも原料を育て、藍染をなりわいとする人々はいました。筑波の地もそうであったように」
 蓼藍の花と葉(丹羽さん提供)
蓼藍の花と葉(丹羽さん提供)藍染の原料となる蓼藍は一年草だ。収穫して乾燥、適度な水分を加えて堆肥化させたものが蒅だ。これを甕やタンク内で灰汁(あく)、貝灰(かいばい)、日本酒、ふすまを混合して発酵させる。この蒅による藍染は、日本独特の文化だ。
藍染の染液作りで特徴的な部分は、木灰の灰汁によるアルカリ性の発酵によるものだ。強アルカリの環境下でなければ、蒅の中の青い色素の元は還元されず、素材に定着することはない。液に浸した素材を引き上げ、空気中の酸素に触れることで、初めて青色が定着する。
 蓼藍からすくもが作られ、染料になる(丹羽さん提供)
蓼藍からすくもが作られ、染料になる(丹羽さん提供)「藍染の濃淡は、素材を染料に出し入れする回数で変わっていきます。ただし常に1回の染まり方が同じ、というわけではありません。人間と同じで、体力を使うと疲れてしまい、徐々に染まり方が弱くなります。丸1日染めの作業をしたら、2~3日は染めずに甕を休ませることで、再び染まる力が回復します。こうした染色のサイクルや、青を染料として定着させる技術は、とても繊細で高度です。それらがどんな地域にもなりわいとして根付いていたということに、天然染色である藍への憧れがあります」
今、つくば市を中心に染色を営む人々の横の繋がりができつつあり、丹羽さんも月に一度、作家仲間と交流を兼ねて持ち寄った取り組みの成果を情報交換している。
 藍染の様々な濃淡
藍染の様々な濃淡年が明けると、丹羽さんには2人目のお子さんが誕生する。そのため、個展の開催はしばらく控え、代わりに工房に客を招いて染色体験を企画していくという。
「本心を言うと、伝統技術の継承であるとか、世界最古の染色手法であるとかの、重大な使命を帯びてのことではないんです。神郡に住んで、近隣の皆さんとの交流が生まれ、その優しさやおおらかさで守られています。ならば私のできることで、地域に寄り添って恩返ししていきたい。その一方で、藍染めに取り組みたいという人々にも、これは小さいけれど素敵な産業だということを伝えたい」
藍がもたらす染色の色彩は、古代人が眺めていた空や海の色合いだと丹羽さんは語る。青い色には心の沈静作用があると同時に、孤独感を覚えることもある。それらは人々の遺伝情報にある、古代人の青に対する感情。そのような悠久の想いが、藍で再現され、現代まで連綿と続いているという。(鴨志田隆之)
丹羽 花菜子(にわ かなこ)
1985年 北海道札幌市生まれ
2008年 武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科テキスタイル専攻卒業
大学在学時より、東京都青梅市の藍染工房壺草苑(こそうえん)で勤務し、2016年、つくば市に移住。2017年、藍染風布として作家活動を始め、2020年、筑波山麓に工房を移転。
藍染風布 https://www.aizome-foopu.com/